国民年金はいつまで払う?65歳まで延長は?受給額まで徹底解説
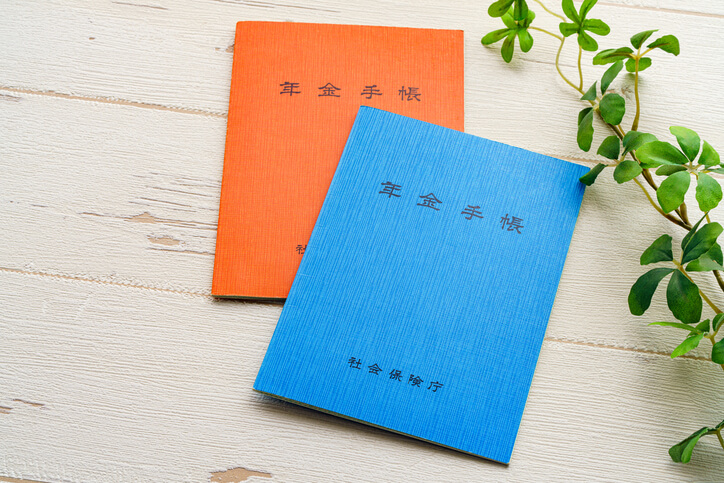
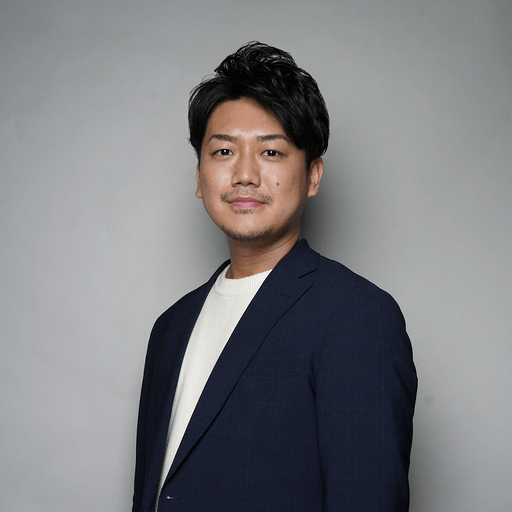
国民年金は、日本の公的年金制度の基盤となる重要な年金です。
現役世代は公的年金制度に基づき保険料を納める義務がありますが、保険料はいつまで支払う必要があるのでしょうか。
この記事では、国民年金の基本的な仕組みや保険料の支払い期間、支払う保険料の額について詳しく解説します。
さらに、受給できる年金額や年金を増やす方法も紹介するので、ぜひ参考にしながら老後に向けた資産計画を立てていきましょう。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎
この記事の目次
国民年金とは
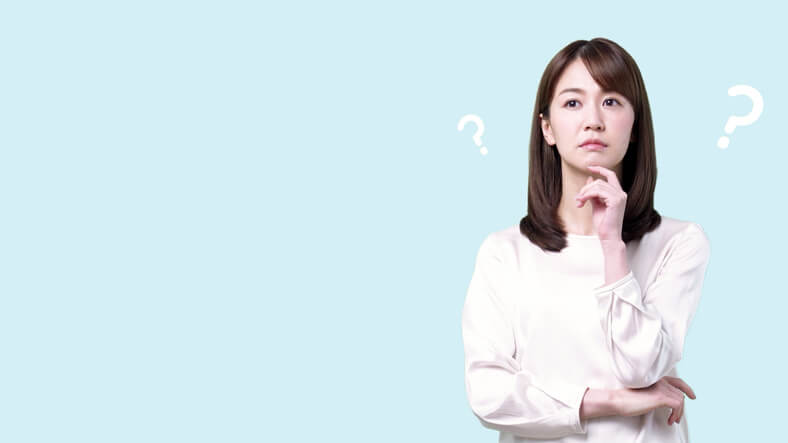
国民年金は、日本国内に居住する20歳から60歳未満のすべての人が加入を義務付けられている公的年金制度です。
日本の年金制度の基盤であることから「基礎年金」とも呼ばれています。
国民年金は主に以下の3つの年金から構成されます。
- 老齢基礎年金:老後の生活を経済的に保障
- 障害基礎年金:病気や事故で生活や仕事が制限された場合に保障
- 遺族基礎年金:被保険者が死亡した場合に遺族の生活を保障
これにより、国民年金は老後の生活保障にとどまらず、障害や死亡など予期せぬリスクにも対応できる社会保障制度となっています。
年金制度の仕組み
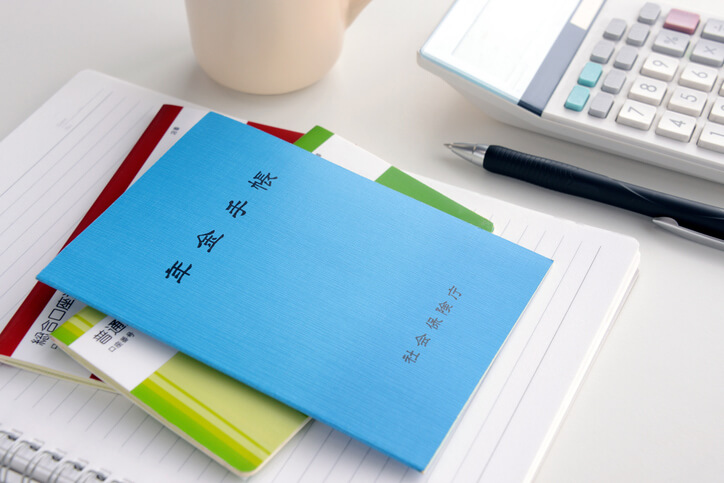
日本の年金制度は「国民年金」「厚生年金」「私的年金」の3階建て構造になっています。
1階部分はすべての国民が加入する国民年金、2階部分は会社員や公務員が加入する厚生年金、3階部分は任意で加入する私的年金です。
私的年金には以下のような制度があります。
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
- 企業型確定拠出年金
- 確定給付企業年金(DB)
自営業者やフリーランス、学生などは厚生年金に加入できませんが、国民年金基金やiDeCoを活用することで年金制度の2階・3階部分を補完できます。
今回は、すべての国民が加入する国民年金について詳しく解説していきます。
国民年金はいつまで支払うのか?

年金制度の1階部分である国民年金ですが、保険料はいつまで支払う必要があるのでしょうか。
ここでは国民年金保険料の支払い期間について解説していきます。
国民年金保険料は60歳以降は支払い義務なし
国民年金の保険料支払い期間は、原則20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)です。
その間に「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」が合計10年以上あれば、65歳から年金を受給できます。
受給できる年金額は納付した期間に応じて変動し、40年間全て納めた場合は満額受給が可能です。
基本的には60歳で保険料の支払いは終了しますが、以下の場合は60歳以降も任意加入ができます。
- 年金の受給資格を満たしていない場合
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が40年間(480ヶ月)未満の場合
60歳以降に該当する方は任意加入を検討してみましょう。
国民年金の支払期間が65歳までに延長される?
少子高齢化の影響で年金財源の確保が課題となっていることから、厚生労働省では保険料支払い期間を65歳まで延長する案が議論されています。
この案が実現すると、保険料の支払い期間は最長45年となります。
しかし、2024年7月に実施された公的年金の「財政検証」で、年金財政の見通しが改善したことから、支払い期間の延長は見送られました。
今後、納付期間の延長が再び検討される可能性はありますが、2025年2月時点では保険料の支払い期間は60歳までです。
国民年金の保険料はいくら支払う

国民年金保険料は、令和6年度時点で1ヶ月あたり16,980円です。
納付対象月の翌月末日が納付期限となっていますが、末日が土日・祝日・年末年始に当たる場合は翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限となります。
納付する保険料を安く抑えたい場合、前払い(前納)がおすすめです。
まとめて前払いすることで割引が適用され、支払う保険料の負担が抑えられます。
クレジットカード払いや口座振替による納付でも割引が適用されるため、上手く活用して保険料の負担を軽減しましょう。
令和6年度(令和6年4月から令和7年3月まで)の国民年金保険料は1ヶ月あたり16,980円です。
納付期限は納付対象月の翌月末日で、月の末日が土日・祝日・年末年始(12月31日、1月2日および1月3日)にあたる場合は翌月最初の営業日が納付期限となります。
保険料の負担を抑えたい場合は、前払い(前納)がおすすめです。
6ヶ月・1年・2年単位でまとめて前払いすると割引が適用され、支払う保険料を節約できます。
クレジットカード払いや口座振替による納付でも割引が適用されるため、上手に活用して、保険料負担を軽減しましょう。
出典:日本年金機構「令和6年3月から国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納について、年度の途中からまとめて振替(立替)できるようになります」
国民年金はいくらもらえる?

国民年金(老齢基礎年金)の満額受給額は令和6年4月分より月額68,000円(年間816,000円)に引き上げられています。
令和5年度は月額66,250円(年間795,000円)であり、今回の改定では原則2.7%の引き上げが行われました。
受給額は物価や賃金の変動を考慮して見直されるため、今後も変動する可能性があります。
最新の受給額については定期的に確認しておきましょう。
国民年金をもらうには最低10年以上支払っている必要がある
国民年金を受給するには、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上必要です。
20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)のうち10年(120ヶ月)以上保険料を納めていないと、老後に年金を受給できないため注意が必要です。
また、保険料納付期間が40年に満たない場合は、納付した期間に応じて減額された年金が支給されます。
年金の受給額を満額に近づけるためには、60歳以降に任意加入制度を利用して不足分を補う方法を検討すると良いでしょう。
国民年金の金額がいくらか求める計算式
国民年金の受給額は以下の計算式で求められます。
- 年金受給額(年間):816,000円(満額支給の場合の年間受給額) × 保険料納付月数 / 480ヶ月(40年)
例えば、保険料納付期間が10年(120ヶ月)の場合は、以下の計算です。
- 816,000円 × 120ヶ月 / 480ヶ月 = 204,000円
この場合、年間で204,000円(月額17,000円)が受給額となります。
納付期間が短いほど受給額も少なくなるため、自分の納付月数を確認し、受給額をシミュレーションしておくと良いでしょう。
保険料納付期間が不足している場合は、任意加入制度を活用して納付期間を延ばす方法も検討してみてください。
もらえる年金額を増やす方法

国民年金の受給額を増やす方法として以下の3つが挙げられます。
- 付加保険料制度の活用
- 任意加入制度の活用
- 年金生活者支援給付金の活用
それぞれの方法について解説していくので、ぜひ参考にして老後の年金受給額を増やしましょう。
付加保険料制度の活用
国民年金第1号被保険者(自営業者や学生)や65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料制度を利用することで将来受給する年金額を増やすことができます。
付加保険料制度とは、毎月の保険料に月額400円を上乗せして納付することで、将来の老齢基礎年金の受給額を増額できる制度です。
付加年金の受給額(年額)は以下の計算式で求められます。
- 200円 × 付加保険料を納めた月数
例えば、40年間(480ヶ月)付加保険料を納付した場合は、「200円 × 480ヶ月 = 96,000円」となり、通常の年金受給額816,000円に加えて96,000円が上乗せされ、年間912,000円を受給できます。
付加保険料のメリットは、2年以上年金を受給すれば元が取れる点です。
老後に向けて年金を増やしたい自営業者や学生は、この制度を活用することを検討すると良いでしょう。
任意加入制度の活用
年金保険料の納付期間が10年に満たず受給資格がない場合や、納付期間が40年未満で満額受給できない場合は任意加入制度を利用できます。
任意加入制度とは、60歳以降も任意で国民年金に加入し、受給額を増やせる制度です。
任意加入をするための条件は以下の通りです。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ受給をしていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480ヶ月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
上記の条件を満たしていれば、60歳以降も国民年金の保険料を支払えます。
納付期間が40年に満たず「老後の年金が少ない」と感じる方は、任意加入制度を検討すると良いでしょう。
年金生活者支援給付金の活用
国民年金の受給者で一定の所得条件を満たす場合、「年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢基礎年金の受給者の場合、以下のすべての条件を満たすことで給付金を受給できます。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が、
・昭和31年4月2日以後に生まれた方は889,300円以下
・昭和31年4月1日以前に生まれた方は887,700円以下
障害年金・遺族年金の受給者も所定の条件を満たすことで支援給付金を受給できます。
年金受給額を増やす方法として、条件を満たす場合は年金生活者支援給付金の活用も検討すると良いでしょう。
まとめ:国民年金の仕組みを理解して賢く老後資金を準備しましょう

国民年金は、日本国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての国民が加入する公的年金制度です。
原則として60歳まで保険料を支払う仕組みになっていますが、将来的には支払い期間が延長される可能性もあります。
国民年金の基本的な仕組みや保険料支払い期間を正しく理解しておくことが大切です。
また、本記事で紹介した保険料納付額や年金受給額を参考に、老後に向けた資産計画を考えることも大切です。
付加保険料制度や任意加入制度なども活用しつつ、計画的な資産準備を進めていきましょう。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎








