【2025】NISAとiDeCoはどっちから始める?併用できるかや違いを解説

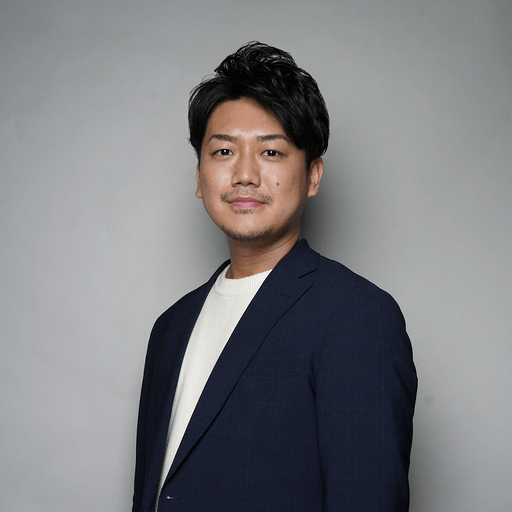
「NISA」と「iDeCo」は、資産形成を支援するために国が推奨している資産運用制度です。
どっちも節税効果があり、お得に資産運用するための制度として注目を集めています。
しかし、それぞれの特徴やメリットなどを理解していないと、どっちを活用すべきか悩んでしまいます。
この記事では「NISA」と「iDeCo」の特徴や違い、どっちがおすすめかを解説します。
各制度の特徴をしっかりと理解し、資産形成に活用していきましょう。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎
この記事の目次
NISA(積立NISA)とiDeCoの特徴
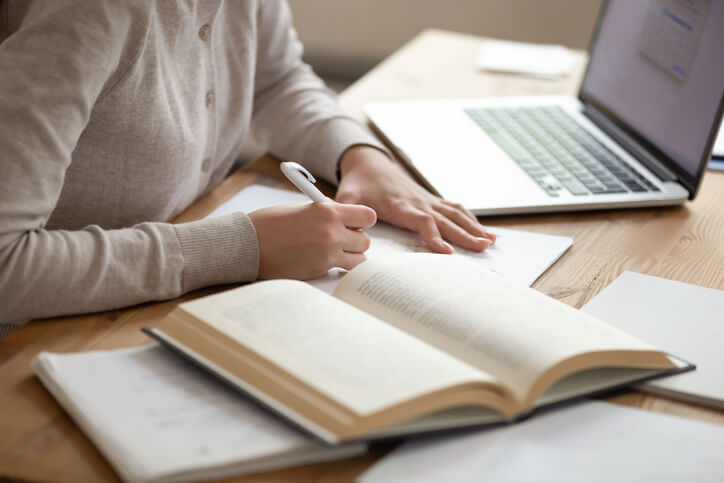
まずはNISAとiDeCoの特徴について解説します。
どっちの制度を利用すべきか判断する際は、それぞれの制度の特徴や違いを理解することが重要です。
ここではNISAとiDeCoの特徴をまとめています。
年間投資額や運用期間などが細かく異なることがわかります。
| NISA | iDeCo | |
| 利用条件 | 18歳以上の方 | 原則として20歳以上65歳未満の方 基本的に公的年金被保険者でること |
| 最大年間掛金 | 最大360万円 (成長投資枠240万円+つみたて投資枠120万円) | 年間24.0万円から81.6万円 (公的年金の加入区分によって異なる) |
| 主な 対象商品 | 【成長投資枠】上場株式、投資信託等 【つみたて投資枠】長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 | 投資信託、保険、定期預金 |
| 運用期間 | 無期限 | 原則60歳まで |
| 資産の 引き出し | いつでも可能 | 原則60歳までは不可 |
| 税制優遇 | 運用益や配当が非課税 | ・掛金が全額所得控除 ・運用利益が非課税 ・受取時に所得控除が適用 |
出典:iDeCo公式サイト「iDeCoの加入資格・掛金・受取方法等」
出典:金融庁「NISAを知る」
2024年から新しいNISAに変わった
2024年1月1日から新しいNISA制度(新NISA)が始まりました。
2023年までの旧NISAでは、「一般NISA」と「つみたてNISA」のどちらか一方しか利用できませんでしたが、新NISAでは「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の併用が可能となり、制度の仕組みも大幅に変更されています。
2023年以前にNISA口座を保有している方は、同じ金融機関に自動的に新しいNISA口座が開設されるため、特別な手続きの必要はありません。
2023年までの旧NISAは、新しいNISAとは別枠で旧制度の非課税枠が適用されます。
旧NISAから新NISAの非課税投資枠の移管はできない点に注意しましょう。
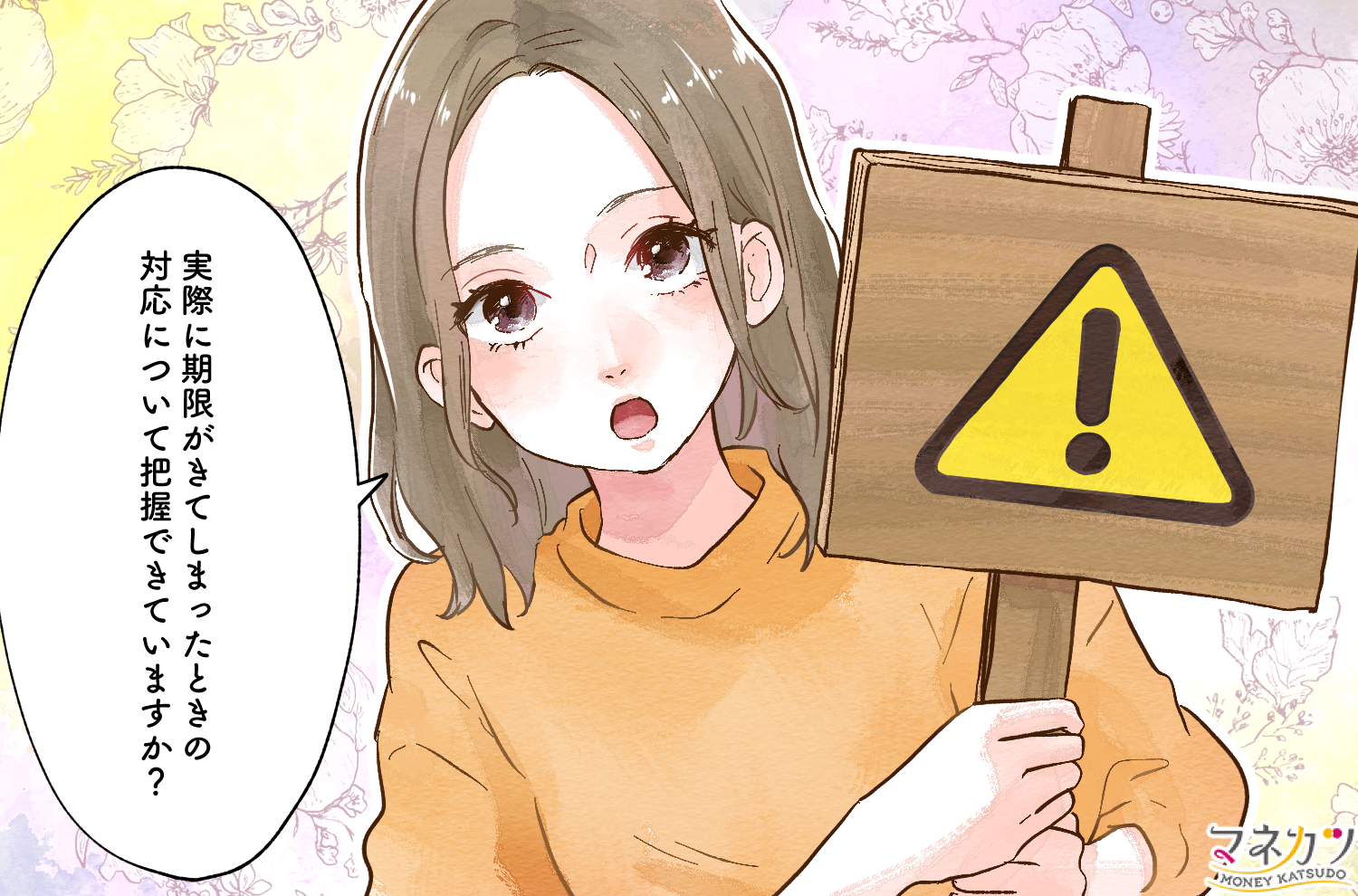
一般NISAの利用期限は?積立NISAとの違いやロールオーバーを解説
NISA(新しいNISA)の特徴
新しいNISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの非課税枠を併用できます。
非課税枠の概要は次のとおりです。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有期間 | 無期限 | |
| 非課税保有限度額 | 1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで) | |
| 口座開設期間 | 恒久化 | |
| 投資対象商品 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 (旧つみたてNISA対象商品と同じ) | 上場株式・投資信託等(整理・監理銘柄や信託期間20年未満の投資信託、毎月分配型の投資信託、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除く) |
| 対象年齢 | 18歳以上 | |
新しいNISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能となり、それぞれの年間投資枠が大幅に拡大しました。
つみたて投資枠では年間120万円、成長投資枠では年間240万円の投資が可能で、非課税保有限度額は合計で1,800万円に設定されています。さらに、新しいNISAでは枠の再利用が可能です。
NISA口座で運用している金融商品を売却した場合、売却した分の非課税枠が再び利用できる点が特徴です。
また、従来の最長5年または20年だった非課税保有期間が無期限になり、老後に向けた長期的な資産運用にも適した制度となりました。
出典:金融庁「NISAを知る」

積立NISAとは?投資初心者におすすめの理由をわかりやすく解説
iDeCoの特徴
iDeCoは「個人型確定拠出年金」とも呼ばれており、公的年金に上乗せする私的年金制度です。
掛金の拠出や運用のすべてを自分で行い、拠出した掛金と運用益の合計額が年金、または一時金で給付される仕組みとなっています。
iDeCoは、税制面で以下の3つの優遇を受けられる点が大きな特徴です。
- 掛金が全額所得控除
- 運用で発生した利益が非課税で再投資される
- 年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金として受け取る場合は「退職所得控除」が適用される
税制面での優遇を受けながら老後の年金を準備できるのが、iDeCoの大きなメリットといえます。

iDeCo(イデコ)とは?仕組みや始め方、注意点をわかりやすく解説
NISAとiDeCoの違い
NISAとiDeCoは、いずれも税制面でのメリットを受けながら資産形成ができる魅力的な制度です。
資産形成の目的に合った制度を選ぶためには、各制度の違いについて把握しておくことが大切です。
ここでは、NISAとiDeCoの投資できる期間や金融商品、上限額の違いについて解説します。
投資できる期間
NISAとiDeCoの投資できる期間は、以下の表の通りです。
| NISA | 無期限 |
| iDeCo | 65歳まで |
新しいNISAでは、非課税保有期間が無期限となりました。
従来のNISAでは、非課税保有期間の終了に合わせて売却かロールオーバーの手続きが必要でしたが、新しいNISAではこれらの手続きが不要となります。
一方、iDeCoは65歳になるまで掛金を拠出でき、60歳から老齢給付金を受け取れる仕組みとなっています。
投資できる金融商品
NISAとiDeCoの投資できる金融商品は、以下の表の通りです。
| NISA | つみたて投資枠 | ・金融庁の基準を満たす一定の投資信託 ・金融庁の基準を満たす一定のETF |
| 成長投資枠 | ・上場株式 ・投資信託 ・ETF(上場投資信託) ・REIT(不動産投資信託) | |
| iDeCo | ・投資信託 ・保険 ・定期預金 | |
NISAの「つみたて投資枠」で投資できる金融商品は、長期の積立や分散投資に適した一定の投資信託およびETFのみです。
これは、金融庁が定めた基準を満たした金融商品に限られるためです。
一方、「成長投資枠」では、上場株式や投資信託、ETF、REITなど、上場しているほとんどの金融商品に投資できます。
iDeCoのは投資信託のような投資商品だけでなく、保険や定期預金といった元本確保型から選べる点が特徴です。

iDeCoのおすすめ銘柄12選!SBI証券や楽天証券を中心に金融機関も解説
拠出できる金額の上限額
NISAとiDeCoの拠出できる上限額は、以下の表の通りです。
| NISA | つみたて投資枠 | 年間120万円(最大1,800万円) |
| 積立NISA | 成長投資枠 | 年間240万円(最大1,200万円) |
| iDeCo | 年間24.0万円から81.6万円 | |
NISAでは、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円までと、投資上限に上限が設けられています。
NISA全体での保有限度額は合計1,800万円で、うち成長投資枠は1,200万円までです。
一方、iDeCoは職種や会社の制度によって拠出上限額が異なり、年間24.0万円から最大81.6万円まで運用することができます。
退職金や企業年金制度を利用できない個人事業主やフリーランスは上限額が高めに設定されている一方、会社員や公務員で企業型DCや企業年金に加入している人は拠出上限額が低くなりやすい傾向があります。

iDeCoの掛金はいくら?5000円は意味ない?上限額や毎月の目安
資金の引き出し可否
NISAとiDeCoの資金の引き出し可否は、以下の表の通りです。
| NISA | いつでも引き出し可能 |
| iDeCo | 原則60歳まで引き出し不可 |
NISAでは、保有している金融商品をいつでも売却して現金化することが可能です。
運用途中での売却は長期的な利益を考えるとあまりおすすめできませんが、急にまとまった資金が必要になったときにすぐ現金化できる点はNISAのメリットといえるでしょう。
一方、iDeCoは原則として60歳になるまでお金を引き出すことができません。
iDeCoは老後のための年金制度として設けられているため、子どもの教育資金や住宅購入費用など、老後を迎える前に必要な資金にはNISAを活用しましょう。
税制優遇(節税)の範囲
NISAとiDeCoの税制優遇の範囲は、以下の表の通りです。
| NISA | ・売却益と配当金・分配金が非課税 |
| iDeCo | ・掛金が全額所得控除 ・運用益が非課税 ・受取時に「公的年金等控除」または「退職所得控除」が適用 |
NISAでは、金融商品の売却による利益や運用中に得られる配当・分配金が非課税となります。
一方iDeCoでは、運用で発生した利益が非課税で再投資されるだけでなく、掛金の拠出時と給付金の受け取り時にも税控除を受けられます。税制面でのメリットが大きいのは、NISAよりもiDeCoだといえるでしょう。
NISAとiDeCoはどっちがおすすめ?
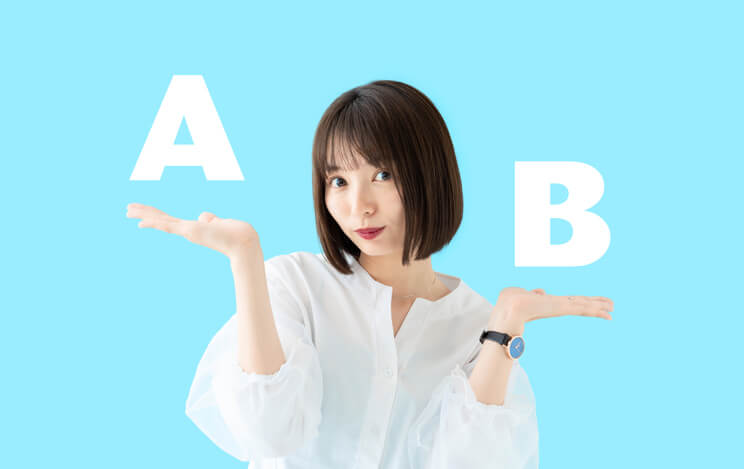
NISAとiDeCoを比較した際に最も大きな違いは資金拘束の有無です。
NISAで運用している資金はいつでも引き出し可能ですが、iDeCoで運用している資金は原則60歳まで引き出しできません。
つまり、NISAで運用している資金はマイホームの購入資金や子どもの教育費など使い道が自由ですが、iDeCoで運用する資金は60歳以降の老後資金にしか使えないということになります。
ここではNISA(成長投資枠・つみたて投資枠)とiDeCoのそれぞれおすすめなケースを解説します。
上記を踏まえてどの制度を利用するか検討してみてください。
NISA(成長投資枠)がおすすめな人
NISAの成長投資枠では、投資信託に加えて株式やREITなど幅広い金融商品に投資できるため、運用の自由度が高いことが特徴です。
さらに、一括での投資や国内外の金融商品への投資も可能で、さまざまな投資スタイルに対応しやすい制度となっています。
そのため「投資経験がある人」や「まとまった金額を投資に使える人」に適した投資枠だといえるでしょう。
投資経験がある人
NISAの成長投資枠では、株や投資信託、ETF、REITなど、さまざまな金融商品に投資できます。
つみたて投資枠やiDeCoと比べて投資の自由度が高く、すでに投資経験がある方に特におすすめの制度です。
また、株式の配当金にかかる税金も非課税になるため、高配当銘柄に投資して安定した配当金を受け取るのも選択肢のひとつになります。
成長性が高い銘柄に投資して、運用益を非課税で受け取るのも良いでしょう。
すでに投資をしている方はこれまでの投資戦略を活かしながら、NISAの成長投資枠で非課税のメリットを最大限に活用しましょう。
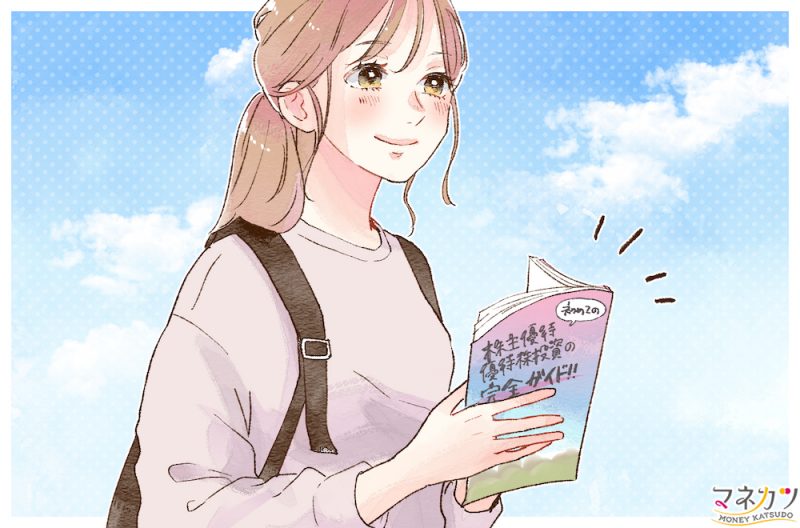
高配当株に投資するメリット・デメリット!銘柄選びのポイントも紹介
まとまった金額を一括投資したい人
NISAのつみたて投資枠やiDeCoでは、基本的に毎月の積立運用しかできません。
一括でまとまったお金を運用したい場合は、NISAの成長投資枠の利用がおすすめです。
すでに余剰資金がある場合や早めに非課税投資を始めたい方は、成長投資枠での一括投資を検討すると良いでしょう。
ただし、成長投資枠の年間非課税限度額は240万円までとなっているため、それを超えた部分の投資から生まれる利益については課税対象となる点に注意が必要です。

株式投資の始め方を初心者向けに解説!メリットや注意点も紹介
NISA(つみたて投資枠)がおすすめな人
NISAのつみたて投資枠は、金融庁が認可した「長期・積立・分散投資」に適した商品に投資できる非課税投資枠です。
毎月自動でコツコツと資産を積み立てることができるため、「投資初心者」「既に定期預金や先取り貯蓄をしている方」、そして「投資に時間をかけたくない、またはかけられない方」にはNISAのつみたて投資枠の活用が特におすすめです。
投資初心者の人
NISAのつみたて投資枠では最初に積み立てる銘柄と金額を設定すれば、その後は売却するまで特別な手間がかかりません。
投資のタイミングを気にする必要がなく、月初や給料日など決めた日程に自動で買い付けてくれるため、投資初心者の方でも始めやすいでしょう。
NISAのつみたて投資枠で投資できる商品は日経平均やアメリカ、世界の株価指数に連動したものなどが多く、長期的に見ればどれも右肩上がりに成長していくことが期待されます。
短期的な下落があっても、長い目で見れば上昇中の一時的な下落に過ぎないことも多いでしょう。
こうした理由から、銘柄の値動きを頻繁にチェックすることなく放置しながら運用できるため、投資初心者におすすめだといわれています。
投資経験が浅い方やこれから資産形成を計画している方は、NISAのつみたて投資枠を活用して長期投資を始めてみましょう。

株初心者はいくらから投資を始めるのがおすすめ?少額投資について解説
定期預金や先取り貯蓄を実施している人
すでに積立式の定期預金や先取り貯蓄を行っている方は、その資金の一部をNISAのつみたて投資枠に振り分けることも視野に入れてみましょう。
NISAでは、運用で得られるリターンが非課税となるため、ただ貯金をするよりも効率的に資産を増やせる可能性が高いです。
すでに貯金の習慣がある方は、負担を増やすことなくこの制度を活用できるでしょう。
NISAのつみたて投資枠は、いきなり満額運用する必要はありませんので、少額から無理なく資産形成を進めていくことが大切です。

先取り貯金おすすめのやり方!金額の目安や口座を分けて管理する理由
投資に時間を使いたくない人
投資に時間をかけたくない方や忙しい方には、NISAのつみたて投資枠の活用をおすすめします。
一度積立の設定をすれば、その後はほとんど手間がかからず、運用も自動で進められるためです。
投資信託は「トヨタ自動車」や「Apple」のような個別株に投資するわけではないため、企業の決算や業績を細かくチェックする必要がありません。
比較的値動きがゆるやかな商品が多いため、デイトレードのように日々の値動きを気にする必要がなく、月に1度程度、評価額をチェックするくらいであることが多いです。
日々忙しく投資に時間を割けない方や投資の手間を最小限に抑えたい方は、NISAのつみたて投資枠を活用してみましょう。

投資信託のメリット・デメリット!投資初心者にもわかりやすく解説
iDeCoがおすすめな人
iDeCoは税制面で多くの優遇を受けられるというメリットの一方、原則60歳まで資金を引き出せないというデメリットもある制度です。
そのため、明確に「老後のための資金を積み立てたい」「収入に余裕がある」「節税効果を利用したい」という方は、iDeCoの活用をおすすめします。
老後のための資金を積み立てたい人
iDeCoは、老後の資金を個人で積み立てるために設けられた私的年金制度です。
「公的年金だけでは不安」「今のうちから老後に向けた資産形成を始めたい」と考えている方には、iDeCoの活用をおすすめします。
近年では「老後2,000万円問題」が話題になっていますが、iDeCoの積立を活用していれば多くの場合で老後の生活費に対する不安を解消できるでしょう。
時間をかけて運用すればするほど高いリターンが期待できるため、可能な限り早くから取り掛かるのがおすすめです。
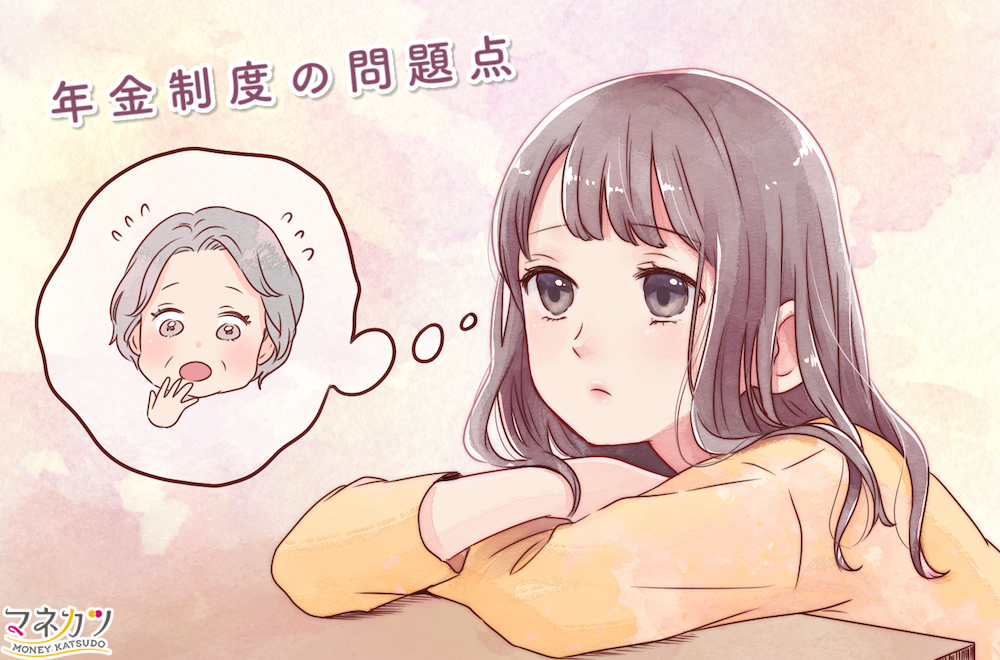
【2025】年金問題の現状や解決策は?老後2,000万円問題に備えよう
収入に余裕がある人
iDeCoは、NISAとは違って拠出した資金を原則60歳まで引き出せないというデメリットがあります。
なにかの理由で急に資金が必要となった場合、お金が足りなくなってしまうケースも考えられるため、収入や貯蓄の状況に余裕がある人が活用すべき制度と言えるでしょう。
もちろん老後のための資金と割り切れれば、収入の多い少ないは関係ありません。
しかし、人生は何が起こるか分からず、iDeCoの積立資金がロックされていることで困る場面が訪れる可能性もあるでしょう。
iDeCoは、「原則60歳まで資金が引き出せない」というデメリットを許容できる方、収入に余裕がある方におすすめできる制度です。
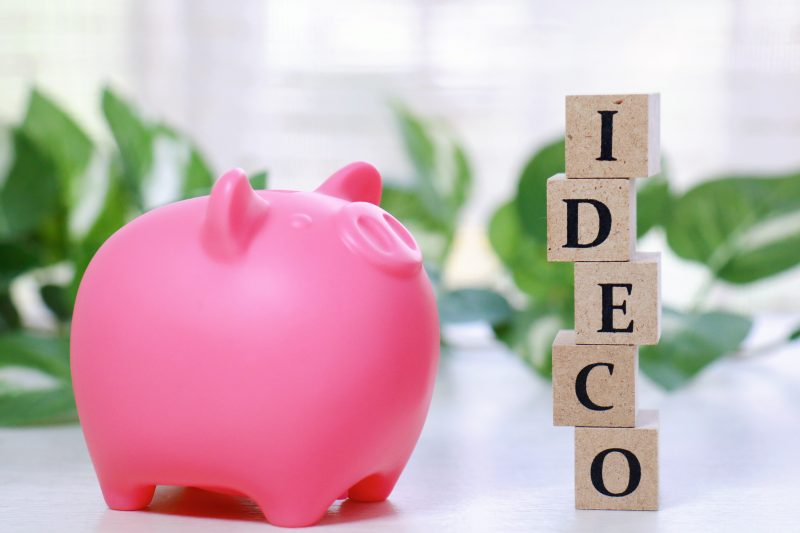
iDeCo(イデコ)にはデメリットしかない?お得に投資する方法
節税効果を活かしたい人
iDeCoは運用益を非課税で再投資できるだけでなく、掛金の拠出や給付金の受け取り時にも控除が適用されるというメリットがあります。
節税効果を活用して税金の負担を軽減したい人には特におすすめです。
例えば、会社員の方が毎月23,000円(年間276,000円)を拠出した場合、翌年の住民税は27,600円ほど軽減されます。
個人の収入によって異なりますが、所得税も掛金に応じて軽減されるため、NISAよりも高い節税効果が期待できます。
さらに、運用している商品の成績に関係なく掛金の金額に応じて毎年一定額が控除される点は非常に大きなメリットです。
税制面でのメリットを最大限に活用したい方は、iDeCoの活用を検討しましょう。

サラリーマンができる税金対策一覧!24選の税金対策を紹介
NISAとiDeCoは併用できる

NISAとiDeCoは、併用可能な制度です。
そのため、老後に向けた資金は「iDeCo」、それ以外の資金運用は「NISA」を活用して運用することが効果的です。
さらに、NISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」が併用できるため、資金の用途や運用ニーズによって使い分けることをおすすめします。
すでに投資経験があり、まとまった資金を投資できる方は成長投資枠を、投資初心者で少額から積立投資を始めたい方はつみたて投資枠の活用がおすすめです。
各制度の特徴を理解した上で、節税効果を得ながら資産形成を進めていきましょう。
NISAとiDeCoで同じ銘柄を選べる
NISAとiDeCoでは、同じ銘柄に投資することも可能です。
ただし、特定の金融資産に集中して投資を行うと、ポートフォリオ内の資産配分が偏ってしまう可能性があります。
リスク分散という観点では、値動きの異なる複数の資産に分散して投資をするのがおすすめです。
投資する銘柄数を多くしたくない方は、バランスファンドのように、1つの銘柄を購入するだけで複数の資産や銘柄に幅広く投資を行える商品を選ぶのも良いでしょう。
NISAとiDeCoは同じ口座にはならない
NISAとiDeCoを併用する際、必ずしも同じ証券会社で運用する必要はありません。
NISAは証券資産、iDeCoは年金資産として異なる口座で管理することになるため、同じ金融期間で口座を開設しても、異なる金融期間で口座を開設することも可能です。
中には楽天証券のように、NISAとiDeCoを同一のアカウントで管理できる金融機関もあります。
なるべく一括で資産を管理したい方は、このような金融機関で管理・運用することが便利です。
NISAやiDeCoの次の投資

これから資産形成を始める方は、制度を活用しながら少しずつ余裕資金を次のステップに進めていくことが大切です。
ここでは、NISAやiDeCoを含む投資のおすすめ順について解説します。
NISAの拠出上限額を目指す
これから資産形成を始める方には、まずはNISAの「つみたて投資枠」の活用をおすすめします。
つみたて投資枠は資金の引き出しに制限がなく、いざお金が必要になったときにいつでも現金化できるためです。
運用開始時に投資金額や積立頻度を設定すれば、あとは自動で投資が行われるため、仕事や育児で忙しい方でも手軽に運用を続けられます。
最初からNISAの非課税枠をすべて使い切る必要はなく、少額からでも投資を始めることが重要です。
資金に余裕が出てきたら、つみたて投資枠の非課税枠を最大限活用できるようよう投資額を増やしていきましょう。
iDeCoも併用して上限金額を目指す
NISAのつみたて投資枠の非課税枠を満額使い切ったら、次はiDeCoの利用を検討しましょう。
iDeCoは原則60歳まで引き出せない制約がありますが、掛金が全額所得控除の対象になるため税制優遇のメリットは大きいです。
職種や会社によってiDeCoの拠出上限額は異なりますが、まずは無理のない範囲から毎月の拠出金額を増やしていきましょう。
たとえば、会社員の方がNISAのつみたて投資枠(年間120万円、毎月100,000万円)とiDeCo(年間276,000円、毎月23,000円)を満額積み立てた場合、毎月の積立額は123,000円となります。
この金額を毎月積み立てていくのは難しいかもしれませんが、可能な範囲でiDeCoを利用すると資産形成のスピードが上がるでしょう。
また、iDeCoの税制メリットを享受したいという方は、NISAの非課税枠を満額使わずにiDeCoにお金を回すのも一つの選択肢です。

iDeCoの掛金はいくら?5000円は意味ない?上限額や毎月の目安
少額から個別株に投資
ある程度投資に慣れてきたら、NISAの「成長投資枠」を活用し、つみたて投資枠やiDeCoではカバーできない個別株を買ってみるのも一つの方法です。
日本株だけでなく、近年は米国株も多くの投資家からの注目を集めています。
さまざまな銘柄を比較検討し、自分にあった投資先を見つけることをおすすめします。
ただし、個別株の場合は投資信託のように一度購入して長期間放置するのではなく、定期的な企業の業績や株価の業績や株価の確認が重要です。
個別株は市場の動向や企業のパフォーマンスに左右されやすいため、リスクを把握した上で慎重に投資判断を行いましょう。
投資を開始する前には、企業の財務状況や成長性などをしっかりと分析し、リスクに見合った投資を心がけることが大切です。
株以外の投資も検討
余裕資金がある方や、より幅広い商品への分散投資を目指したい方には、不動産やコモディティ、FXなど他の投資を検討するのもおすすめです。
複数の不動産に分散投資できるREIT(不動産投資信託)や、コモディティの価格に連動する投資信託であれば、NISAを通じて投資ができます。
しかし、これらの金融商品は値動きの予測が難しいケースも多いため注意が必要です。
不動産市場やコモディティの価格動向は、政治的・経済的な要因に大きく左右されることもあります。
また、FXなど為替市場も変動が激しく、短期間での大幅な価格変動リスクが伴います。
これらの投資を始める際には、リスクを十分に理解し、自分の許容範囲内で運用を行うことが重要です。
分散投資の一環として、慎重に計画を立てながら取り組んでいくと良いでしょう。

REIT(リート)とは?J-REITとの違いやメリットとリスクを解説
NISAやiDeCoにおすすめの証券会社

NISAやiDeCoを始めるためには証券会社や銀行などの金融機関を利用する必要があります。
しかし、NISAやiDeCoを利用するための口座は1人1口座しか開設できません。
複数の金融機関で口座開設できない点から、どこで開設するかが大切になります。
NISAやiDeCoを運用する金融機関は途中で変更することができますが、手続きや審査等があり、すぐに変更できるわけではありません。
購入できる金融商品に差がある場合もあるため、証券会社を選ぶ前からどの銘柄に投資するかを事前に調べておくのがおすすめです。
ここでは特に人気の2つの証券会社をご紹介します。

【2025】楽天証券とSBI証券はどっちがおすすめ?使い分けのコツ
SBI証券

SBI証券は2024年時点で最大手のネット証券です。
その主な特徴として、取引手数料の安さやIPO(新規上場株式)の取扱件数が多い点などがあげられます。
また、Tポイントを利用した投資や三井住友カードによる投資信託の購入も可能です。
SBI証券でのつみたて投資枠およびiDeCoの取り扱い銘柄数は下記のとおりです。
- NISA(つみたて投資枠):247本
- iDeCo:83本
※2024年9月時点
SBI証券は、iDeCoに対応した投資信託が豊富な点と、NISAのつみたて投資枠に対応している商品も多い点がおすすめです。
iDeCoの元本確保型商品も4本あるため、安全性を重視した投資も選択しやすいです。
このように、NISAやiDeCoを利用する際に、自身のリスク許容度や投資目的に合った商品を選びやすいというメリットがあります。
NISAの成長投資枠を利用する方にとっても、NISA口座での国内株・米国株・海外ETFの売買手数料が無料な点や外国株式の取扱数が多い点でおすすめです。
出典:株式会社SBI証券「投資信託パワーサーチ」
出典:株式会社SBI証券「投資信託(元本変動型)」
楽天証券

楽天証券はSBI証券に匹敵する口座開設数を持つ、大手のネット証券です。
大きな特徴は、楽天ポイントを使った投資ができる点です。
楽天カードで投資信託を購入すると、購入額の1%が楽天ポイントで還元されます。NISAのつみたて投資枠で運用する投資信託も楽天カードで購入でき、楽天ポイントが貯まります。
普段から楽天経済圏を利用している方には、楽天証券での投資がおすすめです。楽天証券でのつみたて投資枠およびiDeCoの取り扱い銘柄数は下記のとおりです。
- NISA(つみたて投資枠):238本
- iDeCo:35本
※2024年9月時点
iDeCoは投資信託に加えて、元本確保型商品が1本あります。
NISAのつみたて投資枠に対応している投資信託は合計238本と、幅広い商品の中から自分にあったものを選べるという点がメリットです。
NISA口座の取引では、国内株式・米国株式・海外ETF・投資信託の取引手数料が無料となっているため、成長投資枠を利用する方にもおすすめできます。
出典:楽天証券株式会社「投信スーパーサーチ」
出典:楽天証券株式会社「取扱商品一覧」
出典:楽天証券株式会社「楽天証券のNISAは国内株式も米国株式も、海外ETFも投資信託も取引手数料無料(2024年開始の新NISAから適用)」
まとめ:NISA・iDeCoどちらも違いを理解した上で活用しよう

NISAとiDeCoは、どちらも税制優遇を活用して資産形成ができる制度です。
それぞれに特徴があるため、自身の投資目的に合わせた制度を選びましょう。
資金の引き出しやすさという点では、iDeCoのハードルはやや高いため、気軽に始めてみたい場合はNISAのつみたて投資枠から検討するのがおすすめです。
NISAのつみたて投資枠と成長投資枠およびiDeCoは併用できます。
資金に余裕がある方は、NISAとiDeCoで満額投資することを目標に資産形成を進めていきましょう。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎








