年金は60歳からもらった方が賢い?いつからもらうのがお得なのか解説

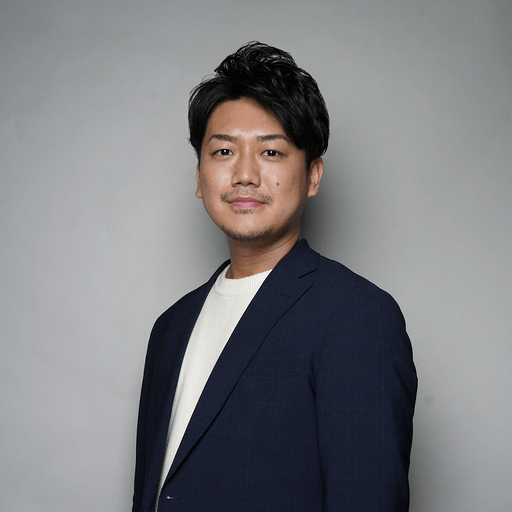
「年金は60歳からもらったほうが賢い」という意見を聞いたことがある方もいるかもしれません。
通常、年金は65歳から受給するのが基本ですが、60歳からの受給も可能です。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、自身に最適な受給開始年齢を理解しておくことが重要です。
この記事では、年金の基本的な受給開始時期や、60歳からもらう場合のメリット・デメリット、また繰り上げ受給時の注意点を詳しく解説します。
老後資金の計画作りにお役立てください。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎
この記事の目次
老後にもらえる公的年金は国民年金・厚生年金の2種類

老後にもらえる公的年金は大きく分けて以下の2種類です。
- 国民年金
- 厚生年金
それぞれの特徴について解説していきます。
国民年金
国民年金は、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の人が加入する公的年金制度です。
20歳から60歳まで保険料を納付し、原則として65歳から年金を受給するという仕組みになっています。
国民年金の加入者は第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者の3つに分類されます。
それぞれの加入対象者は以下の表の通りです。
| 分類 | 対象者 |
| 第1号被保険者 | 農業者や自営業者、学生など、第2号・第3号被保険者以外の人 |
| 第2号被保険者 | 会社員や公務員など、厚生年金保険に加入している人 |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
自分がどの分類に該当するのかを確認しておきましょう。
厚生年金
厚生年金は、会社員や公務員などの国民年金保険の第2号被保険者が加入する公的年金制度です。
国民年金に上乗せされる2階部分として受給できることが厚生年金の特徴です。
厚生年金の保険料は給与や賞与に保険料率をかけて算出されており、事業主と従業員本人で折半して納付します。
加入者は原則として65歳から国民年金と併せて年金を受給する仕組みです。この制度により、老後の生活保障が手厚くなります。
国民年金の受取開始は原則65歳から
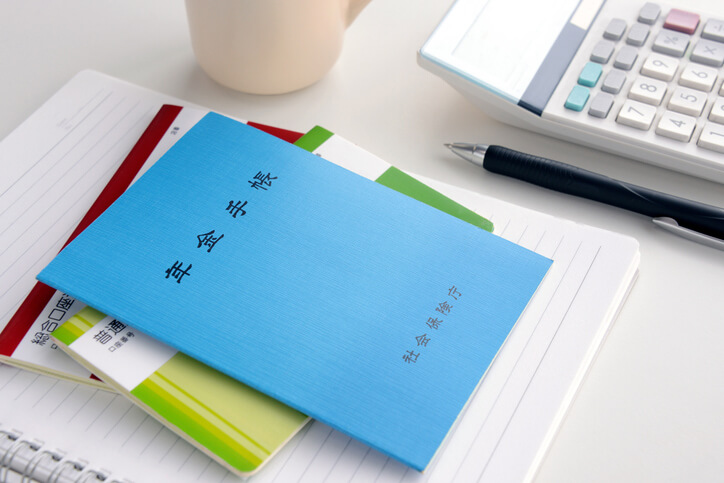
国民年金や厚生年金は、原則として65歳から受給開始となり、支払った保険料額に応じて受給額が決まります。
しかし、受給開始年齢を調整できる「繰り上げ受給」や「繰り下げ受給」も選択可能です。
繰り上げ受給では60歳から年金を受け取れる一方、受給額が減額されるなどの注意点があります。
どの受給方法が自分にとって適しているかを理解するため、繰り上げ受給の特徴やメリット・デメリットを比較検討することが重要です。
年金は早くもらう方がお得なの?

繰り上げ受給を活用すると、65歳より前に年金を受け取ることが可能です。
しかし「年金を早く受け取るべきか悩む」「65歳よりも前に受け取るとどうなるのか分からない」というケースも少なくなりません。
ここでは、年金の繰り上げ受給と繰り下げ受給について解説します。
それぞれの特徴を踏まえ、年金の受給開始年齢を考えてみましょう。
年金の繰り上げ受給
国民年金・厚生年金は原則65歳から受給を開始しますが、希望すれば60歳から65歳までの間で繰り上げて受け取ることができます。
ただし繰り上げ受給を選択すると、繰り上げる期間に応じて年金額が減額されるため注意が必要です。
昭和37(1962年)年4月1日以前に生まれた方の場合、繰り上げ期間ひと月あたりの減額率は0.5%でした。
60歳から受給する場合は5年間(60ヶ月)繰り上げることになるため、減額率は「0.5% × 60ヶ月 = 30.0%」となります。
昭和37年(1962年)4月2日以降に生まれた方の場合、繰り上げ期間ひと月あたりの減額率は0.4%です。
60歳から受給する場合の減額率は「0.4% × 60ヶ月 = 24.0%」となります。
減額率が引き下げられたことで繰り上げ受給を選択しやすくなっていますが、減額後の年金額を十分に検討し、自分の生活に合った選択をすることが大切です。
年金の繰り下げ受給
国民年金・厚生年金は、65歳からの受給開始だけでなく、66歳から75歳までの間に繰り下げて受給することもできます。
繰り下げる期間に応じて年金額が増額され、その増額された年金を一生涯にわたって受け取れます。
繰り下げた場合の増額率は、ひと月あたり0.7%です。
最長の75歳まで繰り下げた場合、繰り下げ期間は10年(120ヶ月)となり、増額率は「0.7% × 120ヶ月 = 84.0%」となります。
増額後の年金額は魅力的ですが、受給期間が短くなる点も考慮する必要があります。
自分の健康状態やライフプランを見直し、増額率と受給期間のバランスを踏まえて最適な受給開始時期を決定しましょう。
年金を60歳からもらうメリット

繰り上げ受給を活用して60歳から年金をもらうメリットとして、主に以下の2点が挙げられます。
- 65歳より前から年金を受け取れる
- 元気なうちに年金を受給して趣味や娯楽に使える
それぞれのメリットについて解説していきます。
65歳より前から年金を受け取れる
年金を繰り上げ受給することで、65歳より早く受け取れるため、安定した収入が確保できるのが大きなメリットです。
収入がない期間が発生しがちな早期退職後も、毎月の収入が得られることで精神面の安心感を得られます。
たとえば、60歳前後で早期退職した場合、本来の受給開始年齢である65歳までは収入が途絶える可能性がありますが、繰り上げ受給により収入源を早めに確保できます。
これにより、貯蓄を減らさず生活費を賄うことが可能です。
早めに年金を受給し、老後の生活を安定させられる点が、60歳からの受給の大きなメリットと言えるでしょう。
元気なうちに年金を受給して趣味や娯楽に使える
健康面で不安がある人にとって、元気なうちに年金を受給することは一つの選択肢となります。
持病や体力低下への懸念から、体力のある60代前半のうちに年金を受け取り、趣味や好きなことにお金を使うという考え方があります。
繰り上げ受給では年金額が減額されますが、「体力が無くなってからではお金を使う意味が薄れる」といった意見も見られます。
将来の健康状態に不安がある場合には、減額を受け入れてでも早い時期に年金を受け取ることを検討すると良いでしょう。
年金を60歳からもらうデメリット
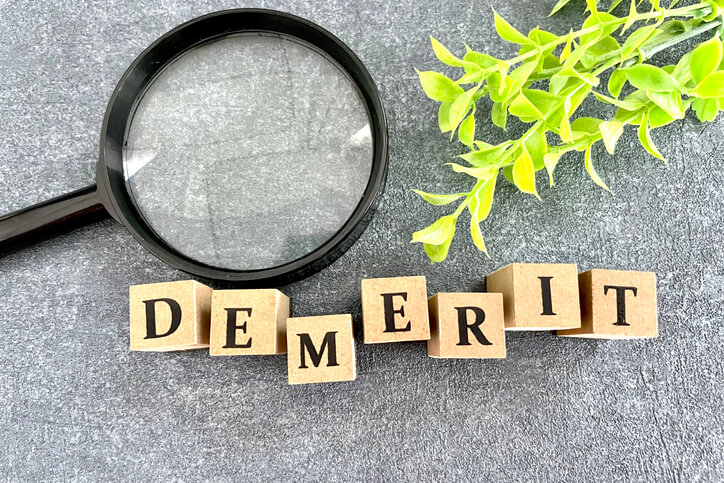
繰り上げ受給を活用して年金を60歳から受給するデメリットとして、主に以下の4点が挙げられます。
- 毎月の年金額が減る
- 一度繰上げ受給の手続きをすると、あとから受給時期を変更できない
- 国民年金と厚生年金の両方が同時に繰上げとなる
- 障害基礎年金や遺族厚生年金を受給できない可能性がある
それぞれのデメリットについて解説します。
毎月の年金額が減る
繰り返しとなりますが、繰り上げ受給を選択すると、毎月受給できる年金額が減額されます。
減額された年金額は一生涯変わらないため、長生きした場合、受給総額で本来の65歳から受給を始めた場合との差が大きくなる可能性があります。
繰り上げ受給の選択前には、「減額後の年金額がいくらになるのか」「その金額で生活を維持できるのか」といった点をシミュレーションし、生活設計を慎重に立てることが重要です。
これにより、減額後の収入でも無理のない生活が送れるかを見極められます。
一度繰上げ受給の手続きをすると、あとから受給時期を変更できない
一度繰り上げ受給を申請すると、受給開始時期を変更することはできません。
たとえ繰り上げ受給の必要がなくなったとしても、減額された年金額が生涯にわたって支給され続ける点に注意が必要です。
例えば、60歳以降に新たな仕事で収入を得るようになった場合、本来の受給開始年齢まで待ったほうが総額で有利になることも考えられます。
それでも一度申請した繰り上げ受給は取り消せないため、減額分を取り戻すことはできません。
繰り上げ受給を検討する際は、将来の収入やライフプランを慎重に見通し、十分な判断のもと選択することが重要です。
国民年金と厚生年金の両方が同時に繰上げとなる
国民年金と厚生年金は、両方同時に繰り上げを行う必要があります。一方のみを繰り上げることはできないため、この点には注意が必要です。
例えば「60歳以降も働いて厚生年金に加入し続けるが、国民年金だけを繰り上げて受け取りたい」という選択はできません。
繰り上げを請求すると、国民年金と厚生年金の両方が同じタイミングで繰り上げられます。
繰り上げ受給を検討する際は、この条件を理解した上で、将来の生活設計に与える影響をしっかりと考慮することが重要です。
障害基礎年金や遺族厚生年金を受給できないケースがある
「年金」と聞いて多くの人がイメージするのは老後の「老齢年金」ですが、公的年金制度には「障害年金」や「遺族年金」も含まれます。
繰り上げ受給を選択すると、これらの年金に影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。
障害年金は、ケガや病気により生活や仕事に制限が生じた場合に給付されます。
しかし、老齢基礎年金を繰り上げ受給している場合、60歳から65歳までの間に障害基礎年金の給付対象となっても受給できません。
また、遺族年金は年金加入者が死亡した際に遺族が受給するものです。
遺族厚生年金は老齢基礎年金と同時に受給できないため、繰り上げ受給後に死亡した場合、65歳までは遺族厚生年金を受け取れなくなります。
障害年金や遺族年金に影響が生じる点を理解し、将来の生活や家族の状況を考慮して繰り上げ受給を検討することが重要です。
繰り上げ受給をする際の注意点

年金の繰り上げ受給をする場合、以下の点に注意しておきましょう。
- 一生減額された年金を受け取ることになる
- 寡婦年金を受給している場合、老齢基礎年金の繰り上げによって寡婦年金を受給する権利を失う
- 国民年金の任意加入被保険者になれない
- 65歳より前に遺族年金の受給権が発生した場合に老齢基礎年金・遺族年金のどちらを受給するか選ばなければならない
繰り上げ受給を選択すると、一生涯にわたって減額された年金を受け取ることになり、途中で取り消すことはできません。
また、65歳より前に遺族年金の受給権が発生した場合、老齢基礎年金と遺族年金のどちらを受給するか選択しなければならない点にも注意が必要です。
さらに、寡婦年金の受給権がある場合でも、老齢基礎年金を繰り上げるとその権利を失ってしまうため、慎重に判断することが求められます。
また、繰り上げ受給を選択すると、国民年金の任意加入制度を利用することができなくなり、追加の保険料を納付して将来の年金額を増やす選択肢が失われます。
これらの点を十分に理解した上で、家計や将来の収入見込みを踏まえ、年金を繰り上げて受給するべきかどうかを慎重に検討しましょう。
まとめ:年金をいつからもらうべきか考えておきましょう

原則65歳から受給する国民年金・厚生年金ですが、希望すれば60歳から繰り上げ受給が可能です。
早い時期から安定した収入を得られることや、元気なうちに年金を活用できるといったメリットがあります。
一方で年金額が減額されたり、障害基礎年金や遺族厚生年金を受給できなくなる可能性があるといったデメリットもあります。
繰り上げ受給のメリットとデメリットを十分に理解し、老後の資産設計やライフプランを考慮した上で、最適な年金の受給開始時期を慎重に選びましょう。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎








