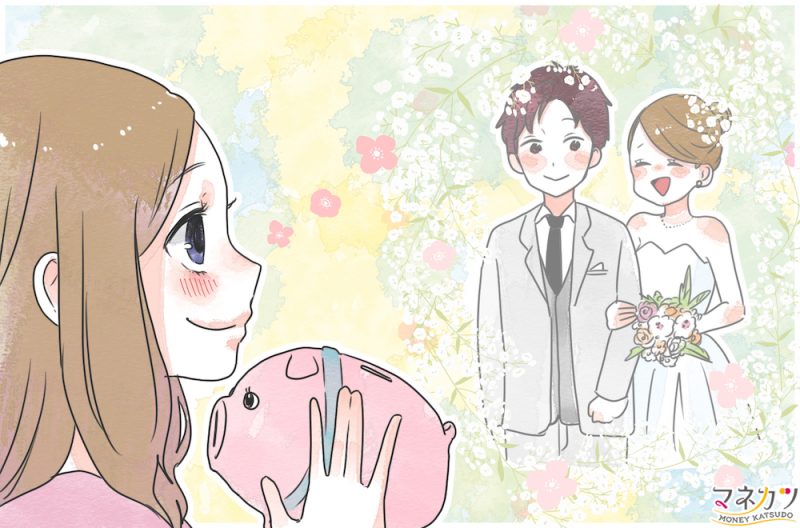貯金500万円は多い?500万円貯めるためのコツとおすすめの資産形成方法をご紹介


記事監修者
山口 祐平
宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー、証券外務員の資格を持つ専門家。
証券や投資用不動産の販売において、卓越した商品分析力を発揮し、幅広い商品知識を駆使して顧客に最適な投資プランを提案している。
商品特性の深い理解に基づき、複雑な金融商品や不動産投資に関するニーズに対応し、信頼性の高いコンサルティングを提供。
これまで培ってきた知識と経験をもとに、顧客の資産形成に寄与している。

記事監修者
山口 祐平
宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー、証券外務員の資格を持つ専門家。
証券や投資用不動産の販売において、卓越した商品分析力を発揮し、幅広い商品知識を駆使して顧客に最適な投資プランを提案している。
商品特性の深い理解に基づき、複雑な金融商品や不動産投資に関するニーズに対応し、信頼性の高いコンサルティングを提供。
これまで培ってきた知識と経験をもとに、顧客の資産形成に寄与している。
「貯金500万円は一般的に多いのか」と疑問を感じる方も多いかもしれません。
同世代や同じ収入水準の人と比べて貯金の額がどの程度なのかを知ることで、資産形成のモチベーションを高めることができます。
この記事では、年代別や年収別に貯金500万円を保有している人の割合を解説し、貯金500万円で実現できること、さらにお金を貯める具体的な方法について紹介します。
また、おすすめの資産形成方法も取り上げているため、効率よく貯蓄を増やしたい方はぜひ参考にしてください。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎
貯金500万円は多い?年代・世帯別の割合

まず、年代別や年収別の貯金500万円の割合について解説します。
あわせて、2人以上世帯の貯金500万円保有者の割合も紹介するので、自身の状況と照らし合わせながら参考にしてみましょう。
【年代別】貯金500万円の割合
金融広報中央委員会の「(参考)家計の金融行動に関する世論調査[総世帯](令和5年)」によると、各年代の金融資産保有額は以下の表の結果となっています。
| 年代 | 金融資産500万円未満 | 金融資産500〜700万円 | 金融資産700万円以上 |
| 20代 | 89.5% | 4.0% | 4.4% |
| 30代 | 69.5% | 6.3% | 20.2% |
| 40代 | 61.5% | 6.8% | 27.5% |
| 50代 | 57.1% | 5.3% | 33.3% |
| 60代 | 45.1% | 6.2% | 45.5% |
| 70代 | 43.2% | 6.3% | 48.0% |
20代・30代では貯金500万円以上の世帯が比較的少ないのに対し、年代が上がるにつれてその割合は増加しています。
特に60代・70代になると、貯金500万円以上の世帯が貯金500万円未満の世帯を上回るという結果が出ています。
こうしたデータより、貯金500万円は若い年代にとってはやや高めの目標である一方、年齢を重ねるにつれてより一般的な水準になると考えられるでしょう。
出典:知るぽると 金融広報中央委員会「(参考)家計の金融行動に関する世論調査[総世帯]令和5年調査結果」
【年収別】貯金500万円の割合
年収別の金融資産保有額を以下の表にまとめました。
| 年収 | 金融資産500万円未満 | 金融資産500〜700万円 | 金融資産700万円以上 |
| 収入はない | 80.5% | 0.7% | 6.9% |
| 300万円未満 | 71.3% | 5.2% | 21.3% |
| 300〜500万円未満 | 58.0% | 5.9% | 32.7% |
| 500〜750万円未満 | 49.2% | 8.8% | 39.2% |
| 750〜1,000万円未満 | 36.0% | 7.0% | 52.7% |
| 1,000〜1,200万円未満 | 29.3% | 4.6% | 64.2% |
| 1,200万円以上 | 27.3% | 3.3% | 66.4% |
年収が高くなるほど貯金500万円以上の割合が増加する傾向にあります。
特に年収750万円以上の層では、半数以上の人が貯金500万円以上を保有していることが特徴的です。
この結果は、収入が増えることで貯蓄に回せる余裕が生まれやすい点を反映しているといえます。
このようなデータを参考に、自分に合った貯蓄目標を設定し、モチベーションを高めていくとよいでしょう。
また、収入だけに依存せず、節約や資産運用を取り入れた戦略的な貯蓄が効果的です。
出典:知るぽると 金融広報中央委員会「(参考)家計の金融行動に関する世論調査[総世帯]令和5年調査結果」
【2人以上世帯】貯金500万円の割合
金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和5年)」によると、2人以上世帯の金融資産保有額は以下のような結果となっています。
| 金融資産保有額 | 割合 |
| 金融資産非保有 | 24.7% |
| 100万円未満 | 8.6% |
| 100〜200万円未満 | 6.8% |
| 200〜300万円未満 | 4.9% |
| 300〜400万円未満 | 4.5% |
| 400〜500万円未満 | 3.2% |
| 500〜700万円未満 | 6.5% |
| 700〜1,000万円未満 | 5.7% |
| 1,000〜1,500万円未満 | 7.9% |
| 1,500〜2,000万円未満 | 4.4% |
| 2,000〜3,000万円未満 | 6.2% |
| 3,000万円以上 | 12.7% |
| 無回答 | 3.9% |
調査によると、約40%の世帯が貯金500万円以上の金融資産を保有していることが分かりました。
一方で、保有資産額には世帯収入やライフステージ、生活スタイルなどに応じて幅広いばらつきがある点も考慮する必要があります。
さらに貯蓄や資産形成を進めるためには、収入アップ、節約、資産運用といった取り組みを組み合わせて効率的に目標を達成することが重要です。
出典:知るぽると 金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査]令和5年調査結果」
貯金500万円でできること

貯金500万円が手元にある場合、どのようなことが実現できるのでしょうか。
貯金のモチベーションを高めるためにも、貯金500万円でできることを把握しておきましょう。
一人暮らしの平均生活費17万円では約2年5ヶ月暮らせる
総務省の「家計調査報告(家計収支編)」によると、単身世帯における2023年の平均消費支出は167,620円でした。
貯金500万円で平均的な生活費17万円を支払うと仮定した場合、単純計算で約29ヶ月(2年5ヶ月)は暮らしていけます。
たとえば、病気やケガで働けなくなったり、転職活動で一時的に収入が減少したりするような状況でも、貯金500万円があれば生活を維持しやすくなります。
貯金500万円は万が一の事態に備えられるだけの金額といえるでしょう。
参考:総務省統計局「家計調査報告(家計収支編) 2023年(令和5年)平均結果の概要」
住宅購入の頭金や自動車購入、海外旅行などの大型出費に対応できる
貯金500万円は、住宅購入時の頭金や自動車の購入資金、海外旅行の費用など、まとまった支出にも対応できます。
ほかにも結婚式や子どもの進学費用などのライフイベントでも、この資金があれば柔軟な対応が可能です。
貯金500万円は日々の暮らしだけでなく、将来設計にも役立つ重要な財産であるといえるでしょう。
資産運用ができる
資産運用は価格変動による損失リスクがあるため、生活費を除いた余剰資金で行うのが基本とされています。
貯金500万円があれば、仮に短期的に損失を抱えても日常生活に大きな影響を与える可能性が低いため、精神的にも余裕を持ちながら運用を続けられるでしょう。
現在の日本では長期間にわたり低金利が続いており、銀行預金だけでは資産を大きく増やすことは期待できません。
余剰資金を活用して株式、投資信託、不動産などに分散投資し、将来に向けて堅実に資産形成を行うこともおすすめです。
適切なリスク管理を行いつつ、長期的な視点で計画的に運用を進めていくのが成功の鍵となるでしょう。
貯金500万円を貯める方法

次に、貯金額を増やしていくための方法を紹介します。
「貯金500万円を目指したい」と考えている方は、以下の方法を参考にしてください。
お金を貯める目的の明確化
お金を貯めるには、まずその目的を明確にすることが重要です。
明確な目標がないまま貯金を始めても、計画を立てにくく、モチベーションを維持するのが難しくなる可能性があるためです。
一般的なお金を貯める目的には以下のようなものがあります。
- マイホーム購入の頭金を貯めたい
- 子どもの教育資金を貯めたい
- 老後資金を準備したい
- 海外旅行に行きたい
- 独立するためにお金を貯めたい
それぞれの目標によって必要な金額や貯めるスケジュールが異なります。
目標が決まったら、「5年以内に500万円を貯める」といったように、その達成期限と必要金額を設定しましょう。
何のためにお金を貯めるのかを考え、現実的なゴールを設定することが、貯金を成功させるための第一歩となります。
家計の収支を把握
お金を効率よく貯めていくためには、まず現状の家計を正確に把握することが不可欠です。
家計簿をつけたり、家計簿アプリを利用したりして、収入と支出のバランスを確認し、どの部分に無駄があるのかを理解しましょう。
特にお金が貯まりにくいと感じている人は、家計の問題点を見過ごしている可能性があります。
例えば、無意識のうちに不要な固定費を支払っていたり、趣味や交際費で予算を超える支出をしていたりすることが考えられます。
近年は家計簿アプリが普及しており、銀行口座やクレジットカードと連携するだけで入出金を自動的に記録してくれるものもあります。
アプリを活用すれば、効率よく家計の状況を把握でき、支出内容をカテゴリーごとに確認することも可能です。
現状を正しく把握することで、節約可能な部分や見直すべきポイントが明確になり、計画的な貯金が進められるようになるでしょう。
固定費の削減

家計の収支を把握したら、次に固定費の見直しを行いましょう。
毎月決まって発生する固定費を削減できれば、長期的に家計を改善し、貯金額を増やすことが可能になります。
例えば、電気料金や通信費のプランを割安なものに乗り換えることで、毎月数千円単位の節約が期待できます。
また、家賃が安い物件への引っ越しも効果的な手段のひとつです。
さらに、生命保険に加入している場合は、必要以上の保障が付いていないか確認し、不要な保障を外せば保険料の負担を軽減できます。
保険の見直しを進める際は、プロのファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのもおすすめです。
自分のライフプランに合わせた最適な保険プランを提案してもらえるため、無駄な支出を削減しやすくなります。
固定費の見直しを行い、毎月の支出を効率的に抑えることで、より計画的な貯金が可能となります。
固定費の削減は一度実行するだけで継続的な効果が得られるため、優先的に取り組むべきだといえるでしょう。
先取り貯金をする
貯金を行う際は「先取り貯金」を行うように心掛けましょう。
先取り貯金とは、給料などの収入が入った時点で一定額を最初に貯金用口座に移し、残りの金額で生活する方法です。
この方法を実践すれば、収入が入るたびに使える金額が自動的に制限されるため、自然と無駄遣いを防げます。
一方で、使った後に余ったお金を貯金しようとする方法だと、つい出費が膨らみ、結果的に貯金が進まないケースも少なくありません。
効率的に先取り貯金を実現するには、銀行の自動振り込み機能を活用するのが便利です。
毎月の給料日直後に一定額を貯蓄専用口座に移す設定を行えば、特に意識しなくても自動で貯金が積み上がる仕組みを構築できます。
収入に見合った無理のない金額を設定し、この方法を継続することで、長期的な貯蓄目標に近づけるでしょう。
お金を貯めやすい時期を確認する

人生では、出費が多くお金が貯まりにくい時期と比較的お金を貯めやすい時期があります。
お金を貯めやすい時期を把握し、計画的に貯金を進めていきましょう。
一般的なお金を貯めやすい時期として以下のようなタイミングが挙げられます。
- 結婚前の独身時代
- 結婚から子どもが生まれるまでの期間
- 子どもが独立した後から定年までの期間
比較的収支に余裕があるタイミングを見計らい、計画的に貯蓄を進めることで、将来に備えた資産形成が可能になるでしょう。
ライフプランニング
ライフプランニングを行うことは、貯金を効率よく進めるために重要です。
ライフプランニングとは、これからの人生におけるライフイベントや目標を見据え、そのための具体的な資金計画を立てることを指します。
例えば、結婚や子どもの誕生・進学、住宅の購入、老後の生活など、今後必要となる大きな出費のタイミングを明確化できます。
それにより、どの時期にどれくらいの資金を確保すべきかが見えてくるため、現状の家計状況や貯金額を見直し、必要な改善点を把握しやすくなります。
専門家であるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談すれば、収支の分析や資金計画のアドバイスを受けながら、将来の夢や目標に向けた現実的なライフプランを作成できるでしょう。
目標に向けたステップが明確になることで、貯金のモチベーションを保ちながら計画的に資産を増やすことができます。
金利の高い銀行を選定
貯金を行う際は、金利の高い銀行を選ぶことが重要です。
金利は預けている間に積み重なるため、低金利の銀行を選ぶと、長期間では貯金額に大きな差が出る可能性があります。
一般的に、ネット銀行はメガバンクや地方銀行と比べて金利が高めに設定されていることが多く、効率的に資産を増やす選択肢といえます。
ただし、高い金利を適用するための条件が設けられているネット銀行もあるため、事前に詳細を確認し、自分の利用状況に適した銀行を選びましょう。
おすすめの資産形成方法

ここでは、貯金500万円を目指す際におすすめの資産形成の方法を紹介します。
自分に合った方法で資産を増やしていき、計画的に貯金していきましょう。
NISA
NISAは、投資で得た利益が非課税となる制度のことです。
最大で年間360万円・生涯で1,800万円まで投資可能となっており、効率的に資産形成を行えることが特徴です。
NISAには「つみたて投資枠」「成長投資枠」という2つの非課税投資枠がありますが、投資初心者の方にはつみたて投資枠をおすすめします。
つみたて投資枠は金融庁が厳選した商品のみが対象となっており、比較的低リスクでコストを抑えた投資を行えるためです。
NISAのつみたて投資枠を上手く活用し、堅実に資産を増やしていきましょう。
iDeCo
iDeCoは「個人型確定拠出年金」のことで、老後資金を自分で準備する私的年金制度です。
以下の3つの税制優遇を受けながら老後資金を準備できます。
- 掛金が全額所得控除になる
- 運用益が非課税で再投資される
- 年金・一時金の受け取り時にも控除が適用される
税金の負担を抑えながら老後に向けた資金準備を行えることがiDeCoの魅力です。
ただし、原則として60歳までは資金を引き出せないため、老後を迎える前の短期的な資金準備には向かない点に注意しておきましょう。
株式投資

株式投資は、企業が資金調達のために発行する「株式」を売買し、収益を得る方法です。
購入時よりも株価が上がったときに売却して利益を得たり、株式の保有期間中に企業から支払われる配当金を受け取ったりする形で収益を狙います。
株式は値動きが大きいため、短期的に大きなリターンを期待できる一方、損失のリスクも高い点に注意が必要です。
そのため、ある程度の投資経験があり、資産に余裕がある方に適した方法と言えるでしょう。投資を始める際には十分な情報収集を行い、分散投資でリスクを抑えることが重要です。
投資信託
投資信託は、投資家から集めた資金をもとに、専門家が運用を行う仕組みの金融商品です。
運用の成果が投資家に分配されるため、手間や時間をかけずに資産運用を行えます。
投資信託は、集めた資金を複数の株式や債券などに投資するため、1つの投資信託を購入するだけで間接的に多様な資産に分散投資することが可能です。
この分散効果によりリスクが抑えられ、比較的安定した値動きとなることから、投資初心者にも適した運用方法といえるでしょう。
債券投資
債券は、国や地方公共団体、企業が資金調達のために発行する有価証券です。
債券を購入すると、発行体から定期的に利子が支払われ、あらかじめ定められた満期を迎えると元本が返済されます。
株式に比べて値動きが小さく、安定した収益が期待できる点が債券投資の魅力です。
元本保証が比較的高い商品も多いため、リスクを抑えたい人や安定的なリターンを求める人に適した投資先といえるでしょう。
不動産投資

不動産投資は、土地や建物を購入して第三者に貸し出し、賃料収入を得る方法です。
将来的に値上がり益も期待できる点が魅力ですが、物件の購入には数百万円から数千万円の資金が必要で、ローンを組んで始めるのが一般的です。
現物不動産の購入が難しい場合、REIT(不動産投資信託)を利用する方法もあります。
プロが投資家から集めた資金で不動産運用を行う仕組みであり、数万円程度の少額から始められるため初心者にも適しています。
REITで不動産投資を始め、資金が貯まってローンを組む余裕が出てきたら現物不動産も視野に入れていくと良いでしょう。
財形貯蓄制度
勤務先の財形貯蓄制度を活用するのも効率的な貯蓄方法のひとつです。
給与天引きによって自動的に貯蓄が進む仕組みのため、計画的な貯金が難しい方に特に向いています。
財形貯蓄制度は目的に応じて「一般財形貯蓄」「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」の3種類が用意されており、それぞれ異なる用途に特化しています。
お金を貯める目的に応じて制度を利用し、計画的に貯蓄を行っていきましょう。
積立定期預金
積立定期預金は、毎月一定額を定期預金に積み立てることで、効率的に貯蓄を増やせる商品です。
普通預金より利率が高めに設定される定期預金の仕組みを活用し、計画的な貯金が可能となります。
自動的にお金を積み立てる仕組みが備わっており、自然に「先取り貯金」が行える点が大きな魅力です。
自分で毎月の貯蓄を管理するのが苦手な方でも、積立定期預金を利用することで、確実かつ継続的に貯金を行えます。貯金習慣をつけたい方におすすめの方法です。
積立保険
貯蓄性のある保険に積み立てる方法は、万が一の保障と将来に向けた貯蓄を同時に備えられるためおすすめです。
終身保険、個人年金保険、学資保険などが代表的な商品です。
積立保険は、計画的に貯蓄を行える一方で、途中で解約すると元本割れが生じる可能性があります。
そのため、事前に解約時の返戻率や運用状況をしっかり確認しておくことが大切です。
自分に合った保険商品を選びたい場合、FP(ファイナンシャルプランナー)などの専門家に相談して、ライフプランに基づいた最適な選択肢を提案してもらうのも効果的な手段です。
まとめ:貯金500万円を目指して計画的に資産を運用しましょう

貯金500万円は、年代や年収によりますが、比較的多い水準とされます。
この金額があれば、万が一の事態があっても一定期間生活が可能で、住宅の頭金や自動車購入といった大型出費にも対応できるため安心感があります。
この記事では、貯金500万円を達成するための具体的な方法や資産形成の手段を解説しました。
ぜひ自分に合った方法で資産形成を行い、貯金500万円に向けて計画的にお金を貯めていきましょう。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎