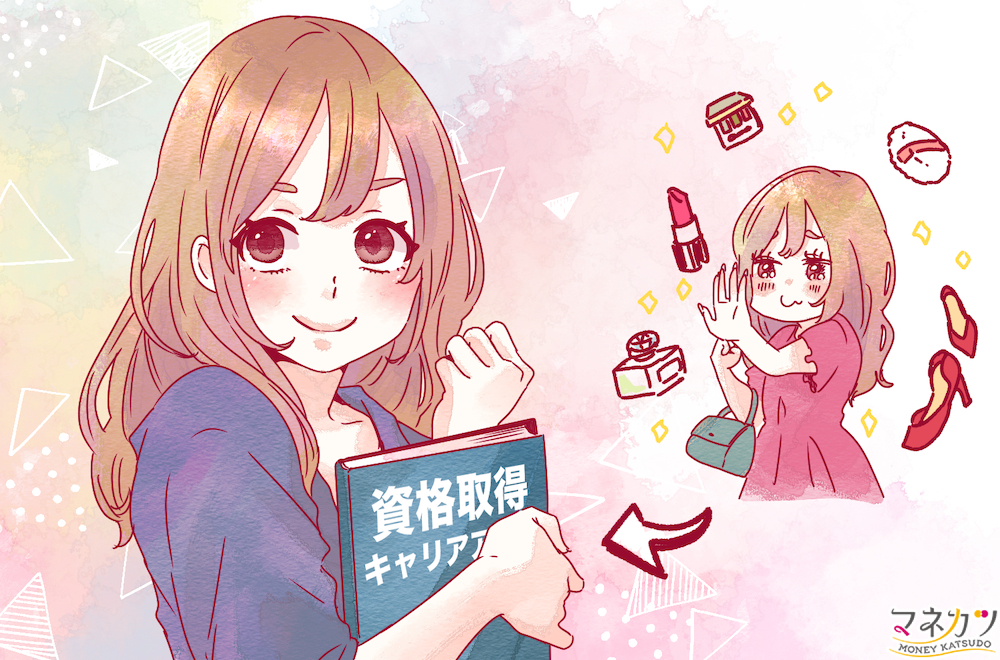相続アドバイザーとは?仕事内容や2級・3級の資格試験について解説
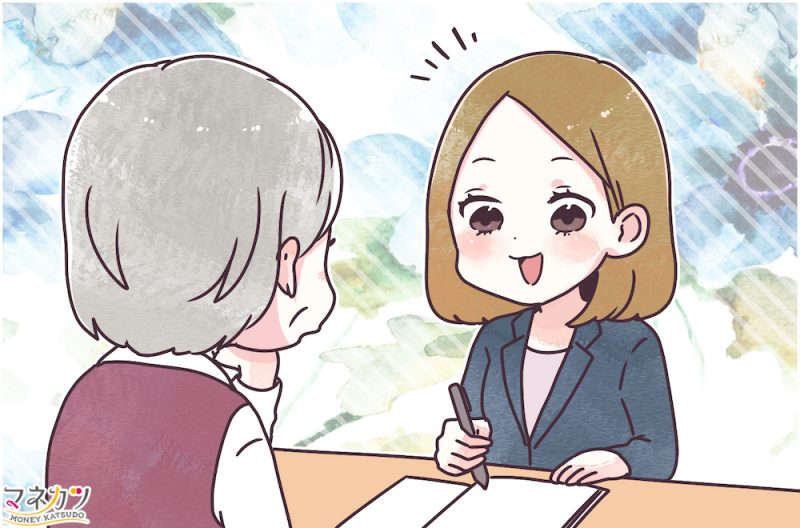

記事監修者
マネカツ編集部
"将来への漠然としたお⾦への不安はあるけど、何から始めていいのかわからない…"
そんな方に向けて「資産運用」や「税金対策」など、お金に関する情報を発信しています。

記事監修者
マネカツ編集部
"将来への漠然としたお⾦への不安はあるけど、何から始めていいのかわからない…"
そんな方に向けて「資産運用」や「税金対策」など、お金に関する情報を発信しています。
相続が発生すると、遺産の分割や相続後の登記、税金の手続きなどすべきことが多くあります。
さまざまな手続きのサポートやアドバイスを行う専門家が「相続アドバイザー」です。
この記事では、相続アドバイザーの仕事内容や必要な資格、資格取得におすすめの通信講座についてご紹介します。
相続アドバイザーの仕事に興味をお持ちの方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎
相続アドバイザーとは

相続が発生すると、遺産の分割や不動産の名義変更、相続税の申告などさまざまな手続きが必要となります。
こうした手続きをサポートする専門家が相続アドバイザーです。
相続アドバイザーの定義
「相続アドバイザー」とは、相続が発生した際に行う手続きや相続対策などについてのアドバイスを行う専門家のことを指します。
分からないことや不安なことが多い相続について、必要なアドバイスを行う仕事です。
また、「相続アドバイザー」という資格を指す場合もあります。
銀行業務検定協会が主宰している資格や、NPO法人 相続アドバイザー協議会が主宰しているものがあります。
相続アドバイザーの仕事
相続アドバイザーの主な仕事内容は、相続に関する手続きのアドバイスや各専門家との仲介がです。
依頼者の相続問題について状況を把握し、相続手続きをスムーズに進めるために必要な情報を提供します。
そして、必要な手続きを代行できる税理士や弁護士などの紹介まで行います。
依頼人の相続問題に寄り添い、適切なサポートを行うのが相続アドバイザーの仕事です。
なお、相続アドバイザー資格を持っていても相続手続きの代行などを行えるわけではないため注意が必要です。
どのような業種で活躍できるのか?
相続アドバイザーが活躍できる業種は、銀行・証券会社などの金融機関の窓口相談員やファイナンシャルプランナー、司法書士などです。
顧客の相続について相談を受けることが多い業種の場合、相続アドバイザーの役割を果たすことができます。
相続アドバイザーを頼るメリット

相続アドバイザーを頼るメリットとして以下の3点が挙げられます。
- どの専門家に相談すれば良いか分からないときの第一窓口になる
- 各専門家に相談する手間や費用が不要
- 銀行等の窓口にいるので相談しやすい
それぞれのメリットを解説します。
どの専門家に相談すれば良いか分からないときの第一窓口になる
相続が発生すると、遺産の分割協議や不動産の名義変更、相続税の申告などさまざまな手続きが必要となります。
手続きの種類が多すぎてどの専門家に相談すべきか分からなくなるケースは少なくありません。
相続アドバイザーは、相続全般についてのアドバイスをしてくれる上に、各手続きで必要な専門家とつないでくれることが特徴です。
「何から始めたら良いか分からない」という場合でも、必要となる手続きや準備すべき書類などについてひとつずつアドバイスしてくれます。
相続で困ったことがあれば、まず始めに相続アドバイザーに相談することをおすすめします。
各専門家に相談する手間や費用が不要
相続アドバイザーに相談するメリットとして、余計な手間や費用をかけずに済むという点も挙げられます。
自分で弁護士や税理士を探す場合、相続問題に強い専門家を探さなければなりません。
また、相続問題について一から相談すると、高額な費用が発生してしまうケースも考えられます。
相続アドバイザーは、相続問題に強い弁護士や税理士をに紹介してくれるため、自分で探す手間が省けます。
相続全般についてのアドバイスにも対応しているため、弁護士や税理士に支払う費用を安く抑えられることもあるでしょう。
各専門家に相談する手間や費用を抑えられる点は相続アドバイザーに相談するメリットです。
銀行等の窓口にいるので相談しやすい
相続アドバイザーは、銀行や保険会社の窓口に配属されているケースが多いです。
普段利用している銀行の窓口で対応してもらえるため、気軽に相談できる点がメリットとして挙げられます。
銀行は全国各地に支店があり、地方にお住まいの方でも利用しやすいことが特徴です。
弁護士や税理士などの専門家が近くにいない場合でも、銀行の相続アドバイザーであれば比較的相談しやすいためおすすめです。
相続アドバイザーの資格:「相続アドバイザー検定2級・3級」

相続アドバイザーの仕事は、資格を持っていなくても行うことができます。
しかし資格を持っていると知識があることを証明できたり、依頼人から信頼されたりするため、取得するメリットは十分にあります。
相続アドバイザーになりたい方は、資格の取得を目指すのも良いでしょう。
ここでは、銀行業務検定協会が主催する相続アドバイザーの2級・3級について解説します。
相続アドバイザー2級・3級の試験概要
相続アドバイザー2級・3級は、相続の手続きや実務に必要な知識を測るための資格試験です。
3級は、相続に関する手続きや被相続人にかかる金融取引の実務、相続税の相談等において必要な知識の習得を測定します。
2級は、3級の上級試験として相続に関する実務や相続対策のアドバイスなどを応用問題によって測ります。
相続アドバイザー検定2級・3級出題範囲
相続アドバイザー3級の出題範囲は以下の通りです。
- 相続の基礎知識
- 相続と金融実務
- その他周辺知識
一方、相続アドバイザー2級の出題範囲は以下の通りです。
- 相続知識(相続の開始と手続期限、相続と遺贈、相続税・贈与税の知識など)
- 相続対策(資産の状況把握、遺産分割、生前贈与による相続対策など)
- 相続アドバイス(遺産分割アドバイス、リタイアメントプランニング、遺言書の作成など)
- 相続手続(相続発生時の確認事項、遺産の相続手続、相続手続必要書類など)
2級になると出題範囲が広がり、内容もより詳細になります。
試験を受ける際は事前に出題範囲を把握しておきましょう。
相続アドバイザー検定2級・3級の試験日
相続アドバイザー資格の試験日は以下の通りです。
- 相続アドバイザー3級:年2回(3月・10月)
- 相続アドバイザー2級:年1回(3月)
試験日のおよそ2ヶ月前から申込受付期間が始まるため、早めに確認して申し込みましょう。
相続アドバイザー検定2級・3級の試験地
相続アドバイザー資格の試験は、全国約180ヶ所の試験会場で行われています。
受験する際は受験票に試験会場が記載されるため、事前に確認しておきましょう。
受験地一覧は以下のページから確認できます。
相続アドバイザー検定2級・3級の試験時間
相続アドバイザー試験の実施時間は以下の通りです。
- 相続アドバイザー3級:13:30〜15:30(120分)
- 相続アドバイザー2級:13:30〜16:30(180分)
相続アドバイザー3級試験は以前まで150分でしたが、2022年度より120分に変更されています。
また、2級・3級ともに試験開始後60分間と終了前10分間の退席は禁止されています。
相続アドバイザー検定2級・3級の出題形式
相続アドバイザー検定の出題形式は以下の通りです。
- 相続アドバイザー3級:四答択一マークシート式40問(各2点)・事例付四答択一式10問(各2点)
- 相続アドバイザー2級:四答択一式25問(各2点)・記述式5題(各10点)
相続アドバイザー検定2級・3級の合格基準
相続アドバイザー検定は、3級・2級ともに「100点満点中の60点以上(試験委員会にて最終決定)」で合格となります。
過去問などでしっかりと対策し、60点以上を確実に取れるように準備しておくことが大切です。
相続アドバイザー検定2級・3級の合格率
相続アドバイザー3級は、30%後半から40%半ばの合格率で推移しています。
3級とはいえ簡単な試験ではないため、しっかりと対策しておくことが大切です。
また、相続アドバイザー2級は20%前半から40%前後の合格率で推移しています。
実施回によって合格率にバラつきがあるため、油断せずに対策しておきましょう。
相続アドバイザー検定2級・3級の過去問
相続アドバイザー試験の過去問の勉強には、問題集の活用がおすすめです。
例年11月中旬に公式の受験用問題解説集が発売されるため、対策を行いましょう。
相続アドバイザー3級は、毎年7月中旬ごろに公式テキストが発売されていますので併用して対策するのがおすすめです。
相続アドバイザー実施・運営団体である経済法令研究会のホームページで公式テキストが販売されていますので、詳しく知りたい方は確認してみてください。
NPO法人 相続アドバイザー協議会の養成講座を受けて相続アドバイザーになる方法もある
NPO法人 相続アドバイザー協議会の養成講座を受講し、相続アドバイザーに必要な知識を身に付ける方法もあります。
相続アドバイザー協議会の養成講座の概要は以下の通りです。
| 受講時間 | 全18講座(1講座2時間) |
| 講座 | 第1講座〜第12講座:ビデオ講座 第13講座〜第18講座:対面講座またはWebでの生配信受講 |
| 受講料 | 初めて受講する方:165,000円(税込) 認定会員:55,000円(税込) |
実務を経験している専門家による講座を受けられる点が魅力です。
相続アドバイザーとして活躍したいと考えている方は、ぜひ受講を検討してみましょう。
相続アドバイザーの資格取得におすすめの通信講座

ここでは、相続アドバイザーの資格取得におすすめの通信講座を2つ紹介していきます。
資格の取得を目指している方はこちらの通信講座も検討してみましょう。
経済法令研究会 相続アドバイザー養成コース(SD)
おすすめの通信講座1つ目は、経済法令研究会の「相続アドバイザー養成コース」です。
カリキュラムは相続アドバイザー2級に対応した内容となっていますが、資格取得者だけでなく営業担当者や窓口担当者なども対象としています。
相続アドバイザー養成コースの概要は以下の通りです。
| 受講期間 | 3ヶ月 |
| 添削回数 | 3回 |
| 受講料 | 13,860円(税込) |
相続開始後の実務や生前対策などの基礎知識をしっかりと身に付けられます。
相続アドバイザー試験の合格を目指している方は、相続アドバイザー養成コースがおすすめです。
TAC相続検定
おすすめの通信講座2つ目は、TAC検定のコースです。
さまざまな資格について講座を提供しているTACの講座であるため、安心して受講できます。
TAC相続検定コースの概要は以下の通りです。
| 受講回数 | 全9回 |
| カリキュラム | 2級基本講義8回+2級実践演習+2級模擬試験(試験1回分) |
| 受講料 | 通常受講料:28,000円 再受講割引受講料:14,000円 |
「相続アドバイザー」は銀行員の立場として必要な知識が問われる内容が多いです。
一方「相続検定」は、銀行員だけでなく一般の方でも円満な相続を実現するために、生前に行う対策についての知識を問う出題内容になっています。
相続検定の勉強をすることで相続に関する専門的・実務的な知識が身につくため、相続アドバイザー資格の勉強にも活かせることが多いでしょう。
参考:TAC株式会社「[試験・学習]出題内容について相続アドバイザー試験とFP試験との違いは何ですか?」
まとめ:相続アドバイザーの特徴を理解しましょう
相続アドバイザーとは、相続に関するアドバイスや税理士・弁護士などの専門家との仲介を行う仕事です。
銀行や証券会社、ファイナンシャルプランナー、司法書士など、相続の相談に携わることが多い業種で活躍しています。
相続アドバイザーとして活動したい場合、相続アドバイザーの資格取得がおすすめです。本記事でご紹介した試験の詳細やおすすめの通信講座を参考に、相続アドバイザー資格の取得を目指しましょう。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎