税金の数と種類一覧!国税と地方税それぞれを解説


記事監修者
マネカツ編集部
"将来への漠然としたお⾦への不安はあるけど、何から始めていいのかわからない…"
そんな方に向けて「資産運用」や「税金対策」など、お金に関する情報を発信しています。

記事監修者
マネカツ編集部
"将来への漠然としたお⾦への不安はあるけど、何から始めていいのかわからない…"
そんな方に向けて「資産運用」や「税金対策」など、お金に関する情報を発信しています。
皆さんは消費税や所得税などを納めていると思いますが、一体いくつの税金の種類があるかご存知でしょうか。
そこで今回は、税金をどこへ納めるか、もしくはその納め方によって変わってくる税金の種類、仕組みなどを余すことなくご紹介していきます。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎
この記事の目次
税金は大きく分けて「国税」と「地方税」の2種類

まず税金は、どこへ納めるかによって「国税」と「地方税」の2種類に大別することができます。
国が課す「国税」
国が課す、つまり国に納める税金が国税です。国税には、法人税や所得税、消費税、酒税、たばこ税などがあります。
地方自治体が課す「地方税」
一方で、都道府県や市区町村といった地方自治体が課す、すなわち地方自治体に納める税金が地方税です。地方税には、住民税(道府県民税と市町村民税)や自動車税などがあります。
直接税と間接税の違い
また、税金の納め方によって「直接税」と「間接税」の違いがあります。まず直接税は、税金を納める人と負担する人が同じ税金のことです。
直接税には、所得税や法人税、住民税(道府県民税と市町村民税)などがあります。一方で、間接税は税金を納める人と負担する人が異なる税金のことです。間接税には、消費税や酒税、たばこ税などがあります。
これまでお伝えしてきた国税・地方税と、直接税・間接税それぞれに該当する税金を分類しますと下記の通りになります。
- 直接税:所得税、法人税、相続税、贈与税など
- 間接税:消費税、酒税、たばこ税、関税など
- 地方税(道府県税)
- 直接税:道府県民税、事業税、自動車税など
- 間接税:地方消費税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税など
- 地方税(市町村税)
- 直接税:市町村民税、固定資産税、軽自動車税など
- 間接税:市町村税たばこ税、入湯税
このように、税金はどこへ納めるか、どのように納めるかによってさまざまな種類に分別されています。次項から国税・地方税と、直接税・間接税それぞれの仕組みなどを詳細に解説していきます。
出典:国税庁「税の種類と分類」
国税の種類

国税の種類一覧は下記のとおりです。
| 税金の納め方 | 税金の種類 |
| 直接税 | 所得税 法人税 相続税 贈与税 復興特別所得税 地方法人税 地方法人特別税 |
| 間接税 | 国税の消費税 酒税 たばこ税 たばこ特別税 石油ガス税 石油石炭税 自動車重量税 登録免許税 地方揮発油税 揮発油税 航空燃料勢 印紙税 関税 電源開発促進税 |
国税の直接税
1:所得税
個人の儲けに対して課税される税金で、例えば勤務先の会社から受け取る給料やボーナス、もしくは自営業を営むことで稼いだ利益にかかります。
所得税の計算方法は、1年の間に受け取ったすべての所得からさまざまな所得控除を差し引いた残りの所得(課税所得と呼ぶ)に税率をかけて求められます。
なお所得控除とは、それぞれ、その人の状況に応じて税負担を調整する制度のことで、医療費控除や基礎控除、配偶者控除などがあります。
また税率は、累進課税という仕組みとなっており、所得が多い人ほど段階的に高くなるようになっており、国民1人1人の収入に応じて公平な税負担となるように考えられています。
所得税の納税方法は、会社に勤めるサラリーマンの場合は、勤務先の会社が本人の給料から所得税を差し引き、本人に代わって納税を行います。いわゆる源泉徴収のことです。
一方で、自営業の人は、会社が代わりに納税を行ってくれることがないため、自分自身でその年1年間の所得と税額を計算し、税務署に申告することになります。
つまり、確定申告を行い、所得税を納める ことになります。
2:法人税
会社が利益をあげた際にかかる税金のことです。法人税は、各企業により決められた決算期が終わったあとに、その期の所得から税額を計算し確定申告を行い、法人税を納めることになります。
3:相続税
一定額以上の財産を相続したときに、相続した人に課せられる税金です。 亡くなられた人から相続や遺贈などにより得た財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合に、相続税の課税対象となります。
なお基礎控除額は下記の計算式で求められます。
- 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
4:贈与税
4つ目が贈与税です。こちらは個人から財産をもらった時に課せられる税金です。また自分自身で保険料を支払っていない生命保険金を受け取った場合も、贈与と見なされ、贈与税の対象となります。
なお贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。
まず暦年課税とは、個人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかります。
一方で、相続時精算課税を選択した場合は、その年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額が贈与税の対象となります。
出典:国税庁「贈与税について」
5:復興特別所得税
5つ目は復興特別所得税です。こちらは、東日本大震災からの復興のため、さまざまな施策を行うのに必要となる財源確保を目的する税金です。
2013年から2037年まで、基準所得税額の2.1%が、復興特別所得税として徴収されることになっています。
6:地方法人税
地方法人税は、2014年10月から徴収され始めた比較的新しい国税となります。
こちらは、法人税の納税義務のある法人が、地方法人税も納める必要があり、地方法人税確定申告書の提出を行います。なお地方法人税の税額は、課税標準法人税額に 4.4%の税率を乗じた金額となります。
7:地方法人特別税
地域間の財政力格差の是正を図る目的で、法人事業税の一部を分離し創設されたものです。
そのため、法人事業税の納税義務がある法人が、この地方法人特別税を納める必要があります。
国税の間接税
1:国税の消費税
1989年から導入された国税で、ものを買ったりサービスを受けたりしたときなどにかかる税金になります。
消費税は広く公平な税負担を求める間接税で、最終的に消費者が負担し、事業者が納税します。
日本の消費税の税率は6.3%、 地方消費税の税率が1.7%で、この2つを合わせて8%の税率になります。
2:酒税
日本酒やビール、ウィスキーなどのお酒にかかる税金です。アルコール度数が1度以上の飲料が対象となり、税額はお酒の種類やアルコール度数によって細かく決められています。
製造業者もしくは輸入業者が納税しますが、価格に税金が含まれているため、負担しているのは消費者となります。
3:たばこ税
各種たばこにかかる税金のことです。
酒税と同様に、製造業者もしくは輸入業者などが納税するものの、たばこの価格に税金が含まれているため、負担しているのは消費者となります。
そして、たばこ税は国に納められる国税と、地方に納められる地方税に分けられます。地方税に関してはのちほど解説します。
4:たばこ特別税
たばこ税同様、製造業者が納税し、負担するのは消費者となります。
5:石油ガス税
液化石油ガス利用する際に課せられる税金のことです。タクシーなどの利用が多いようです。
6:石油石炭税
原油や輸入石油製品などに課せられる税金です。
7:自動車重量税
車検などの際に自動車の重量などに応じて課税されます。なお、環境性能の高い自動車に対しては、自動車重量税が減免される措置が施行されています。
8:登録免許税
不動産の権利の登記、や船舶、航空機などの登録、法人登記、医師・弁護士など資格の登録など、登記や登録などの際に課税されます。
9:地方揮発油税
地方自治体の財源確保のため、ガソリンにかかる国税として徴収される税金です。
10:揮発油税
自動車の燃料となるガソリンに課せられる国税となります。
11:航空燃料税
その名通り、航空機に使用される燃料に課せられる税金です。
12:印紙税
不動産の譲渡契約書や株券など課税対象となる文書に対して課される税金のことです。
13:関税
一般的に輸入品に課せられる税金のことです。
14:電源開発促進税
地方税の種類

| 道府県税 | 市町村税 | |
| 直接税 | 道府県税(住民税) 事業税 自動車税(環境性能割・種別割) 軽自動車税(環境性能割・種別割) 固定資産税 鉱区税 不動産取得税 狩猟税 核燃料税 | 市町村税 自動車税(環境性能割・種別割) 軽自動車税(環境性能割・種別割) 固定資産税 鉱産税 特別土地保有税 事業所税 都市計画税 水利地益税 共同施設税 宅地開発税 国民健康保険税 |
| 間接税 | 地方消費税 ゴルフ場利用税金 道府県たばこ税 軽油取引税 | 市町村たばこ税 入湯税 |
道府県税の直接税
1:道府県税
住民が、それぞれ住んでいる都道府県に納める税金のことです。
道府県税は、住民が平等に負担する金額(均等割と呼ぶ)と、前年の所得の額に応じて負担する金額(所得割)から構成されています。
またその道府県に事務所、事業所を設けている法人についても、法人県民税として、均等割、法人税割で納めます。
2:事業税
法人や個人事業に対して、その事業所の所在する道府県で利益に課せられる税金です。
3:自動車税(環境性能割・種別割)
2019年10月から、自動車取得税と自動車税が廃止され、環境性能割と種別割が導入されました。
環境性能割は、自動車を購入する際に、環境に与える影響に応じて課せられる税金です。
種別割は、毎年4月1日に自動車の車検証上の所有者に対して課せられる税金です。
4:軽自動車税(環境性能割・種別割)
自動車税(環境性能割・種別割)と同じ税金です。
対象が軽自動車や原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車などを所有する人となっています。
5:固定資産税
土地や家屋などの固定資産の所有者に課せられる税金です。
6:鉱区税
鉱区税は、鉱区に鉱業権を所有する人に課せられる税金です。
7:不動産取得税
不動産取得税は、土地や家屋を取得したときに課せられる税金です。
8:自動車取得税
自動車取得税は、3輪以上の軽自動車や普通自動車などを取得したときに課せられる税金です。
9:狩猟税
狩猟税は、狩猟者が登録する際に課せられる税金です。
10:核燃料税
核燃料税は、原子力発電所の安全対策などの費用に充てるため、原子力発電所を立地する自治体が、電気事業者に対し課せられる税金です。
道府県税の間接税
都道府県税のうち間接税は以下の4種類になります。
1:地方消費税
ものを買ったりサービスを受けたりしたときなどにかかる税金になります。地方自治体の財源確保を目的に導入されています。
2:ゴルフ場利用税
ゴルフ場利用税は、その名の通り、ゴルフ場を利用する人に対して課せられる税金です。
3:道府県たばこ税
たばこの製造業者や輸入業者などが、その道府県内のたばこ小売業者にたばこを売り渡す際に課せられる税金です。
4:軽油引取税
軽油引取税は、軽油の元売り業者から軽油を引き取った人に課せられる税金です。
市町村税の直接税
ここからは、地方税のうち直接税である11種類をご紹介します。
1:市町村税
こちらは、その市町村に住所を有する個人、そして住所を有する法人等が、市区町村に納める税金のことです。
2:自動車税(環境性能割・種別割)
2019年10月から、自動車取得税と自動車税が廃止され、環境性能割と種別割が導入されました。
環境性能割は、自動車を購入する際に、環境に与える影響に応じて課せられる税金です。
種別割は、毎年4月1日に自動車の車検証上の所有者に対して課せられる税金です。
3:軽自動車税(環境性能割・種別割)
自動車税(環境性能割・種別割)と同じ税金で、対象が軽自動車や原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車などを所有する人となっています。
4:固定資産税
土地や家屋を所有する人に対し、市区町村が課す税金です。
5:鉱産税
鉱物の採掘事業を行う鉱業者に課せられる地方税です。
6:特別土地保有税
土地の有効利用や投機的取引の抑制を図るために設けられた税金で、一定規模以上の土地を取得もしくは所有する人に課せられる税金です。
7:事業所税
一定規模以上の事業を行っている事業主に対して課税される税金です。
8:都市計画税
それぞれの自治体で条例を制定して課税されるものです。都市計画事業や土地区画整理事業を推進する費用に充てるため、市街化区域内の土地や家屋に対して課せられる税金です。
9:水利地益税
水利事業や林道事業などの費用に充てるために、それらの事業から利益を受ける土地や建物に課せられる税金です。
10:共同施設税
共同集荷場や汚物処理場などの費用に充てるために、それらの施設の利用者に対して課せられる税金です。共同施設税は、1971年度以降、課税している市町村はありません。
11:宅地開発税
市街化区域のうち公共施設の整備が必要とされる地域内で宅地開発を行う場合宅地の面積によって課せられる税金です。
12:国民健康保険税
国民健康保険の被保険者に属する世帯主に課せられる税金です。
市町村税の間接税
ここからは、地方税のうち間接税の2種類をご紹介します。
1:市町村たばこ税
国税のたばこ税と同様に、各種たばこにかかる税金です。たばこの製造業者が、小売販売業者に売り渡し本数に応じてかかるものです。
2:入湯税
その名の通り、鉱泉浴場に入湯する人に対し課せられる税金です。
税金を少なくするためにできること

私たちはさまざまな場面で税金を納付しています。
税金を納付する際は、各種控除や税制優遇制度が使えないか確認しましょう。
ここでは、税金を少なくするためにできる3つのことを紹介します。

サラリーマンができる税金対策一覧!24選の税金対策を紹介
ふるさと納税を利用する
1つ目はふるさと納税です。
ふるさと納税は、本来は現在住んでいる自治体に納めるべき税金を、応援したい自治体に寄付(ふるさと納税)することで、住民税や所得税が控除される仕組みです(寄附金控除)。
寄付のお礼として自治体から特産物を中心とした返礼品がもらえます。
寄付した合計金額から、2,000円を差し引いた額が翌年の住民税から控除されます(所得税還付の場合もあり)。
注意点として、ふるさと納税で控除される金額には上限があり、人によって異なります。
詳しくはふるさと納税について解説している以下の記事をご確認ください。
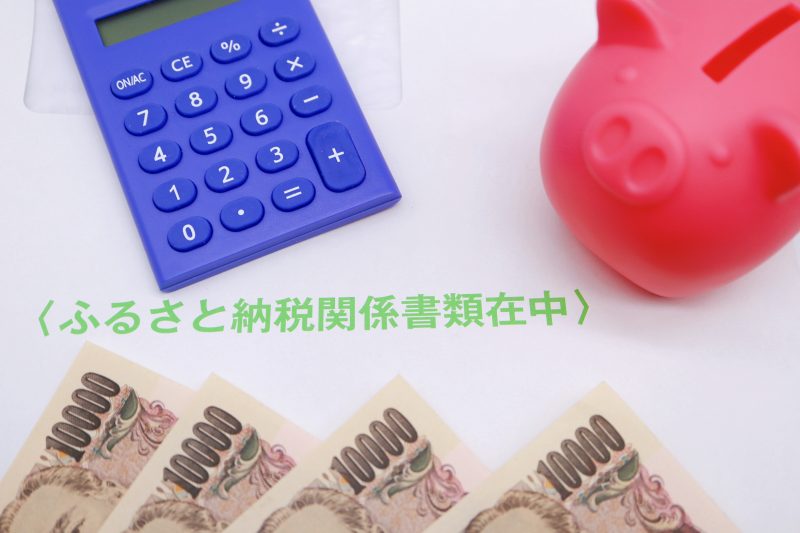
【2025】ふるさと納税とは何かわかりやすく解説!やり方や仕組み
医療費控除を利用する
2つ目は医療費控除です。
1月1日から12月31日までの1年間に負担した医療費が一定額を超えた際に、所得控除を受けられる制度です。
一定額とは、その年の所得総額の5%か10万円のうち、いずれか低い方の金額となります。
所得総額が200万円以上の方であれば、医療費が10万円を超えた年に利用できます。
医療費控除は納税者本人だけではなく、生計を一にする配偶者と子ども、その他の親族です。
病院の診察料以外にも、治療のための医薬品の購入や一定条件を満たした通院の交通費なども医療費に含まれます。
出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
出典:国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」
NISAやIDeCoを利用する
3つ目はNISAやiDeCoの利用です。
NISAやiDeCoは投資をする方に向けた税制優遇制度です。
本来であれば、投資で得た利益には20.315%の税金が発生しますが、NISAやiDeCoを利用するとこの税金が非課税となります。
NISA
NISAは「一般NISA」と「つみたてNISA(積立NISA)」に分かれています。
投資初心者の方にはつみたてNISAがおすすめです。
つみたてNISAは年間40万円まで投資可能で、対象商品は長期投資に向いている銘柄に加え国が認めた投資信託とETFのみです。
2024年からはNISA制度が新しくなります。
詳しくは以下の記事をご確認ください。
新NISAとは?変更点やいつからか、積立NISAと比べて解説
iDeCo
iDeCoは老後資産の形成に特化した制度です。
掛金は毎月5,000円から1,000円単位で指定でき、上限額は職業や他の年金を利用しているかによって異なります。
投資した金額(掛金)は全額控除される点からNISAよりも節税効果は高いですが、原則60歳までは引き出せない点に注意が必要です。
詳しくは以下の記事をご確認ください。

iDeCo(イデコ)とは?仕組みや始め方、注意点をわかりやすく解説
まとめ:税金の数と種類を把握しよう

国税25種類、地方税26種類それぞれご紹介してきました。皆さんはいくつの税金をご存じだったでしょうか。
税金のことを少しずつでも知っていき、より賢く、そして豊かな生活を送ってください。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎







