iDeCo(イデコ)とは?仕組みや始め方、注意点をわかりやすく解説

老後の資産形成方法として人気を集めているのが「iDeCo」と呼ばれる個人型確定拠出年金です。
iDeCoにはNISAや積立NISA以上の節税効果があり、おすすめの資産運用として年々利用する人が増えています。
とはいえ、iDeCoの仕組みを理解せずに運用を開始することはおすすめできません。
この記事では、idecoの特徴や仕組み、はじめ方や注意点などを解説します。
自分がいくらまで掛金を拠出できるのか、加入資格を満たしているのかなど、事前に確認しておきましょう。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎
この記事の目次
iDeCo(イデコ)とは

iDeCoとは、「個人型確定拠出年金」と呼ばれる個人年金制度です。
確定拠出年金法に基づいて実施されている制度で、国民年金や厚生年金とは異なり、加入は任意です。
特徴については、以下が挙げられます。
- 個人で積み立てる個人年金制度
- 運用する商品・金額を自分で選択する
- NISA(積立NISA)に比べて節税効果が大きい
- 一度加入すると途中で解約できない
ここでは特にポイントとなる点を紹介します。
個人で積み立てる個人年金制度
iDeCoは毎月一定額を積み立てし、自身が選んだ金融商品を運用します。
国民年金や厚生年金のように決められた金額を掛けるものではなく、決められた範囲で自由に支払金額を設定することができます。
iDeCoは企業型の確定拠出年金とは違って、自営業(個人事業主)や主婦の方でも利用することが可能です。
毎月5,000円から1,000円単位で金額を指定できますが、上限額に関しては職業によって異なります。
税制優遇の効果が大きい
iDeCoには3つの税制優遇があります。
- 掛金が全額控除される
- 運用益が非課税
- 受取時に控除が受けられる
NISAと比較されることが多いですが、基本的にはiDeCoを利用したほうが節税効果は大きいです。
掛金が全額所得控除の対象であるため課税所得が減少し、その年の所得税と翌年の住民税が軽減されます。
また、NISA(積立NISA)と同様に金融商品を非課税で運用することが可能です。利益が発生した場合も、20.315%の税金はかかりません。
iDeCoで運用した資金は60歳以降に受け取れますが、その際にも税制優遇が受けられます。
iDeCoはNISAと併用することが可能なので、資金に余裕がある方は併用することも検討してみてください。
【注意】一度加入すると途中解約はできない点に注意
iDeCoを申し込む前に1つだけ注意しなければならないことがあります。
iDeCoは途中解約ができないという点です。
一度加入すると原則60歳までは運用し続ける必要があります。
仮に掛金を拠出できない場合は掛金の減額や一時停止が可能ですが、積み立てた資金を引き出すことはできない点に注意が必要です。
iDeCoの運用を開始した場合は、資金を受け取るのは60歳以降になることを覚えておきましょう。
iDeCo(イデコ)と公的年金の違い

運用する商品を自分で決める必要がある
iDeCoでは積み立てた資金で運用する商品を自分で決める必要があります。
一方で、公的年金は国民から徴収した資金の一部を、「GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)」が代わりに運用しています。
そのため、公的年金は個人で運用することはありません。
iDeCoの運用商品は、大きく分けると「定期預金」「保険」「投資信託」の3種類になります。
| 分類 | メリット | デメリット |
| 定期預金 | 元本割れのリスクがない | 低金利なため、リターンをあまり見込めない |
| 保険 | 元本割れのリスクがない | 利息は円金利がベースなため、現在ではリターンをあまり見込めない |
| 投資信託 | 運用の成果によって、大きなリターンを見込める | 元本割れのリスクがある |
注意点として、iDeCoで運用する商品には、元本割れリスクがあるものも含まれています。
元本割れのリスクがない商品は「定期預金」と「保険」で、元本割れのリスクがある商品は「投資信託」です。
投資信託は元本割れのリスクがある代わりに、定期預金や保険に比べて高いリターンを期待できるため、老後資金を多く確保できる可能性が高くなっています。
運用する機関やリスク許容度に応じて運用する商品を選びましょう。
投資信託の投資対象別のリスクとリターン
購入する投資信託によって投資対象が分かれており、投資対象によってリスクとリターンが異なります。
投資信託の種類は大きく5種類に分けられます。
| 分類 | 特徴 |
| 国内株式型 | 価格変動リスクは高いが、その分リターンを期待できる |
| 外国株式型 | 価格変動リスクに加えて、為替変動リスクがある |
| 国内債券型 | 金利リスクがあるものの、比較的安定したリターンを狙える |
| 外国債券型 | 金利リスクに加えて、為替変動リスクがある |
| バランス型 | 国内外の株式・債券を組み合わせて運用する商品1つの商品でより高い分散投資の効果を狙える |
株式と債券を比較すると、株式の方がハイリスク・ハイリターンとされており、国内と外国を比較すると、外国の資産に投資する方がハイリスク・ハイリターンとされています。
一般的に、投資では高いリターンを期待するほど、損失時のマイナスも大きくなります。
投資信託の運用手法
投資信託の投資対象とは別で、運用手法によっても期待できるリターンは異なります。
運用手法には「インデックス型」と「アクティブ型」の2種類があります。
インデックス型は、アメリカの「S&P500」や日本の「TOPIX」「日経225」などの株価指数と同じ値動きを目指す運用手法です。
指数と同じ銘柄で揃えられる場合がほとんどなので、運用に関する手間の少なさから手数料が低い物が多い特徴があります。
一方、アクティブ型は上記の指数以上のリターンを狙う運用手法です。
指数以上のリターンを得られるケースもあれば、指数以下のリターンとなるケースもあります。
アクティブ型の投資信託では、運用会社が銘柄の調査・分析や積極的な売買などを行うため、インデックス型よりも手数料が高く設定されている点に注意が必要です。
受け取り金額が運用方法によって異なる
iDeCoで運用した資金は、運用方法によって受け取り金額が異なります。
公的年金として受け取れる金額は、納めてきた期間や保険料の総額によって決まります。
個人の運用成績が受け取り金額に反映される点が、iDeCoと公的年金の大きな違いです。
運用商品によってiDeCoで受け取れる金額にどの程度差が生じるかを見ていきます。
一方は年利0.01%の定期預金、もう一方は年利3%のリターンが見込める投資信託で比較します。
毎月の積立額は2万円で、積立期間は25年間を想定しています。
| 元本 | 25年の運用益 | 合計 | |
| 定期預金 | 600万円 | 7,481円 | 600万7,481円 |
| 投資信託 | 600万円 | 292万円 | 892万円 |
定期預金と投資信託を比較すると、25年で約300万円もの違いが生じており、定期預金はほとんど資産が増えていないのがわかります。
とはいえ、投資信託は元本割れのリスクがある商品であり、運用がうまくいかない場合は25年後に受け取れる資産が600万円以下になる可能性もあります。
iDeCo(イデコ)の仕組み・始め方

運用する証券会社を選び口座を開設する
iDeCoを始めるためには、iDeCo口座を開設する必要があります。
銀行や証券会社、保険会社などからiDeCoを運用する金融機関を選びましょう。
なお、iDeCo口座は1人1口座までしか開設できません。
運用途中に別の金融機関に口座を作りたい場合は、変更手続きが必要です。
手間がかかるため、口座開設前によく確認してから開設しましょう。
金融機関選びのポイントは、以下の3点です。
- 商品ラインナップ
- サポートの充実度
- 手数料

iDeCoを利用するおすすめの証券会社は?選ぶ基準や始め方も解説!
商品ラインナップ
商品ラインナップは、金融機関によって異なります。
どのような商品で運用するか、どの程度のリターンを求めるか、などを踏まえた上で商品ラインナップを確認しましょう。
サポートの充実度
金融機関によって、対面・非対面やWebサイトの取引画面の見やすさ・使いやすさなどが異なります。
資産運用に関してある程度知識がある方、これから勉強しようと考えている方は、手数料が安い傾向にあるネット証券などの非対面で運用できる金融機関がおすすめです。
手数料
iDeCoを運用する際には、手数料がかかります。
iDeCo口座を開設する金融機関によって金額が異なるため、なるべく手数料が安いところを選ぶといいでしょう。
サポートと同様、ネット証券は手数料が安い傾向にあります。
毎月拠出する掛金を決める
次に、毎月拠出する掛金を決めます。
最低5,000円から1,000円単位で設定することが可能ですが、掛金変更は1年に1回しかできないため無理のない金額に設定しましょう。
投資は続けることが大事ですので、日々の生活を圧迫しない金額に設定することが大切です。

iDeCoの掛金はいくら?5000円は意味ない?上限額や毎月の目安
運用する商品と掛金比率を決める
次に、運用する商品と掛金比率を決めます。
運用する商品と比率によって期待できるリターンが変動します。
複数の資産を組み合わせて運用できるため、毎月の掛金と老後資金として準備したい金額を踏まえて、資産配分を決めましょう。
高いリターンを求めたい方は「投資信託」、元本を減らしたくない方は「定期預金」「保険」から選ぶのがおすすめです。
これらを組み合わせて運用することも可能できます。
例えば定期預金と投資信託を半分ずつで運用すれば、ある程度元本を確保しながらリターンを求めることが可能です。

楽天VTIとは?メリット・デメリットや利回りを解説
60歳以降に積み立てたお金を受け取る
60歳以降になると、iDeCoで積み立てたお金を受け取れます。
受け取るタイミングによってメリット・デメリットがあるため、慎重に判断する必要があります。
iDeCoの受取タイミングを遅らせるメリットは、非課税運用の期間を継続できる点です。
老後資金に余裕がある方であれば、受取タイミングを延長させることで更なる資産拡大に期待できます。
デメリットは、受取開始時期に制限があり、その期間と暴落が重なるリスクがある点です。
一方で早めにiDeCoを受け取るメリットは、その時点での評価額を確保できる点です。
iDeCoで確保した老後資金を元に老後生活をスタートし、公的年金の繰下げ受給を狙う選択肢もあります。
受け取り開始時期が75歳まで拡大
2022年4月に施行された法改正により、iDeCoの受取開始時期が75歳までに拡大されました。
この改正により、75歳まで非課税運用の期間を継続できます。
運用期間が伸びる分、リターンを増やせる可能性が大きくなったことになります。
iDeCo(イデコ)に加入できる人と掛金の月額上限
iDeCoの掛け金上限額や加入資格について確認します。
上限額や加入資格については、職業や他の年金を利用しているかによって異なります。
| 加入資格 | 掛金 | |
| 自営業者、無職、学生など (第1号被保険者) | 月額68,000円まで ※国民年金基金や国民年金付加保険料との合算した金額 | |
| 会社員・公務員 (第2号被保険者) | 企業年金がない会社員 | 月額23,000円まで |
| 企業型確定拠出年金に加入している場合 | 月額20,000円まで | |
| 確定給付企業年金、厚生年金基金と企業型確定拠出年金に加入している場合 | ||
| 確定給付企業年金、厚生年金基金に加入している場合 | ||
| 公務員など | ||
| 第2号被保険者の専業主婦(主夫) (第3号被保険者) | 月額23,000円まで | |
会社員:上限23,000円
| 加入区分 | 上限額 |
| 企業年金に加入していない会社員 | 23,000円 |
| 企業型DCのみに加入している会社員 | 20,000円 |
| DBと企業型DCに加入している会社員 | |
| DBのみに加入している会社員 |
会社員は、企業年金の加入状況によって上限額が変動します。
企業年金には、企業型確定拠出年金(企業型DC)とDB(確定給付企業年金・石炭工業年金基金・私立学校教職員共済)が含まれます。
公務員:2024年12月から上限が20,000円に
2024年12月から、DBに加入している会社員や公務員のiDeCoの拠出額の上限が20,000円に引き上げられます。
ただし、以下の掛金合計が上限55,000円であることに注意が必要です。
- iDeCoの掛金
- 企業型DCの事業主掛金額
- 確定給付型の他制度の掛金
つまり、「企業型DCの事業主掛金額」と「確定給付型の他制度の掛金相当額」の合計が35,000円を超える場合は、iDeCoの上限は20,000円以下となります。
出典:iDeCo公式サイト「iDeCo の拠出限度額の見直しに伴う iDeCo 掛金額変更の事前受付について」
個人事業主・フリーランス:上限68,000円
個人事業主・フリーランスや国民年金の任意加入被保険者の上限額は、68,000円です。
ただし、国民年金基金に加入している場合や、国民年金付加保険料を納付している場合は、iDeCoの上限額と合算して68,000円までとなります。
個人事業主や国民年金の任意加入被保険者には、厚生年金や企業年金などがない関係で、iDeCoの掛金上限が高く設定されています。
専業主婦(主夫):上限23,000円
専業主婦(主夫)の上限額は、23,000円です。
ただし、収入が一定額以下の場合は所得税や住民税を納めていないため、iDeCo税制優遇のうち「掛金控除」の恩恵が受けられない点には注意しましょう。
とはいえ、「運用益非課税」「受取時の控除」の恩恵は受けられるため、60歳まで引き出せないデメリットと合わせて利用を検討してください。
iDeCoの節税メリット

iDeCoは以下のような節税メリットがあります。
- 掛け金を積み立てた時
- 運用益が出た時
- 積み立てたお金を受け取る時
それぞれについて、詳しく確認していきましょう。
掛け金を積み立てた時
iDeCoで積み立てた掛け金は、全額が所得控除になります。
会社から毎月受け取る給料には「所得税」と「住民税」という税金がかかります。
iDeCoを利用することで所得税と住民税をある程度軽減することができます。
節税額については、年収や掛け金によって異なります。
詳しく知りたい方は自分がどのくらい節税できるか、シミュレーションサイトで計算してみることをおすすめします。
金融商品の運用益が出た時
株や投資信託などの金融商品の運用で利益が出た場合は、通常20.315%の税率で源泉徴収されます。
例えば10,000円の運用益が出た場合、2,031円の税金が源泉徴収されます。
しかし、iDeCoの場合運用益は非課税になります。iDeCoを運用して10,000円の運用益が出た場合には、2,031円の節税になるということです。
しかし、運用益はすぐにはもらえません。
運用益は掛け金と一緒に再投資され、給付金として60歳以降にもらえるという点に注意しましょう。
積み立てたお金を受け取る時
iDeCoは一時金として受け取る場合と年金として受け取る場合と2種類の受取方法が選択できます。
積み立てたお金の受取方法によって、さまざまな節税効果があります。
一時金として受け取る場合には、退職金などと合算して「退職所得控除」の対象になります。
退職所得控除の場合は、勤続年数に応じて下表のような非課税枠があります。
| 勤続年数 | 退職所得控除 |
| 20年以下 | 40万円×勤続年数 |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
勤続年数に応じて大きな節税効果になるというメリットがあります。
iDeCoを年金として受け取る場合には、他の年金と合算して、公的年金等の控除が受けられます。
公的年金等の控除額は年金収入額によって異なります。
65歳未満の場合は最低でも60万円、65歳以上の場合は最低でも110万円は非課税枠が保証されています。
一時金で受け取る場合も年金で受け取る場合も、他の所得と合算されて控除されます。
iDeCoの節税シミュレーション

それでは、実際にiDeCoのシミュレーションをしてみましょう。
今回は以下のケースで想定してみます。
- 30歳の会社員
- 年収500万円
- 掛け金23,000円を30年間運用
- 運用益100万円
この場合、所得税・住民税の軽減額は、30年間で165.6万円になります。
1年あたりで換算すると55,200円です。
運用益についても非課税なので、受取時に203,150円の節税になります。
上記のシミュレーションを見ただけでも、iDeCoの節税効果が高いことがわかります。
iDeCo(イデコ)を始める際の注意点・リスク

原則60歳まではお金を受け取れない
iDeCoは、原則60歳になるまで資金を引き出せません。
運用している資金は、老後資金以外で使えない点に注意する必要があります。
無理に掛金を増やす必要はないため、家計の負担にならない金額から運用しましょう。
様々な手数料がかかる
iDeCoを運用する際には、さまざまな手数料がかかります。
加入・移換時手数料は、iDeCoの新たな加入者や企業型確定拠出年金からの移換者が初回のみ負担する手数料です。
加入者手数料は、掛金を拠出するたびに負担する手数料で、毎月拠出する場合は年間1,260円がかかります。
還付手数料は、国民年金の未納月が発生した場合や限度額を超えて拠出した場合など、加入者に掛金が還付される際に発生する手数料です。
上記に加えて、「口座管理手数料」と「信託報酬」も発生します。
仮に毎月数百円程度の手数料でも、数十年単位で運用する場合は手数料だけでも数万円超えてくることもあります。
少しでも手元に多くの利益を残すために「どのくらいの手数料が発生するか」を意識しましょう。
運用商品によっては元本割れリスクがある
iDeCoを投資信託で運用する場合、元本割れのリスクがあります。
iDeCoで運用できる投資信託は、長期・積立・分散投資ができる商品であり、長期投資が可能な方であれば元本割れのリスクは少ないと言われています。
ただ、未来のことは誰にもわかりません。
元本割れが発生する可能性もあるということを留意しておきましょう。
掛金変更は1年に1回しかできない
iDeCoの掛金は、1年に1回だけ変更できます。
掛金を増額する場合も減額する場合も1年に1回しか変更ができません。
積立NISAのように、比較的自由に掛金を変更することはできないため注意しましょう。
まとめ:iDeCo(イデコ)は注意点を把握してから利用しよう
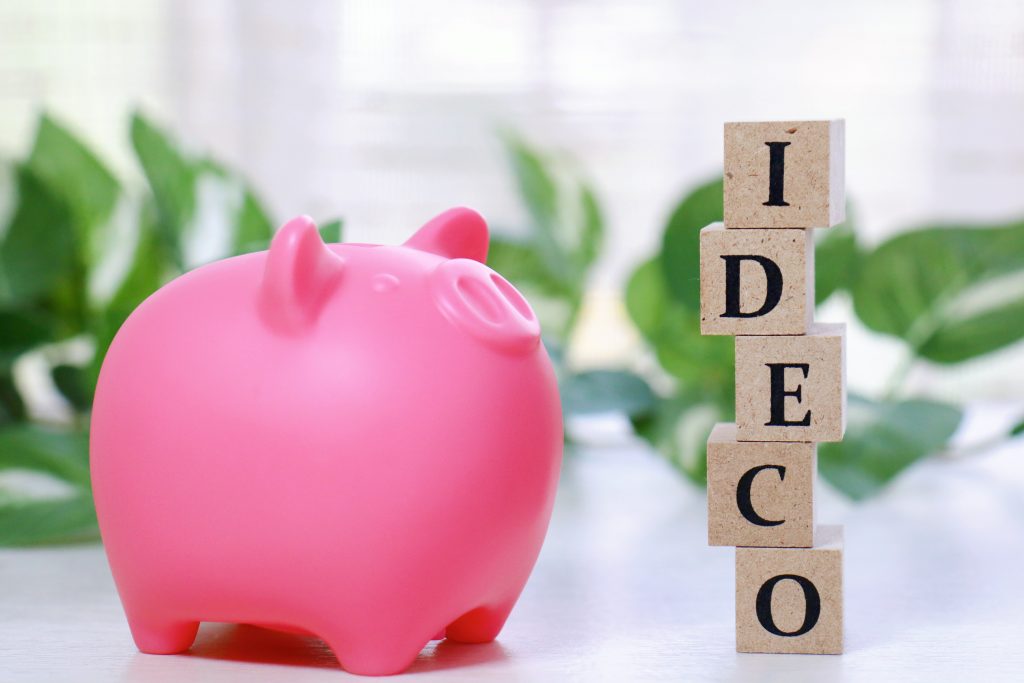
iDeCoは個人で運用する年金制度で、毎月一定額を積み立てて運用します。
公的年金との違いは、将来受け取れる金額が個人の運用成績次第で変わるということです。
途中で解約できず原則60歳まで資金を引き出せない点や、運用方法によって元本割れの可能性があるという点をしっかり理解した上で運用を検討しましょう
iDeCoの税制優遇には大きな魅力があるため、無理なく運用できればお得に老後資金を形成できます。
掛金が負担となり家計を圧迫しないよう、無理のない金額での運用をシミュレーションしてみましょう。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎








