年収650万円の手取りは?勝ち組なの?その生活レベルとできること・できないこと

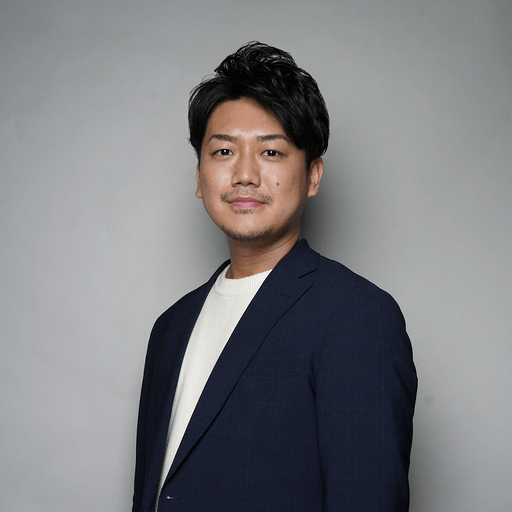
年収650万円は、一般的には高い水準の収入であるイメージがありますが、実際に得られる手取り収入はどれくらいなのでしょうか。
実際の手取り額を把握するには、税金や社会保険料を考慮する必要があります。
手取り収入がどの程度になるかを理解し、生活レベルや支出をイメージすることが重要です。
この記事では、年収650万円の手取り額や生活レベル、おすすめの税金対策や資産運用の方法を紹介しています。
年収650万円を目指すためのステップアップ法や賢い節約術なども紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎
この記事の目次
年収650万円の手取り額は年間約499万円(月に約41万円)

年収650万円の手取り額は約499万円となります。
額面収入から差し引かれる金額は以下の表の通りです。
| 項目 | 金額 |
| 所得税 | 240,700円 |
| 住民税 | 334,100円 |
| 厚生年金保険料 | 581,940円 |
| 健康保険料 | 317,364円 |
| 雇用保険料 | 39,000円 |
| 合計 | 1,513,104円 |
年収650万円の場合、およそ150万円が税金・社会保険料で引かれることになります。
ただし、家族構成や住宅ローン契約の有無、生命保険の加入状況等によって手取り額は異なるため、上記の金額はあくまで参考程度に把握しておきましょう。
<参照>年収別の手取り一覧表
次に、年収別の手取り額を一覧表で紹介します。
細かい手取り額は配偶者の有無や扶養家族の人数などによって違いがあるため、ここでは以下の条件をもとに表を作成しています。
- 企業に勤める会社員で所得は給与所得のみ
- 独身で扶養する子供はなし
- 控除は「給与所得控除」「社会保険料控除」「基礎控除」のみを考慮
上記の条件をもとにした手取り一覧表は以下の通りです。
| 額面年収 | 手取り(年額) | 手取り(月額) |
| 年収100万円 | 約83万円 | 約7万円 |
| 年収300万円 | 約236万円 | 約20万円 |
| 年収500万円 | 約387万円 | 約32万円 |
| 年収700万円 | 約524万円 | 約43万円 |
| 年収1,000万円 | 約722万円 | 約60万円 |
| 年収1,500万円 | 約1,017万円 | 約85万円 |
| 年収2,000万円 | 約1,292万円 | 約108万円 |
上記の手取り一覧表を参考に年収ごとの手取り額をイメージし、年収650万円の手取りがどの程度の水準なのかを把握しましょう。
【2025】年収別の手取り金額を一覧表で紹介!計算や節税方法を解説
年収650万円は「勝ち組」か?そのすごさを解説

国税庁による「令和5年分民間給与実態統計調査」によると、給与所得者の平均給与は460万円でした。
平均的な給与水準と比較すると、年収650万円は比較的高年収の部類に入ると言えるでしょう。
また、男女別の年収分布は以下の表の通りです。
| 年収区分 | 男性 | 女性 |
| 100万円以下 | 3.6% | 14.1% |
| 100万円超200万円以下 | 6.0% | 20.5% |
| 200万円超300万円以下 | 9.7% | 19.6% |
| 300万円超400万円以下 | 14.9% | 18.1% |
| 400万円超500万円以下 | 17.5% | 12.7% |
| 500万円超600万円以下 | 14.0% | 6.7% |
| 600万円超700万円以下 | 10.0% | 3.4% |
| 700万円超800万円以下 | 7.2% | 1.9% |
| 800万円超900万円以下 | 4.9% | 1.0% |
| 900万円超1,000万円以下 | 3.6% | 0.7% |
| 1,000万円超1,500万円以下 | 6.3% | 1.0% |
| 1,500万円超2,000万円以下 | 1.4% | 0.2% |
| 2,000万円超2,500万円以下 | 0.4% | 0.1% |
| 2,500万円超 | 0.5% | 0.1% |
上記の表から単純計算すると、年収650万円は男性で上位30%ほど、女性で上位8%ほどの水準であると考えられます。
一般的な水準と比べて年収650万円は高い年収だと言えるでしょう。
年収650万円の生活レベルを徹底比較【シミュレーション】

次に、年収650万円(手取り約41万円)の人の生活レベルを4つのパターンに分けててシミュレーションします。
年収650万円の暮らしをイメージしてみましょう。
実家暮らし・独身の場合
実家暮らしで独身での場合、基本的に家賃や住宅ローンの支払いが不要となり、生活費も家族と分け合うため月々の負担はかなり抑えられます。
具体的には以下のような生活費の内訳となります。
| 項目 | 金額 |
| 家賃 | なし |
| 光熱費 | 5,000円 |
| 通信費 | 10,000円 |
| 食費 | 40,000円 |
| 交通費 | 10,000円 |
| 保険料 | 15,000円 |
| 娯楽・趣味・交際費 | 100,000円 |
| 貯蓄・投資 | 210,000円 |
| その他(雑費・日用品など) | 20,000円 |
生活費の負担を大きく抑えられる分、娯楽や趣味に使うお金や、貯蓄・投資に回すお金が充実しています。
実家暮らしの独身の方にとっては、年収650万円はかなり余裕を持った生活を送れる水準となるでしょう。
一人暮らし・独身の場合
一人暮らしをしている独身の場合も、年収650円あればある程度余裕を持った生活を送れそうです。
具体的には以下のような生活費の内訳となります。
| 項目 | 金額 |
| 家賃 | 80,000円 |
| 光熱費 | 10,000円 |
| 通信費 | 10,000円 |
| 食費 | 50,000円 |
| 交通費 | 10,000円 |
| 保険料 | 15,000円 |
| 娯楽・趣味・交際費 | 60,000円 |
| 貯蓄・投資 | 150,000円 |
| その他(雑費・日用品など) | 25,000円 |
支出の大きな部分を占めるのが家賃となるため、物件を慎重に見極める必要は出てきます。
将来を見据えて貯蓄や投資を継続し、資産形成を行っていくことが大切です。
しかし、趣味や娯楽にもある程度お金を回せる水準であり、よほどの浪費をしなければ苦しい生活になる可能性は低いでしょう。
配偶者あり・子どもなしの場合
配偶者がいて子どもがいない夫婦2人暮らし場合、共働きでなくても生活を送っていくことは可能です。
具体的には以下のような生活費の内訳となります。
| 項目 | 金額 |
| 家賃 | 100,000円 |
| 光熱費 | 15,000円 |
| 通信費 | 12,000円 |
| 食費 | 80,000円 |
| 交通費 | 15,000円 |
| 保険料 | 20,000円 |
| 娯楽・趣味・交際費 | 50,000円 |
| 貯蓄・投資 | 83,000円 |
| その他(雑費・日用品など) | 35,000円 |
一人暮らしよりも家賃や光熱費、食費などの負担が大きくなるため、支出のやりくりを工夫する必要は出てきます。
夫婦二人で問題なく生活はしていけそうですが、無駄遣いを極力減らすような努力が必要です。
配偶者あり・子どもありの場合
配偶者と子どもがいるパターンの場合、しっかりと家計管理を行っていく必要があります。
具体的には以下のような生活費の内訳となります。
| 項目 | 金額 |
| 家賃 | 120,000円 |
| 光熱費 | 20,000円 |
| 通信費 | 12,000円 |
| 食費 | 100,000円 |
| 交通費 | 20,000円 |
| 保険料 | 25,000円 |
| 娯楽・趣味・交際費 | 30,000円 |
| 貯蓄・投資 | 43,000円 |
| その他(雑費・日用品など) | 40,000円 |
子どもの年齢によっては上記費用に加えて教育費などもかかってくるため、家計の管理を徹底した上で無駄な支出を減らすことが重要です。
生活を送っていくことは可能ですが、やりくりの工夫が必要となるでしょう。
年収650万円の住宅ローンと家賃の目安

年収650万円の人が住宅ローンを組む場合、月々の返済額をいくらに設定すべきなのでしょうか。また賃貸住宅に居住する場合、どの程度の家賃の部屋を選べば良いのでしょうか。
ここでは、年収650万円の住宅ローンと家賃の目安を紹介します。
住宅ローンの目安は3,250万円から4,550万円
一般的に住宅ローンの借入額は「年収の5〜7倍」の金額が目安と言われています。
年収650万円の場合、単純計算で3,250万円〜4,550万円が目安です。
上記の借入額で35年ローンを組むと仮定した場合、月々の返済額は9万円〜13万円程度(利率やボーナス返済の有無による)になります。
手取り収入が月41万円ほどある考えると、返済していける水準と言えるでしょう。
家賃の目安は10万円から12万円
一般的に家賃は「手取りの25%〜30%以内に抑えるべき」と言われています。
年収650万円の手取り額は月に約41万円となるため、単純計算で102,500円〜123,000円ほどの金額設定が適切でしょう。

家賃の目安は手取りの何割?家賃別の生活費や東京の一人暮らし相場も紹介
マイホームやマイカーを持てる?年収650万円でできること・できないこと

年収650万円の人は、マイホームやマイカーを購入できるのでしょうか。
ここでは、年収650万円の人のマイホーム・マイカーの購入や子どもの教育費について解説します。
マイホーム
年収650万円であれば、基本的に住宅ローンを組んでマイホームを購入可能です。
前述の通り、住宅ローンは「年収の5〜7倍」の借入額が目安とされているため、約3,250万円〜4,550万円を借り入れてマイホームを購入できます。
ただし、不動産価格が高騰している都心部で戸建てを購入したり、高級なマンションを購入したりすることは難しい可能性があります。
物件は慎重に選び、無理なく返済できる範囲で住宅ローンを契約しましょう。
マイカー
年収650万円の方は、ローンを利用してマイカーを購入可能です。
貯蓄の状況によっては中価格帯の車を一括で購入することも不可能ではありません。
中古車であれば、家計を圧迫することも少ないためおすすめです。
ただし、高級車やスポーツカーなど高額な車を購入することは難しい場合もあるでしょう。
生活費や貯蓄状況に支障をきたさない範囲で購入できる車を探すことが重要です。
教育費
年収650万円であれば、子どもの教育費も十分に捻出できます。
公立の学校に通うための費用はもちろん、学習塾や習い事に通わせることも十分に可能です。
しかし、学費が高額になる私立学校や授業料が比較的高い学習塾などは家計に負担がかかる可能性があります。
また貯蓄状況によっては、海外留学などでまとまった教育費がかかると難しい場合もあります。
教育費の負担が重くなる場合は、奨学金や学資保険などの制度の活用を検討しましょう。
年収650万円のための賢い節約術

年収650万円の人は家族構成や生活スタイルによっては、節約が必要となる場合もあります。
ここでは、年収650万円の人のための賢い節約術を紹介します。
家計簿で支出の管理
家計簿をつけて収入と支出を管理することが節約の第一歩となります。
どこにお金が使われているのかを把握することで、無駄な支出を防げるようになるためです。
家計簿アプリなどを活用して家計管理を行い、支出の傾向を捉えましょう。
収入・支出を把握できたら、月々の予算を設定していきます。
予算の範囲内に収めるようにお金の使い道を考え、節約すべきポイントを意識しましょう。

【2025】資産管理アプリのおすすめ8選!無料のアプリや選ぶ際のポイントも解説
固定費の見直し
節約をする際に重要となるのが、毎月かかる「固定費」を見直すことです。
毎月の支出の大半を占める住居費や光熱費、通信費、保険料などを見直すことで支出を大幅に改善できます。
特に通信費や保険料などはよく分からないまま契約してしまい、余分なプランが付帯しているというケースも少なくありません。
一度見直しを行い、最適なプランに乗り換えて無駄な固定費を削減しましょう。

固定費7項目を節約・削減する方法一覧!節約のためのポイントも紹介!
クレジットカードの活用
日々の支払いをクレジットカードにまとめることで、ポイント還元を受けられます。
高還元率のカードを選べば効率良くポイントが貯まっていき、貯まったポイントは買い物等に充当できます。
また、クレジットカードには旅行保険や空港ラウンジの利用、提携店舗での優待などの特典が付帯しているケースが多いです。
クレジットカードの特典を効果的に活用し、よりお得に生活することで無駄な支出を減らせる可能性もあります。

公共料金はクレジットカードで払える!おすすめの選び方を解説
年収650万円を目指すためのステップアップ法

次に、年収650万円を目指すための4つの方法を紹介します。
自分に合った方法で年収アップを目指しましょう。
転職する
現在の勤め先で年収650万円に到達することが難しい場合、より高い給与を提示してくれる企業に転職することをおすすめします。
スキル・経験を活かして外資系企業や成長企業、IT・金融などの給与水準が高い企業に転職し、年収650万円以上を目指していくと良いでしょう。
転職活動の際には、自己分析を行って自身の強みやスキルを活かせる企業を探すことが重要となります。
転職エージェントなどのサービスを活用し、自分の市場価値を理解した上で転職活動を進めましょう。
昇進する
現在の勤め先で昇進や昇給を目指すのも年収アップを狙う方法のひとつです。
特に、管理職やリーダーなどのポジションに就ければ年収650万円に近づくことが期待できます。
昇進を目指す際には、必要なスキルや資格の取得が近道となります。
また、日々の仕事で成果を出しつつ、リーダーシップを発揮することもポイントとなるでしょう。
副業を始める
副業を始めて本業以外の収入源を確保する方法もおすすめです。
自身のスキルを活かした副業を始めることで、高い収入を得るチャンスが広がります。
クラウドソーシングサイトなどで自身のスキルを活かせる仕事を受注し、効率的に収入を得ていきましょう。
時間管理をしっかりと行い、本業に支障をきたさない範囲で副業を始めてみると良いでしょう。

【2025年版】安全でおすすめの厳選副業20選!女性向けなど立場別で紹介
投資する
投資をして資産収入の増加を目指し、年収を増やす方法もあります。
株式や不動産などに投資をしたり、NISAやiDeCoのような税制面での優遇を受けられる制度をうまく活用したりすることで、長期的に資産を増やすことが期待できます。
ただし、投資は資産が減少するリスクも伴うため、自身での勉強やプロへの相談などで知識を身に付けリスク対策をすることも重要です。
長期視点でじっくり資産を増やしていく意識を持ち、無理なく投資を継続していきましょう。

【初心者向け】女性が投資を始めるには?おすすめの方法を解説!
年収650万円の人におすすめの税金対策

前述の通り、年収650万円の場合はおよそ150万円の税金や社会保険料が引かれます。
適切な税金対策を実践し、税負担を軽減して手取りを増やしていく取り組みが重要です。
ここでは、年収650万円の方におすすめの税金対策を解説します。
ふるさと納税による節税
ふるさと納税は、地方自治体に寄付をして地域の特産品などの返礼品を受け取る制度のことです。
寄付金のうち2,000円を超える部分が所得税や住民税から控除・還付されるため、税負担を軽減することができます。
また、実質的な自己負担額2,000円でお得な返礼品を受け取れる点もメリットです。
ふるさと納税は、自身が居住している自治体以外であればどこにでも寄付を行えます。
「生まれ育った自治体に寄付をする」「欲しい返礼品を提供している自治体を選ぶ」など、好きな自治体に寄付をすると良いでしょう。

年収1,000万円のふるさと納税限度額は?メリットや返礼品の選び方も紹介
iDeCoやNISAによる節税
本来、株式や投資信託などで得た利益に対しては20.315%の税金が発生します。
しかし、iDeCoやNISAといった税制優遇制度を使うことで投資の利益にかかる税金を軽減可能です。
iDeCoは、自分で掛金の拠出や運用を行い、老後になってからその運用成果を受け取る仕組みの年金制度です。
拠出した掛け金は全額所得控除となるため、所得税や住民税の負担を軽減できます。
さらには運用益が非課税で再投資されるため、効率的に資産を増やしていける点が魅力です。
NISAは、年間最大360万円までの投資で得た利益が非課税となる制度のことです。
株式や投資信託で得られるリターンを非課税で享受できるため、効率の良い資産運が目指せます。iDeCoやNISAで資産形成をしつつ、税負担も軽減させていきましょう。

【2025】NISAとiDeCoはどっちから始める?併用できるかや違いを解説
年収650万円の人におすすめの資産運用方法

将来の金銭的な不安を解消するためにも、適切な手法で資産運用を行っていくことが大切です。
ここでは、年収650万円の人におすすめの資産運用の方法を紹介します。
投資信託
投資信託は、投資家から資金を集めてプロが運用を代行し、収益を投資家に分配する仕組みの金融商品です。
集めた資金は複数の株式や債券で運用されるため、1つの商品を購入するだけで分散効果を得られることが特徴となっています。
プロに運用を任せられる分、知識に自信がない投資初心者の方でも利用しやすい商品です。
投資先が分散されていることからリターンの安定性も高く、リスクを抑えた運用が期待できる点も魅力です。
手間をあまりかけず、リスクを抑えた運用をしたい方には投資信託をおすすめします。
REIT(不動産投資信託)
REITは、投資家から集めた資金で不動産に投資を行い、収益を投資家に分配する仕組みの金融商品です。
不動産の投資信託というイメージの商品であり、居住用の不動産や商業施設、オフィスビルなどに投資を行っています。
通常、不動産物件の購入には数百万円から数千万円の資金が必要となり、銀行からの融資を利用するケースも少なくありません。
いきなりローンを組んで高額な不動産物件を購入するのは投資初心者にとってハードルが高いと感じる人もいるでしょう。
REITであれば数万円から購入でき、仕組み上複数の物件に分散投資を行えるため、不動産投資を始めたい投資初心者の方におすすめです。
まとめ:年収650万円の手取りや生活レベルの理解を深めましょう

年収650万円の人は税金や社会保険料でおよそ150万円引かれ、手取りは約499万円となります。
手取り収入を増やすためにも、効果的な税金対策を実践することが大切です。
本記事でご紹介したもの以外にも税金対策の方法はあるため、正しい知識を身につけて実践していくことが大切です。
ぜひこの機会にオンラインの「税金対策セミナー」に参加し、自分にぴったりの税金対策の方法を学んでみましょう。









