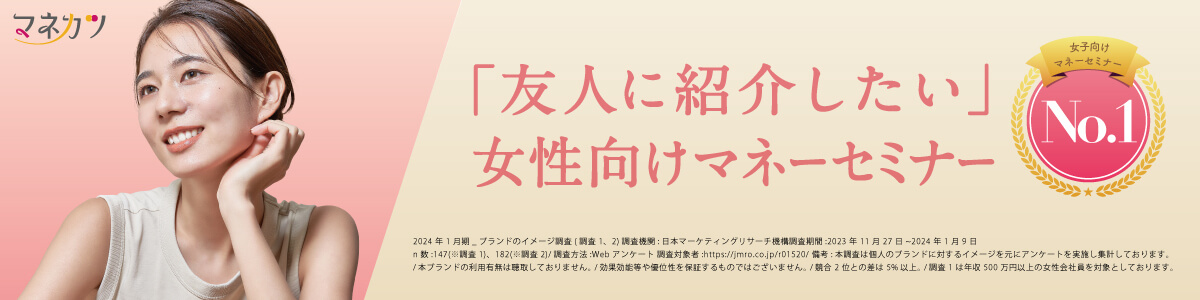【2024】配偶者控除とは?配偶者特別控除との違いや計算シミュレーションを紹介

毎年11月頃に会社に提出する年末調整書類の中で、「配偶者控除」という言葉を目にしたことがある方もいるかもしれません。
配偶者控除とは、配偶者の収入が一定金額以下の場合に納税者本人の所得税が軽くなる制度のことです。
この記事では、配偶者控除の内容や控除額の計算方法についてわかりやすく解説します。
配偶者控除は所得税の軽減効果が大きいため、申告漏れに注意しましょう。
\現在開催中の無料セミナーはこちら/
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】
オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎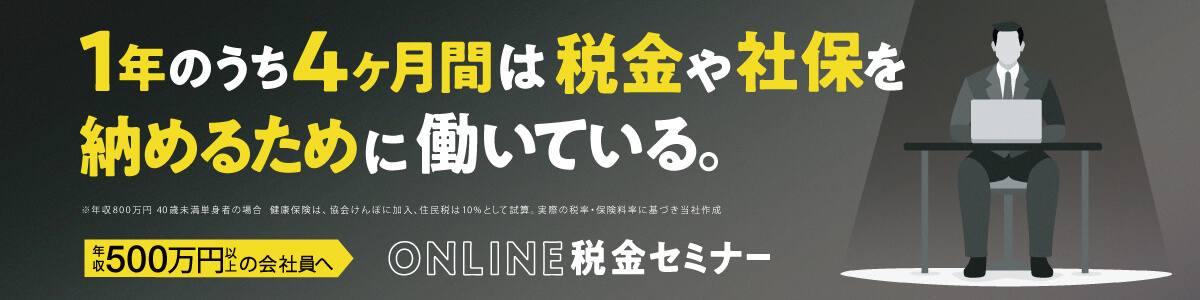
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?
人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎
この記事の目次
配偶者控除とは

「配偶者控除」とは、所得税や住民税を計算するときに使える「所得控除」の1つです。
所得税は、所得から所得控除を差し引いた「課税所得」に税率を掛けて計算します。
- 課税所得 = 所得 – 所得控除
- 所得税 = 課税所得 × 税率
たとえば給与所得が300万円、所得控除が50万円ならば、課税所得は250万円です。
所得控除額が大きいほど課税所得は減るため、税金が安くなります。
配偶者の所得金額が一定以下ならば、納税者が所得控除を受けられます。
夫が会社員で妻が専業主婦の場合、夫の所得から一定額が控除され、税金が安くなる仕組みです。
配偶者控除の対象になる条件
配偶者控除の対象になるのは、次の条件を満たす人です。
- 納税者の配偶者であること
- 納税者と生計が同じであること
- 年間所得が48万円以下であること など
年間所得とは、その年の1月1日から12月31日までの所得です。
配偶者の給与収入が103万円までなら給与所得控除(55万円)が受けられるため、所得が103万円 – 55万円 = 48万円となり上記の条件を満たします。
パートで働く主婦などが「103万円の壁」を意識して給与を抑えようとする主な理由は、配偶者控除の条件を満たし夫の所得税を軽くしようと考えるためです。
配偶者控除の金額【早見表】
配偶者控除の金額(以下、控除額)は、納税者の所得と配偶者の年齢によって異なります。
控除額は次の通りです。
なお、配偶者の年齢はその年の12月31日時点で判断します。
| 納税者の所得 | 控除額 | |
| 配偶者70歳未満 | 配偶者70歳以上 | |
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
夫が会社員で妻が専業主婦の場合、夫の所得が大きいほど控除額は少なくなり、1,000万円を超えると所得控除は受けられません。
70歳以上の配偶者のことを「老人控除対象配偶者」と呼び、70歳未満の人と比べて控除額は高くなります。
配偶者控除と配偶者特別控除の違い

配偶者の所得条件「年間所得が48万円以下であること」を満たさない場合でも、配偶者の所得が一定額以下ならば、「配偶者特別控除」を受けられます。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違いについて解説します。
配偶者控除の対象にならない場合に段階的に適応される
配偶者の年間所得が48万円を超えると、所得控除が一切受けられなくなるわけではありません。
配偶者の所得が増えるごとに控除額が段階的に小さくなり、配偶者の所得が133万円を超えると所得控除が受けられなくなります。
所得控除の名称は、配偶者の所得が48万円以下のときが「配偶者控除」、48万円超133万円以下のときが「配偶者特別控除」です。
また、配偶者控除と配偶者特別控除では、控除額も異なります。
配偶者特別控除を受けられる条件
配偶者特別控除の対象になる配偶者とは、次の条件を満たす人です。
- 納税者の配偶者であること
- 納税者と生計が同じであること
- 年間所得が48万円超133万円以下であること
- 配偶者特別控除を使っていないこと など
配偶者控除と同様、納税者の年間所得が1,000万円を超えると配偶者特別控除は受けられません。
配偶者特別控除の金額【早見表】
配偶者特別控除の金額は、納税者本人と配偶者それぞれの合計所得によって異なります。
控除額は次の通りです。
| 配偶者の年間所得 | 納税者の年間所得 | ||
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | |
| 48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者が70歳未満で年間所得が「48万円超95万円以下」の場合、配偶者特別控除は配偶者控除と同額です。
たとえば納税者本人の年間所得が950万円超1,000万円以下、配偶者の年間所得が130万円超133万円以下の場合、控除額は最小値の1万円となります。
配偶者控除額の計算シミュレーションと考え方

配偶者控除や配偶者特別控除の金額は、夫婦の年間所得や配偶者の年齢などによって異なります。
実際にいくらくらいの配偶者控除が受けられるか、モデルケースを使ってシミュレーションしましょう。
夫婦とも70歳未満で、収入は給与のみとします。
「年収(給与収入)」から「給与所得控除」を差し引いた金額が「年間所得」です。
年収162万5,000円までは給与所得控除額は55万円、それ以上になると控除額は年収に応じて増加し、上限は195万円です。
納税者の年収:700万円、配偶者の年収:95万円
納税者の年間所得は520万円(給与所得控除180万円)、配偶者が40万円(給与所得控控除55万円)です。
「納税者の年間所得1,000万円以下」「配偶者の年間所得が48万円以下」の条件を満たすため、配偶者控除が適用されます。
先に紹介した「配偶者控除額の早見表」より、配偶者控除額は38万円です。
配偶者控除38万円が適用されるのは、年収ベースでみると納税者が1,095万円以下、配偶者103万円以下の場合です。
納税者の年収:1,100万円、配偶者の年収:180万円
納税者の年間所得は905万円(給与所得控除195万円)、配偶者が125万円(給与所得控除55万円)です。
配偶者の年間所得が48万円を超えるため配偶者控除は適用されませんが、配偶者特別控除が使える範囲内です。
「配偶者特別控除額の早見表」に夫婦の年間所得を当てはめると、配偶者特別控除額は8万円になります。
配偶者特別控除が使える配偶者の年収は、103万円超201万円以下です。
納税者本人の年収が1,195万円を超える場合
納税者の年間所得は1,000万円(給与所得控除195万円)を超えるため、配偶者控除も配偶者特別控除も使えません。
納税者の年収が1,095万円を超えると1,145万円以内、1,195万円以内と控除額が徐々に減額され、1,195万円を超えると配偶者控除が適用されなくなります。
参考: 水戸市「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(市民税課)」
配偶者の年収が201万円を超えそうな場合
配偶者特別控除が受けられる配偶者の年間所得は、「48万円超133万円以下」の範囲内です。
年間所得133万円は年収ベースで201万6,000円で、これを超えると配偶者特別控除は受けられません。
配偶者の年収が201万円前後の場合、控除額は最大でも3万円とあまり大きくはありません。
控除を受けるために給与を抑えて働く人もいますが、しっかり稼いで夫婦の手取りをアップさせる方が効果的であると考えられます。
育休中や共働きでも控除は受けられる
配偶者が「出産手当金」や「育児休業給付金」を受け取っている場合でも、配偶者控除・配偶者特別控除の条件を満たしていれば、所得控除が受けられます。
受け取った出産手当金や育児休業給付金は「非課税」であるため、配偶者の所得には含まれません。
また、夫婦とも会社員で共働きの場合でも、条件を満たせば所得控除を受けられます。
配偶者の年収によって現れる「◯◯◯万円の壁」とは?

会社員の配偶者がパートやアルバイトなどで働くとき、年収の目安としてよく使われるのが「◯◯◯万円の壁」です。
◯◯◯万円は、その金額を超えると税金や社会保険などに影響する節目の年収を表しています。
それぞれの「◯◯◯万円の壁」について確認していきましょう。
年収100万円の壁:住民税が発生
「年収100万円の壁」とは、「住民税」がかかる境界となる年収です。
パートやアルバイトでも、年収が100万円を超えると住民税がかかります。
住民税には「所得割」と「均等割」の2種類がありますが、年収100万年を超えるとかかるのは所得割です。
- 所得割:所得金額に応じてかかる地方税。税率は10%。
- 均等割:所得がある人全員(免除制度あり)にかかる地方税。税額は全国一律5,000円。
住民税の課税を避けるために年収を100万円以内に抑える人もいるため、「年収100万円の壁」といわれます。
年収103万円の壁:所得税が発生、配偶者控除
「年収103万円の壁」は、配偶者控除が適用される配偶者の年収の上限額です。
「所得税」の境目となる年収でもあります。
給与所得者の所得税を計算するときは、年収から「給与所得控除」と「基礎控除」を差し引いて所得税率を掛けます。
年収162万5,000円までは給与所得控除額が55万円、基礎控除は一律48万円です。
控除額の合計は103万円であるため、年収103万円までは所得税がかかりません。
配偶者の年収を103万円以内に抑えると、所得税がかからないうえに、配偶者控除が適応されます。

所得税はいくらから引かれる?103万の壁や所得税の計算方法を解説
年収106万円の壁:社会保険料が発生(条件付き)
「年収106万円の壁」は、社会保険料の境目となる年収です。
社会保険料には「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」の3つがあります。
40歳未満の人は、介護保険料がかかりません。
ただし、年収106万円以上で社会保険に加入するのは、次の条件を満たす会社員に限定されます。
- 勤務先が「従業員101人以上の会社」または「100人以下で社会保険加入について労使の合意がある会社」
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 2ヶ月を超えて雇用される予定である
- 学生ではない
国が推進する「社会保険料の適用拡大」によって、2022年10月より対象企業の従業員数が「501人以上」から「101人以上」になりました。
また、2024年10月には、「従業員数51人~100人未満の企業」も対象になります。
参考:厚生労働省「平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています!(社会保険の適用拡大)」
参考:厚生労働省「従業員数500人以下の事業主のみなさま」
年収130万円の壁:社会保険料が発生
上述した社会保険の加入条件を満たしていない場合でも、年収130万円を超えると勤務先の社会保険に加入しなければなりません。
自営業の場合は、国民年金や国民健康保険に加入します。
夫が会社員で妻がパートの場合、妻の年収が130万円以内なら、夫の扶養として健康保険料や年金保険料の支払いは必要ありませんが、年収130万円を超えると扶養から外れます。
社会保険料は給与の約15%で手取りの収入が減るため、100万円や103万円を超えたときより、大きな負担を感じるでしょう。
ただし、社会保険に加入すれば、休業時に給与補償があったり老齢厚生年金がもらえるなどのメリットもあります。
年収150万円の壁:配偶者控除
年収150万は、配偶者が70歳未満ならば、配偶者控除と同額の配偶者特別控除が受けられる年収の上限です。
夫の年収が900万以下で妻のパート収入が103万円を超えると配偶者控除は適用されませんが、150万円以内ならば、配偶者控除と同額(38万円)の配偶者特別控除が受けられます。
ただし、妻の年収が150万円を超えても、一定の配偶者特別控除は受けられます。
年収がアップするとともに控除額は減りますが、夫婦を合わせた手取り収入が減るわけではありません。
控除額はあまり気にせずに、どんどん収入アップを図るという選択肢もあります。
年収201万6,000円の壁:配偶者特別控除の上限
配偶者の年収が201万円を超えると年間所得は133万円を超えるため、配偶者特別控除を受けられません。
先に解説した通り、配偶者の年収が201万円前後の場合、控除額は最大でも3万円ほどです。
所得控除は気にせずしっかり稼ぐ方が、世帯収入を上げるには効果的でしょう。
「◯◯◯万円の壁」による収入や税金などへの影響は、人によって異なります。
しかし、壁に拘って仕事を抑えていると、自分の可能性を狭めたり社会で活躍するチャンスを逃したりする可能性もあることも覚えておきましょう。
配偶者控除・配偶者特別控除の手続き方法

最後に、配偶者控除や配偶者特別控除の手続き方法について簡単に解説します。
年末調整の手続き方法
会社員の場合、「年末調整」によって所得控除の申告を行います。
申告を行うのは、配偶者側ではなく所得控除を受ける納税者側です。
申告に使うのは、会社から配布される「給与所得者の配偶者控除等申告書」です。主な記載内容は、次の通りです。
- 納税者本人の年間所得
- 配偶者の氏名・マイナンバー・住所・生年月日
- 配偶者の年間所得 など
申告書は、その他の年末調整書類と同時に会社に提出します。
税務署への申告は会社がしてくれるため、会社に書類を提出すれば年末調整は完了です。
参考:国税庁「[手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告」
確定申告の手続き方法
所得控除を受ける納税者が自営業や確定申告が必要な会社員の場合、「確定申告」によって所得控除の申告を行います。
この場合は自分で確定申告書類を入手して、必要事項を記入した上で税務署に届け出しなければなりません。
確定申告書類の中に配偶者控除などの申告欄があるので、年末調整とほぼ同じ内容を記載します。
書類の提出は税務署の窓口に行くほか、郵送やインターネットを利用した電子申請も可能です。

会社員でも確定申告は必要?自分でするやり方やどのような人が必要か解説
まとめ:配偶者控除とは何か理解して負担を抑えよう

配偶者控除は、配偶者が専業主婦(夫)やパートなどで収入が一定金額以下の場合、納税者本人の所得税が軽くなる制度のことです。
納税者の所得が1,000万円以下・配偶者が48円以下の場合に適用されます。
年収ベースで、納税者1,195万円以下・配偶者103万円以下と覚えたほうがわかりやすいかもしれません。
一般的には配偶者側が上限を超えないように工夫しながら収入を考えることが多くなります。
控除額が大きく一定の節税効果に期待できるため、上限額を超えたり申告漏れがないように注意しましょう。
\現在開催中の無料セミナーはこちら/
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】
オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎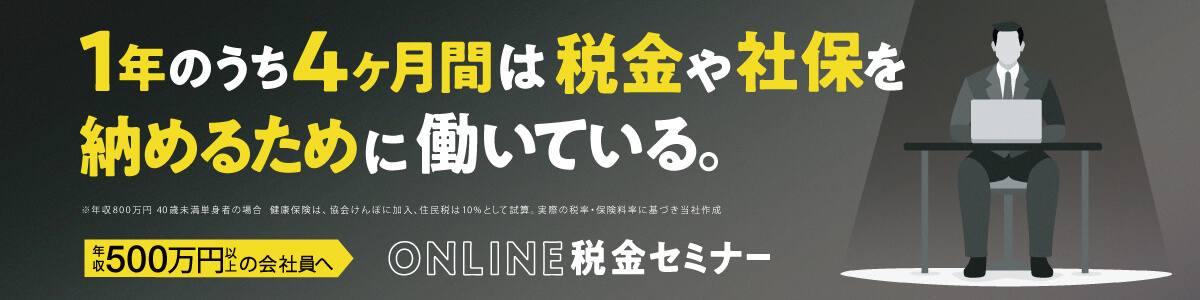
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?
人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎
| 税金の関連記事 | |
| 税金の使われ方 | 所得納税書の入手方法 |
| 雑所得とは | 所得税の計算方法 |
| 宝くじの税金 | 住民税の分割払い |
| 会社員にできる節税 | ボーナスの税金 |
| 転職後の住民税 | 配偶者控除について |
| 会社員の確定申告 | 退職時の税金 |

記事監修者
マネカツ編集部
"将来への漠然としたお⾦への不安はあるけど、何から始めていいのかわからない…"
そんな方に向けて「資産運用」や「節税」など、お金に関する情報を発信しています。

記事監修者
マネカツ編集部
"将来への漠然としたお⾦への不安はあるけど、何から始めていいのかわからない…"
そんな方に向けて「資産運用」や「節税」など、お金に関する情報を発信しています。