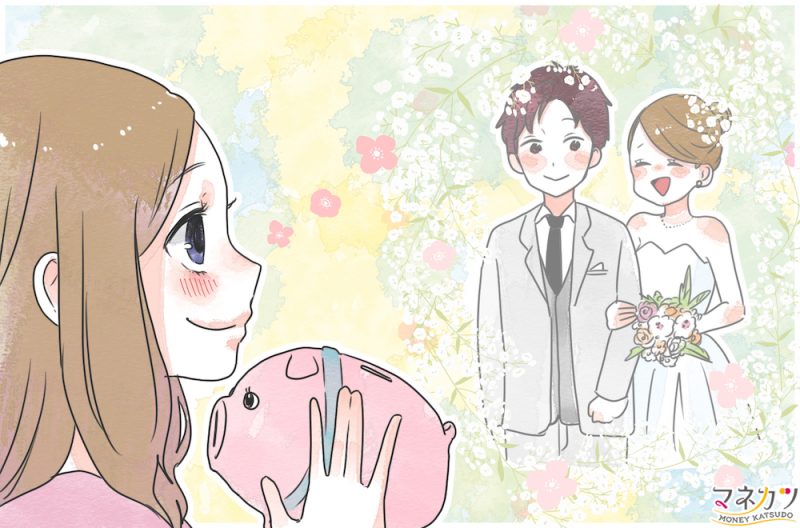定期預金が満期になったらどうする?引き出すのか継続するのか満期後に考えたいことを紹介


記事監修者
マネカツ編集部
"将来への漠然としたお⾦への不安はあるけど、何から始めていいのかわからない…"
そんな方に向けて「資産運用」や「税金対策」など、お金に関する情報を発信しています。

記事監修者
マネカツ編集部
"将来への漠然としたお⾦への不安はあるけど、何から始めていいのかわからない…"
そんな方に向けて「資産運用」や「税金対策」など、お金に関する情報を発信しています。
定期預金は、一定期間引き出せない代わりに普通預金よりも金利が高く設定されている預金方法です。
子どもの教育資金や車の買い替え費用など、使い道やタイミングが決まっているお金を定期預金に預けた場合は、満期を迎えた際にお金を引き出します。
一方で、使い道が決まっていない定期預金が満期になった場合は、どのように扱えばいいか悩む方もいるかもしれません。
この記事では、満期になった定期預金の扱いや、満期になったら考えたいことを紹介します。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎
この記事の目次
定期預金の仕組み

定期預金とは、一定期間お金を引き出さないことを条件に、普通預金よりもやや高い金利を受け取ることのできる預金サービスのことです。
定期預金も銀行の「ペイオフ」の対象となっており、普通預金の残高と合わせて金融機関ごとに1,000万円とその利息が、何かあった際にも保証されています。
元本が保証されるため、しばらく使う予定のないお金を定期預金に預けるのも資産運用の選択肢となるでしょう。
ただし、低金利の現在では、普通預金と定期預金の金利の差はあまりなく、お金を多く増やしたいと考えている人にはあまり向いていないといえます。
| 金利 | 100万円預けた際の利息 | |
| 普通預金 | 0.001% | 10円 |
| 定期預金 | 0.002% | 20円 |
※ゆうちょ銀行の2022年9月時点での金利で計算
※利息にかかる税金は考慮していません
定期預金が満期になったらどうする?

満期までの期間は数ヶ月~10年程
定期預金は、始める際に預入期間(満期までの期間)を設定します。
預入期間は金融機関によって異なりますが、数ヶ月〜10年の範囲内で設定できる金融機関が多いです。
メガバンクであれば期間を10年まで設定できますし、楽天銀行のようなネット銀行であれば預入期間を1週間に設定できる場合もあります。
定期預金の預入期間は短期から長期まで選択肢が豊富なため、自分のライフプランに合わせやすく使いやすいです。
参考:株式会社ゆうちょ銀行「定期貯金」
参考:楽天銀行株式会社「定期預金(1週間、2週間)」
定期預金の利息計算
定期預金は開始時の金利が満期まで適用されるため、満期までに受け取れる利息をあらかじめ計算できます。
通常、金融機関のホームページで表示される金利は「年利」といい、1年あたりの利息を意味する数字です。
そのため、1週間満期のように1年未満の定期預金の利息を計算する際は、年利をそのまま適用するのではなく、1週間に合わせて計算する必要があります。
例えば元本100万円を年利1%の1週間定期預金に預けた場合の金利は、以下のとおりです。
- 100万円 × 1% × 7/365 = 191円
同様に、金利が年利で表示されている場合は、1ヶ月であれば1ヶ月分の利息、3ヶ月であれば3ヶ月分の利息を受け取れます。
「自動解約」か「自動継続」を選ぶ
満期を迎えた定期預金は、以下のいずれかを選択することになります。
- 自動解約:普通預金口座に移す
- 自動継続:定期預金での運用を継続する
定期預金開始時に満期になったときの扱いを決めているため、特別な事情がなければ定期預金が満期を迎える際の手続きは必要ありません。
定期預金の開始時にどちらを選択したか忘れてしまった人は、銀行に確認しましょう。
自動解約
自動解約を選択すると、定期預金が満期を迎えた際に自動的に解約されます。
解約された定期預金の元本と利息は、定期預金の開始時に指定した普通預金口座に入金されます。
子どもの教育資金や住宅購入の頭金など、ライフプランからお金を使う時期を想定して定期預金する場合は「自動解約」の設定がおすすめです。
自動解約に設定しておくと、銀行に足を運んで解約の手続きをしたり、ネットバンキングサービスにログインして解約手続きをする手間が省けます。
自動継続
自動継続を設定すると、同一の預入期間・同一の利息支払方法で定期預金が継続されます。
注意点として、金利は継続日(満期日)の店頭表示金利が適用される点が挙げられます。
キャンペーンや株主優待サービスなどを使って、通常よりも高い金利で定期預金を開始した場合でも、満期を迎えて自動継続すると店頭表示金利が適用されるケースが一般的です。
開始時は「自動継続」にしたものの、後から「自動解約」に変更したい場合は、満期日に解約するように変更できる金融機関が多いようです。
ただし、変更の可否や手続きが可能な期間などは、金融機関によって異なります。
また、満期日が近づいたタイミングで事前に通知が届く金融機関もあるようです。
参考:株式会社みずほ銀行「定期預金の満期案内はいつ郵送されますか」
「自動継続」した場合の利息について
満期を迎えた定期預金で「自動継続」を選択した場合は、利息の扱いも設定します。
利息の扱いは「元利金継続(継続預入)」「元金継続(再預入)」から選択します。
元利金継続(継続預入)
元利金継続(継続預入)を選択すると、元本と利息を合わせて定期預金を継続します。
複利効果を利用しつつ運用することになるため、定期預金を活用して少しでもお金を多く増やしたい人におすすめです。
元本が100万円で、1年満期、年利1%の定期預金を元利金継続する場合を例に解説します。
この定期預金が満期を迎えたときに得られる利息は10,000円です。
元利金継続の場合、元本と利息を合わせた101万円で自動的に新しい定期預金が開始されます。
さらに1年後、再び満期を迎えると得られる利息は10,100円となり、繰り返すほどに利息が大きくなって効率的にお金を増やせます。

複利の効果を簡単に解説!単利との違いや投資信託で効果を得る方法
元金継続(再預入)
元金継続(再預入)とは、定期預金の元本のみで再び定期預金を開始し、利息は指定した普通預金口座に自動的に入金する方法です。
満期を迎えて自動継続しても元本が増えないため、次の満期に得られる利息は変わりません。
得られる利息を自由に使える点はメリットですが、低金利の現在ではゆうちょ銀行やメガバンクなど多くの金融機関で定期預金金利は0.002%と低く、得られる利息も少ないためあまりメリットを感じないかもしれません。
定期預金が満期になったら考えたいこと

定期預金が満期を迎えた場合の今後の保有方法や運用方法について解説します。
子どもの教育資金用だったり、車の買い替え費用だったりと、特定の目的のために定期預金をしていた場合は、満期を迎えた定期預金の使い道が決まっています。
一方で、特別な目的がなく余剰資金で貯めていた定期預金は、使い道が決まっていません。
そのまま定期預金で運用を続けても問題ありませんが、別の選択肢も含めて考え方を紹介します。
生活防衛資金に追加する
「生活防衛資金」とは、不測の事態に対応するための資金です。
不測の事態には、病気やケガで働けなくなったり、失業してしまったりした状態や自然災害で家や財産に被害が出た場合などが挙げられます。
このような緊急時に対応するための資金を生活防衛資金として、貯金とは別で用意しておきましょう。
生活防衛資金は、もしものときに引き出しやすい普通預金口座での管理がおすすめですが、そのまま定期預金で管理したり、元本割れのリスクが低い債券で管理する選択肢もあります。
生活防衛資金として準備しておく金額の目安は人によって異なります。
ベースとなる数字は1ヶ月あたりの生活費です。
| 家族構成 | 生活防衛資金の目安 |
| 一人暮らし・独身 | 3〜6ヶ月分 |
| 夫婦(子どもがいない) | 3〜6ヶ月分 |
| 夫婦(子どもがいる) | 6〜12ヶ月分 |
自営業やフリーランスの方であれば、上記の目安よりも多めに準備しておいた方がいいかもしれません。
緊急時に備えるための資金が不足していると感じた人は、満期になった定期預金で補てんすることも検討しましょう。

【2025】生活防衛資金の目安はいくら?一人暮らしに必要な金額や貯金との違い
そのまま継続して定期預金する
定期預金が満期になっても特別な使い道がなく、生活防衛資金への補てんも必要ない場合は、そのまま自動継続で預ける選択肢もあります。
定期預金には「預金を簡単に引き出せない」特徴があるため、口座にお金が入っているとつい使ってしまう方でも、一定額を使わずに保有し続けられるでしょう。
上述の通り、キャンペーンによる上乗せ金利で定期預金を開始した場合、自動継続すると店頭表示金利が適用されるため、自動継続後に得られる利息は少なくなります。
少しでも高い金利で定期預金の運用を続けたい場合、キャンペーンの金利次第では自動継続ではなく一度解約して、新しく別の定期預金を開始してもよいかもしれません。
詳細については銀行に相談するのがおすすめです。
投資を始めてみる
当面の生活費や生活防衛資金も確保できている場合、定期預金で貯まったお金は「余剰資金」に分類されます。
一般的に、投資は余剰資金で行うことが推奨されるため、定期預金が満期を迎えたタイミングで投資を始めてもいいかもしれません。
定期預金で預けていたお金を投資に回すことに抵抗がある場合は、積立NISAから始めることをおすすめします。
積立NISAは、投資できる商品を金融庁が厳選している点や、毎月の投資額の上限が33,333円(年間で40万円が上限)と少額に抑えられることから、投資の経験の少ない人にもおすすめできる制度です。

積立NISAとは?投資初心者におすすめの理由をわかりやすく解説
まとめ:定期預金が満期になったら解約か継続を選べる

満期になった定期預金は「解約」か「継続」かを選びます。
満期後の対応については、定期預金の開始時にどちらにするかを選択しているため、満期日に特別な対応は必要ありません。
金融機関にもよりますが、一般的には満期を迎える前であれば解約するか継続するかの設定変更ができるケースが多いです。
満期になった定期預金は、そのまま定期預金として運用を続けるほか、生活防衛資金や投資に回す選択肢もあります。
生活防衛金として一定額以上の貯蓄がすでにある人は、満期を迎えた定期預金で投資を始めてみてはいかがでしょうか。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎
| 各年代の平均貯金額の記事 | |
| 20代の平均貯金額 | 30代の平均貯金額 |
| 40代の平均貯金額 | 50代の平均貯金額 |
| 60代の平均貯金額 | |
| 貯金の関連記事 | |
| 100万円貯める方法 | 貯金200万円は少ない? |
| 貯金300万の資産運用 | 40歳1000万は少ない? |
| 生活防衛資金はいくら? | 手取り15万円貯金方法 |
| 先取り貯金について | 貯金できない人の特徴 |
| 固定費の節約方法 | 実家暮らしの貯金方法 |
| 500円玉貯金について | 365日貯金について |