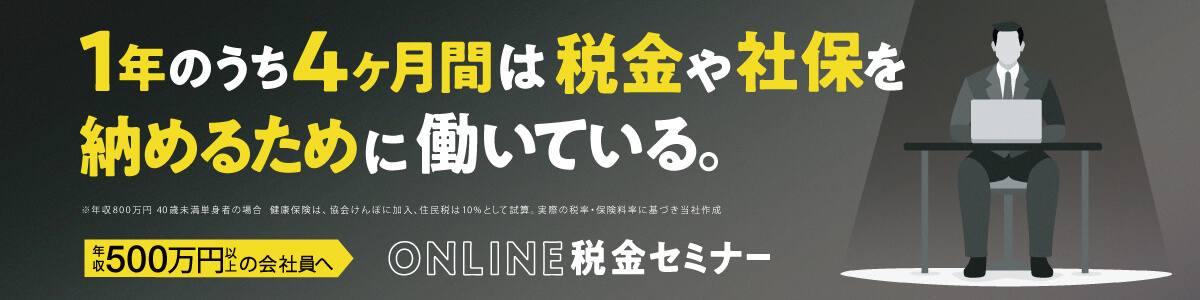【2025】独身税は日本で施行される?海外の事例や税金対策8選

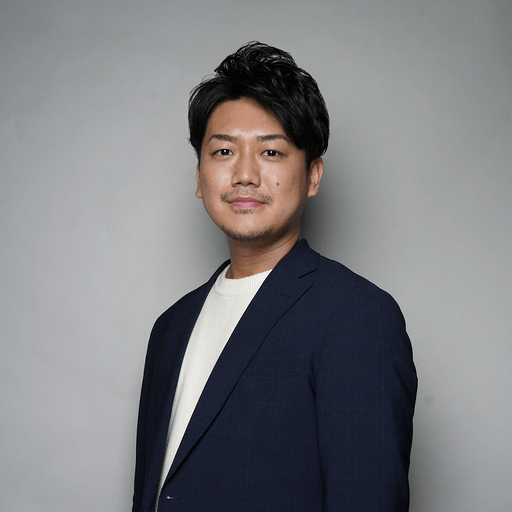
「独身税」。なにやら刺激的なワードですが、独身税を過去に導入した国は実際にあります。
日本でも度々SNSやネットニュース・掲示板などで議論になっているテーマです。
言葉のインパクトが強いせいもあり、どのような目的で議論されているのか、どのような影響があるか、実際に過去に施行された国ではどのようなことが起こったのか。
その中身までは知らない方も多いと思います。
この記事では独身税が日本で話題になった経緯、実際に導入されたブルガリアでの事例や独身の方も今から始めておきたい税金対策について紹介します。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎
独身税とは

「独身税」とはその名の通り、成人した未婚者(独身の方)に課す税金のことです。
過去にブルガリアが導入していた事例がありますが、2021年時点で独身税を導入している国はありません。
そもそもどういう目的で施行されたのかについて解説します。
出生率をあげるために施行された政策
独身税は出生率を上げるための少子化対策として、ブルガリアで1968~1989年まで導入されていました。
現在は施行されていませんが、約20年間ほど続きました。
ブルガリアの独身税では、独身者のみ収入の5~10%を税金として微収するものでした。25歳以上の独身者が対象です。
婚姻者と比べて税金を高くすることで、結婚を促すことを目的としていたようです。
結婚する人が増えれば、それだけ出生率もあがるだろうという理屈です。
ブルガリアの独身税は失敗に終わった
先述した通り、ブルガリアの独身税は21年で終了しました。
あまりにも評判が悪かったということもありますが、独身税が導入されていた間、ブルガリアの出生率は2.18から1.86へと下がっていたのも原因といわれています。
ブルガリアの独身税が失敗して以降、世界で独身税を導入した国はありません。
独身税を導入するのはハードルが高いですし、政府が想定した成果を得ることも難しいようです。
独身税は日本で施行されるか

刺激的なワードである「独身税」ですが、果たして日本でも導入される可能性はあるのでしょうか。
一時期SNSやニュースでも話題になった、日本での独身税について解説します。
かほく市ママ課の意見交換で一躍話題に
2017年に石川県かほく市のママ課(市のブロジェクトによる市民ボランティア組織)のメンバーと、財務省主計官との意見交換会が北陸財務局の主催で開催されました。
この意見交換会でママ課から意見の一つとして「独身税の導入について」の話題があがったようです。
このときに「独身税」という言葉だけが一人歩きしてしまい、ニュースでの報道やSNSでの拡散によって一時炎上のような形で話題になりました。
かほく市は「市としての正式な提案ではない」との声明を発表するなど、事態の沈静化に追われました。
日本でも注目度は高い
独身税はなにかとSNSやネットニュースなどで話題になります。
しかし、議論が深まることはほとんどなく、出ては消え、出ては消えの状況が続いている状態です。
これまでも政策の一つとして発表されたという事実はなく、著名人やマスコミが話題に上げたタイミングでそれを見た人たちがSNS上で意見するという構図になっています。
実際にSNSで「独身税」について調べてみると、反対意見が多い一方で賛成意見も少なからずあります。
実現の有無はさておき、日本でも関心のあるテーマではあるとはいえそうです。
選択の自由が奪われる
日本人の生涯未婚率は年々上昇しています。一昔前は「結婚するのが当たり前」という暗黙の文化や空気感がありましたが、現在はその価値観も大きく変わってきています。
自分の意志で結婚を選択しない人も、男女ともに増えているようです。
もし独身税が導入されてしまうと、「結婚をしない」という選択の自由が奪われてしまうことになってしまいます。
結論:日本で施行される可能性は低い
独身税は、噂レベルではたびたび出てくる話題です。しかし、実際に国の政策として議論されているわけではありません。
議論が加速し、今後日本で施行される可能性はゼロではありませんが、可能性は限りなく低いといえます。
ブルガリアでの失敗事例もありますし、現在は更に多様化も進んでいます。
少子化対策としての政策なら子育て支援や扶養控除の緩和、消費減税や経済成長など、別の形での対策を望みたい限りです。
独身者が支払っている税金

税金にはさまざまなものがあります。
所得税、住民税の直接税、消費税のほか、自動車税、タバコ税、酒税などの間接税がありますし、税金ではありませんが、似たような負担のある雇用保険料や年金保険、健康保険の社会保険料などがあります。
また、日本の所得税は累進課税で課税所得額が多くなればなるほど税率が高くなります。
独身時代が長くなればそれだけ収入は増えますが、控除額は増えないためますます独身者の税金負担は大きくなるのです。
それぞれの税金について見てみましょう。
所得税
所得税は、一定以上の収入がある人にかかってくる税金です。
会社に勤めている場合には給料から天引きされる源泉徴収税としてかかってきます。
給料は30万円あっても所得税に社会保険料、住民税などが差引かれますので、実際の手取り額は少なくなってしまうのです。
自分で事業をしている場合は確定申告をし、所得税などを支払います。
住民税
住民税は、1月1日に住んでいる住所地の都道府県税(4%)と市町村民税(6%)が合わさったもの(計10%)で、前年の所得に応じて翌年にかかってくる税金です。
源泉徴収された所得や確定申告した所得に応じて計算されて徴収されます。
会社に勤めている場合には、会社に徴収依頼がきて所得税と同じように天引きされますし、自分で事業をしている方の場合は、通知書とともに納付書が送られてきます。
住民税は6月にまとめて一括払いか、6月、8月、10月、翌年1月の計4回に分けて支払います。

住民税は分割払いできる?断られるケースや払えない場合の対応を解説
雇用保険
雇用保険は、失業した時に失業保険が支払われる雇用保険制度に基づいて徴収される保険料で、会社に勤めている方のみ会社で天引きされるのです。
国で定められた保険料(0.6%)を会社と折半して支払います。
(雇用保険料率は年度により変わります。)
社会保険
社会保険としては、老後に年金を受けられる年金保険と、普段病気やけがなどで病院にかかった時に7割ほどを負担してくれる健康保険の2つがあります。
会社に勤めている方の場合には、厚生年金保険、健康保険となり、これも会社と自身が折半して保険料を負担していて、給与天引きで徴収されます。
自分で事業をしている方の場合には、国民年金制度、国民健康保険制度に加入が義務付けられており、会社に負担してもらうことができませんので、自分で全額支払う必要があります。
【その他】自動車税、たばこ税など
その他にも、消費税や自動車税、酒税、タバコ税などの間接税が商品を購入するごとにかかっており、毎月の収入のかなりの部分を税金として負担している形です。
ただ、間接税の場合は累進課税になっていないため、実質的には独身者の負担は少ないといえます。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎
独身税は、噂レベルではたびたび出てくる話題です。しかし、実際に国の政策として議論されているわけではありません。
議論が加速し、今後日本でも施行される可能性はゼロではありませんが、可能性は限りなく低いといえます。
ブルガリアでの失敗事例もありますし、現在は更に多様化も進んでいます。選択の自由が奪われることになり、差別を生むことになりかねません。
少子化対策としてなら、子育て支援や扶養控除の緩和など、別の形での対策を望みたい限りです。
実質独身税!?既婚者の税制優遇

日本で独身税は導入されていませんが、既婚者には様々な税制優遇があります。
独身者と既婚者の税制制度の違いについて紹介します。
配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者控除・配偶者特別控除ともに、所得金額が一定金額以下の配偶者がいる人が受けられる所得控除です。
「配偶者を養う行為が税を負担する能力を減らしてしまう」という考え方から、その負担を調整するために設けています。
独身者にこのような制度はないため、既婚者ならではの税制優遇といえます。

【2025】配偶者控除とは?配偶者特別控除との違いや計算シミュレーションを紹介
扶養控除
扶養控除とは、合計所得が48万円以下で生計を一にする時に受けられる控除のことです。
家族がいて面倒を見なければいけない場合、独身者よりも負担が重くなります。
このような事情に考慮して、扶養する家族の人数に応じて税負担を軽減するものです。
家族がいる分、扶養家族がいる方が生活費はかかりますが、税金という面では独身者と比べて有利な場面が多いです。(なお、独身者でもご両親が扶養に入り扶養控除を使えるケースもあります)

扶養家族の対象条件とは?年収との関係や控除、履歴書の書き方について
既婚者と独身者の納税額を比較
既婚者と独身者の納税額を比較してみましょう。
35歳女性で年収1,000万円の方がいたとします。
結婚していて専業主夫、子供なしの場合と結婚せず独身の場合の所得税と住民税は以下のようになります。
| 既婚者 | 約132.5万円 |
| 独身者 | 約143.6万円 |
結果、既婚者のほうが税負担が約11万円も少なくなります。
子供ができて16歳以上になった場合、子供の扶養控除も使えるので税制優遇が大きくなります。
このように既婚者に有利な制度があることは認識しておきましょう。
\ ポイントを押さえて税金対策 /
▶︎▶︎無料オンライン税金セミナーを予約する◀︎◀︎
独身者必見!今からできる税金対策8選

独身税が日本で施行されることはありませんが、既婚者と比べて税制優遇に差があることも事実です。
ただ、独身者の方でもできる税金対策はたくさんあります。
独身者が今からできる税金対策について紹介します。
- 医療費控除を活用する
- 仕送りなどがあれば扶養控除が使える
- 特定支出控除を利用する
- ふるさと納税
- 住宅ローンを組む
- 雑損控除を活用する
- iDeCo(イデコ)で積立
- 生命保険で税金対策
1. 医療費控除を活用する
医療費控除とは、自分や家族の医療費を10万円超支払った人の場合、確定申告することによって一定額(原則200万円)まで控除される制度です。
確定申告による医療費控除は、年間に支払った医療費のうち5万円、又は所得の5%を越えた額の低いほうを越えた部分を所得の控除として受けることができます。
病院に行くための交通費なども含めて控除を受けることが可能です。
例えば歯医者で高額の医療費がかかった場合、20万円であれば控除対象は15万円になり、税率10%であれば15,000円の税金を取り戻すことができます。
2. 仕送りは扶養控除が使える
高齢の親などに仕送りをしている場合には、扶養控除が利用できます。
親が69歳以下なら38万円、70歳以上なら48万円を所得から差し引くことができますので、積極的に活用すべき制度です。

扶養家族の対象条件とは?年収との関係や控除、履歴書の書き方について
3. 特定支出控除を利用する
特定支出控除とは、仕事をする上で必要と認められた金額が給与所得控除の1/2を越えた場合に控除として認められる制度です。
個人事業主だけでなく、会社員の方でも使用できます。
仕事をする上での経費と認められるのはスーツや靴の購入代金、仕事のための勉強代や資格を得るための費用、交際費などが対象になります。
資格の範囲は自動車免許や簿記、弁護士など幅広いため、制度に適用できる支出がないか見直してみましょう。
4. ふるさと納税
ふるさと納税とは、全国各地の自治体に寄付することで控除が受けられる制度です。
自治体の中には地域の特産品などをお礼にくれるところも多く、2,000円の自己負担額で年収別の上限金額まで控除が受けられるので返礼品の分だけお得になる制度になります。
直接的な税金対策にはなりませんが、本来払うはずの税金で返礼品が貰えるという面では活用したい制度です。
ふるさと納税は確定申告が必要であると思われがちですが、ワンストップ特例制度を使えば確定申告不要で制度を活用することが可能です。

ふるさと納税はワンストップ特例制度と確定申告どっちがお得?違いを解説
5. 住宅ローンを組む
住宅ローンを組むと、住宅ローン控除を利用できます。
住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末時点での残高の1%が一般的に10年間、所得税(及び住民税)の額から控除され、最大控除額は10年間で一般的に400万円(1年で40万円)になり非常にお得な制度です。
税金対策のために住宅ローンを組むのは順番が違いますが、購入を検討している方は税制優遇を受けられる点を認識しておきましょう。
6. 雑損控除を活用する
雑損控除は、台風や地震などの自然災害によって損失を被った場合や、盗難にあった際に利用できる所得控除です。
雑損控除はぜいたく品には適用できませんが、不幸にも盗難や災害などにあってしまった場合は、積極的に活用すべき制度になります。
7. iDeCo(イデコ)で積立
iDeCoとは個人型確定拠出年金の愛称です。毎月の掛金が全額所得控除の対象になるため、年末調整や確定申告を行うことで税金が戻ってきます。
iDeCoは掛金が全額所得控除になるだけでなく、運用中に発生した利益に対しても税金がかからず、年金としてお金を受け取るときにも税制優遇されているお得な制度です。
老後資金を貯めるための資金で税金対策にもなるため、少額からでも始めることをおすすめします。

iDeCoを利用するおすすめの証券会社は?選ぶ基準や始め方も解説!
8. 生命保険で税金対策
生命保険料は所得控除になるため、年末調整や確定申告を行うことによって所得税が安くなります。
生命保険料控除は「生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」それぞれで利用できます。
一つの保険料当たり最大4万円が利用できるため、合計最大12万円分を所得控除に利用できます。
まとめ:独身税の噂に踊らされないように注意

今回は独身税について解説しました。独身税が日本で導入される可能性は極めて低いですが、100%導入されないとは限りません。
既婚者にしか利用できない税制優遇策があるのは事実ですが、独身の方でも利用できる税制優遇はたくさんあります。
「独身税」という言葉に惑わされず、今ご自身が活用できる税金対策で賢く資産を増やしましょう。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎
| 現在人気の記事一覧 | |
| マネリテとは | 断捨離の効果 |
| マイナンバーカード作り方 | マイナンバーカード自撮り |
| マイナポイント入手方法 | 住民票は移すべき? |
| ボーナスの平均支給額 | 預金封鎖とはなにか |
| 一攫千金は現実的? | 小銭の両替方法 |
| 年収別の手取り金額 | 現金書留封筒の購入場所 |
| 女性一人暮らしの食費 | おすすめ資産管理アプリ |