【2025】女性・主婦におすすめの株主優待10選!10万円以下で買えるものや美容系まで紹介

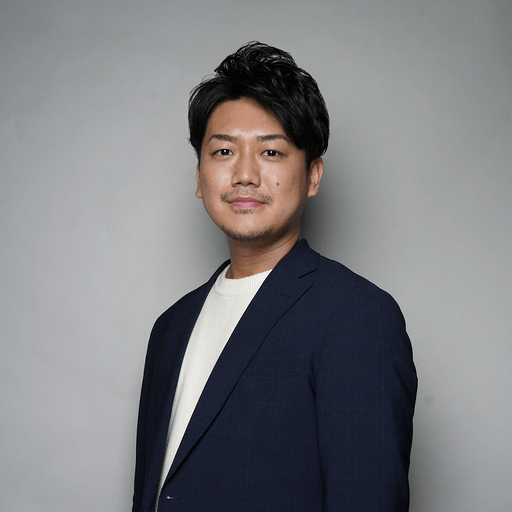
株式投資をするメリットの一つに「株主優待」があります。
株式を保有していることで、配当金以外にも食品や割引券、化粧品などががもらえます。
株主優待に注力している企業は多く、優待を目的に投資をしている方も多いです。
この記事では、株主優待の種類や購入するときの注意点、女性や主婦の方におすすめの銘柄を紹介します。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎
株主優待とは

株式投資の楽しみの一つに株主優待があります。
株主優待とは具体的にどのようなものかを解説します。
企業から株主への御礼品
株主優待とは、株式を発行している企業から株主に対して贈られる御礼品です。
企業からの「株式を保有してくれてありがとう!」という思いが込められています。
昔は海外でも実施されていましたが、今では「日本独自の文化」といっても過言ではありません。
企業側は、株主優待を投資家へ贈ることで自社商品のアピールができ、より会社のファンになってもらうことに期待できます。
また、株主からの支持が高まれば長期間、株を保有してくれることが見込めるため、株の保有期間に応じて優待内容がお得になる「長期保有優遇制度」を設けている企業もあります。
人気の株主優待
| 女性におすすめの 株主優待 | 化粧品 美容品 サプリメント ファッション 雑貨購入割引券など |
| 日常生活で使える 株主優待 | クオカード レストラン食事券 ファーストフード食事券 居酒屋割引券など |
| 好きな商品が届く 株主優待 | グルメカタログ ギフトカタログ 飲料品・お菓子詰め合わせセット など |
| 趣味を楽しめる 株主優待 | 図書カード スポーツ用品割引券 電化製品割引券 映画観賞券など |
| 旅行がお得になる 株主優待 | 宿泊券 旅費・運賃割引券 遊園地入場券など |
株主優待のバリエーションは非常に豊かです。
商品券から化粧品、割引券、好きなものが選べるカタログギフトや企業の自社商品など、日常生活で使える優待品が数多くあります。
上場企業の約4割が実施している
株主優待は、あくまでも企業側が行う株主還元施策の一つであるため、株主優待を実施していない企業もあります。
株主優待を実施している企業は、上場企業全体の約4割を占めます。
各企業の定める「株主優待がもらえる権利が確定する日(権利確定日)」に、その企業の株を保有していることで株主優待がもらえます。
株主優待を実施している・していない企業の一例は次のとおりです(2023年6月時点の情報です)。
| 優待を出している企業 | 優待を出していない企業 |
| ハウスオブローゼ アジュバンホールディングス ミルボン ハーバー研究所 オリエンタルランド ワコールホールディングス イオン カゴメ など | 出前館 アサヒホールディングス LIXIL トヨタ自動車 リンクアンドモチベーション ノエビアホールディングス など |
女性・主婦におすすめの10万円以下で買える株主優待4選

株主優待の多くは、100株(1単元)以上の株式を保有している株主を対象としています。
例えば、株価が800円で株主優待がもらえる基準が100株からの場合、8万円の資金が必要です。
そこで、貯金やボーナスでチャレンジできそうな10万円以下で買える株式のうち、女性や主婦の方におすすめの銘柄を4つ紹介します。
バロックジャパンリミテッド(3548)
バロックジャパンリミテッドは、「婦人服の「MOUSSY(マウジー)」や「SHEL’TTER(シェルター)」、「RODEO CROWNS(ロデオクラウンズ)」などのブランドを展開しているアパレル企業です。
2000年に渋谷109にファッションブランド「MOUSSY」を展開。シルエットが美しく見えるジーンズが爆発的に売れ、2016年には東証一部に上場しています。
株主優待(100株保有の場合)は、店舗や自社通販サイトで使える2,000円分のクーポンが半年に1回もらえます。
通販サイトで利用した場合、購入金額にかかわらず送料が無料になる特典もあります。
100株保有していると年間で4,000円分のクーポンがもらえるので、株主優待利回りは約4.6%です(2023年6月時点)。
クーポンはアウトレットサイトでも利用でき、お得に買い物が楽しめます。
バロックジャパンリミテッドの株主優待の基本情報
| 株価 | 860円 ※2023年6月27日時点 |
| 権利確定日 | 2月末日・8月末日 |
| 優待回数 | 年2回 |
| 優待獲得株数 | 100株以上:上期に1枚、下期に1枚、計2枚(年間4,000円相当) |
| 200株以上:上期に2枚、下期に1枚、計3枚(年間6,000円相当) | |
| 500株以上:上期に2枚、下期に2枚、計4枚(年回8,000円相当) |
出典:株式会社バロックジャパンリミテッド「株主優待制度」
出典:Yahoo!ファイナンス「(株)バロックジャパンリミテッド」
クックパッド(2193)
クックパッドは、料理レシピの投稿・検索を中心とした日本最大の料理サイトを運営する会社です。
1998年に料理サイト事業を開始し、100万品以上のレシピが投稿され毎日多くのユーザーに利用されています。
2018年9月には、生鮮食品ネットスーパー「クックパッドマート」を開始するなど、「毎日の料理を楽しみにする事業」を広く展開中です。
株主優待(100株保有の場合)は、クックパッドプレミアムサービス利用の無料クーポン券(6ヶ月分/1,848円×1枚)と、家族や友人がプレミアムサービスを無料利用できる紹介クーポン券(6ヶ月分/1,848円×3枚)です。
クックパッドのプレミアムサービスについて
プレミアムサービスとは、クックパッドの全ての機能を利用できるサービスです。通常は月額308円(税込)がかかりますが、株主優待を使うと6ヶ月間無料で利用できます。
さらに、100株以上を1年以上保有するとプレミアムサービスの1年間無料クーポンがもらえるため、株を持ち続けると実質的に永年無料でプレミアムサービスが利用できようになります。
プレミアムサービスでは、人気順や調理時間など条件を絞り込んでレシピが検索できたり、毎日の献立の提案、ダイエットや離乳食など専門家が厳選するテーマ別のレシピ提案など、料理がますます楽しくなる機能が利用できます。
料理好きの方や普段からクックパッドを利用している方におすすめです。
クックパッドの株主優待の基本情報
| 株価 | 170円 ※2023年6月27日時点 |
| 権利確定日 | 12月末日 |
| 優待回数 | 年1回 |
| 優待獲得株数 | 100株以上 |
| 保有期間1年未満: ・「クックパッド」プレミアムサービス利用/6ヶ月無料クーポン1枚 ・「株主様専用ご紹介クーポン」プレミアムサービス利用/6ヶ月無料クーポン3枚 | |
| 保有期間1年以上: ・「クックパッド」プレミアムサービス利用/1年間無料クーポン1枚 ・「株主様専用ご紹介クーポン」プレミアムサービス利用/6ヶ月無料クーポン3枚 |
出典:クックパッド株式会社「第26期株主優待のご案内」
出典;Yahoo!ファイナンス「クックパッド(株)」
コジマ(7513)
コジマは、一般家庭用電化製品をはじめ、おもちゃ、日用品、医療品などを販売する大手家電量販店です。
1955年の創業以降、事業を拡大し1996年に上場、2012年にビックカメラの子会社になっています。
「家事代行サービス」や家電製品の相談や点検を行う「コジマくらし応援便」など、販売以外にもさまざまなサービスを展開中です。
株主優待(100株保有の場合)は、店舗やネットで利用できる「株主様お買物優待券(1,000円分)」です。
コジマのほかビックカメラ、ソフマップおよびビックカメラアウトレットの各店舗でも使えます。
電化製品だけではなく、店舗内で取り扱っている日用品や医療品の購入にも使えるため便利です。
さらに、2021年からは長期保有者向けの優待制度も新設されました。
1年以上株式の保有を続けることで、株主優待券が最大2枚追加されるため、長く株式を持ち続けるほどお得になります。
コジマの株主優待の基本情報
| 株価 | 579円 ※2023年6月27日時点 |
| 権利確定日 | 8月末日 |
| 優待回数 | 年1回 |
優待獲得株数 | ・株主優待制度 100株以上:1,000円券×1枚 500株以上:1,000円券×3枚 1,000株以上:1,000円券×5枚 3,000株以上:1,000円券×15枚 5,000株以上:1,000円券×20枚 ・長期保有優待制度 保有期間1年以上2年未満(連続3・4回保有):1,000円券1枚追加 保有期間2年以上(連続5回以上保有):1,000円券2枚追加 |
出典:株式会社コジマ「株主優待制度」
出典:Yahoo!ファイナンス「(株)コジマ」
RIZAPグループ(2928)
RIZAPグループは、パーソナルトレーニングジム「RIZAP(ライザップ)」やRIZAP GOLF等のRIZAP関連事業の運営、また、美容関連用品・健康食品の販売を行っている子会社を総括する持株会社です。
ライフスタイル事業として雑貨商品やスポーツ用品などの企画から販売までを行うなど、数多くのグループ企業と連携を図っています。
2006年に上場、2016年より「RIZAPグループ株式会社」に社名を変更し、健康を願う全ての人々の健康に貢献したいという考えのもと、事業を拡大し続けているグループです。
株主優待は、持ち株数に応じてもらえる株主優待ポイントです。
例えば、400株以上で10,000ポイント、800株以上で14,000ポイントがもらえます。
ポイントを使って、RIZAPのシェイプアッププログラムコースに申し込めたり、美容グッズやサプリメントなどさまざまな商品の中から好きなものを選ぶことができます。
株主優待ポイントの有効期限は最大3年間なので、ポイントを貯めてより豪華な商品と交換することも可能です。
日頃から健康や美容に気をつけている方に嬉しい株主優待になっています。
RIZAPグループの株主優待の基本情報
| 株価 | 157円 ※2023年6月27日時点 |
| 権利確定日 | 3月末日 |
| 優待回数 | 年1回 |
| 優待獲得株数 | 400株未満:特別優待券5,000円分 400株以上:10,000ポイント 800株以上:14,000ポイント 1,600株以上:24,000ポイント 2,400株以上:30,000ポイント 4,000株以上:36,000ポイント 8,000株以上:72,000ポイント 16,000株以上:144,000ポイント |
出典:RIZAPグループ株式会社「株主優待情報」
出典:Yahoo!ファイナンス「RIZAPグループ(株)」
女性・主婦におすすめの美容系株主優待6選

日本を代表する美容系株主優待を6つ紹介します。
10万円では買えませんが、株主優待カタログを見るだけでもわくわくするものばかりです。
資生堂(4911)
資生堂は、化粧品を中心とした事業を行っており、化粧品の国内シェア第1位を誇っています。
国内だけに限らず世界約120カ国の地域でも事業展開しており、世界に飛躍する日本企業です。
1872年に洋風調剤薬局として東京・銀座に誕生、1927年に株式会社資生堂が設立されました。
老舗でありながら今もなお日本のトップ企業として名を馳せ、化粧品事業だけではなく、レストラン事業、美容室事業、教育・保育事業と幅広く展開しています。
株主優待は、資生堂の自社商品です。「アクアレーベル」「専科シリーズ」など、資生堂ブランドから選べます。
株主優待でありながら、奨学金制度への寄付を選択することもでき、社会貢献をしたい方の要望にも応えています。
ただし、優待をもらうには権利確定日から100株以上を1年以上保有していることが条件のため、保有期間に注意が必要です。
資生堂の株主優待の基本情報
| 株価 | 6,541円 ※2023年6月27日時点 |
| 権利確定日 | 12月末日 |
| 優待回数 | 年1回 |
| 優待獲得株数 | 100株~1,000株未満を1年超保有:自社グループ製品カタログ(1)から1点 |
| 1,000株以上を1年超保有:自社グループ製品カタログ(2)から1点 |
出典:株式会社資生堂「株主優待」
出典: Yahoo!ファイナンス「(株)資生堂」
ポーラ・オルビスホールディングス(4927)
ポーラ・オルビスホールディングスは、「ポーラ」「オルビス」の2大化粧品ブランドを中心とした「美と健康」に関わる事業をグローバルに展開しています。
以前は訪問販売が主流でしたが、現在は店舗型の「ポーラ ザ ビューティー」や「ポーラ エステイン」で売上を伸ばし、スキンケア事業を順調に拡大中です。
株主優待は、保有株式数と保有期間に応じた「株主優待ポイント」がもらえます(1ポイント100円相当)。
100株を3年未満保有している場合、15ポイント(1,500円相当)、3年以上保有で35ポイント(3,500円相当)がもらえ、株主優待カタログ掲載のグループ商品と交換できる仕組みです。
いつもの化粧品と交換したり、新しい化粧品にチャレンジしたりとスキンケアが楽しみになりますね。
ポーラ・オルビスホールディングスの株主優待の基本情報
| 株価 | 2,079円 ※2023年6月27日時点 |
| 権利確定日 | 12月末日 |
| 優待回数 | 年1回 |
| 優待獲得株数 | 【保有期間3年未満】 |
出典:株式会社ポーラ・オルビスホールディングス
出典:Yahoo!ファイナンス「(株)ポーラ・オルビスホールディングス」
ファンケル(4921)
ファンケルは「FANCL」ブランドを中心とした無添加化粧品や「カロリミット」、「粉末青汁」などのサプリメント、健康食品を自社で研究・開発・販売しています。
お客様の声をすばやく社内へ反映する「製販一貫体制」を強みとし、国内だけではなくアジアや北米など海外にも事業を展開中です。
100株以上200株未満の株式を保有している場合、株主優待として、カタログより3,000円相当の商品を1点選ぶことができます。
カタログには「マイルドクレンジング」や「大人のカロリミット」、「ファンケル銀座スクエアご利用券」などが掲載されています。
多彩なファンケルの商品の中から、体調や目的に合わせて自分にピッタリの優待を選ぶことが可能です。また、3,000円を優待の代わりに寄付することも選べます。
ファンケルの株主優待の基本情報
| 株価 | 2,380円 ※2023年6月27日時点 |
| 権利確定日 | 3月末日 |
| 優待回数 | 年1回 |
| 優待獲得株数 | 100株以上200株未満:3,000円相当の自社製品または「ファンケル銀座スクエア」利用券 |
| 200株以上:6,000円相当の自社製品または「ファンケル銀座スクエア」利用券 |
※2023年3月31日現在、1単元(100株)以上を6ヶ月以上継続保有が条件
出典:株式会社ファンケル「株主優待」
出典:Yahoo!ファイナンス「(株)ファンケル」
ヤーマン(6630)
ヤーマンは、「美しくを、変えていく。」という企業スローガンのもと、家庭用美容機器や化粧品の研究・開発・製造に取り組んでいる企業です。
エステサロン用の美容機器の研究開発によって培われた知見を家庭用美容機器の開発に活かすことで、一人一人が理想の美しさを叶えられることを目指しています。
100株以上保有していれば、保有期間が1年未満でも5,000円の株主優待割引券が進呈されます。
株主優待割引券の金額は、保有株式数や保有期間によって異なり、500株以上の株式を5年以上保有すると最大23,000円の株主優待割引券を手に入れることが可能です。
株主優待割引券は、ヤーマンオンラインストアで商品購入の際に利用できます。
ヤーマンの株主優待の基本情報
| 株価 | 1,017円 ※2023年6月27日時点 |
| 権利確定日 | 4月末日 |
| 優待回数 | 年1回 |
| 優待獲得株数 | 【100株以上500株未満】 保有期間1年未満:5,000円 1年以上:7,000円 2年以上:10,000円 5年以上:13,000円 【500株以上】 保有期間1年未満:14,000円 1年以上:17,000円 2年以上:20,000円 5年以上:23,000円 |
出典:ヤーマン株式会社「株主優待制度のご案内」
出典:Yahoo!ファイナンス「ヤーマン(株)」
シーボン(4926)
シーボンは、ホームケアとサロンケアの両方で「美を創造し、演出する」ことを目指す企業です。
アフターサービスにも力を入れており、化粧品を購入した方は全国に展開するシーボンのサロンで定期的な肌チェックやフェイシャルケアを受けられるというサポートを行っています。
化粧品を販売して終わりではなく、「購入後もお客様の肌に対して最後まで責任を持つ」という想いを大事にしている企業です。
シーボンの株主優待は、保有期間・保有株数に応じた金額分のシーボン商品と引き換えられるというものです。
引き換えられる優待品には、スキンケアアイテムやヘアケアアイテムのほか、酵素ドリンクやメンズケアアイテムなども含まれています。
普段からシーボンの商品を愛用している方や、新しく試してみたい商品がある方にとっては嬉しい優待です。
ただし、優待がもらえるのは継続保有期間が1年以上となる株主に限られる点に注意しましょう。
シーボン株主優待の基本情報
| 株価 | 1,559円 ※2023年6月27日時点 |
| 権利確定日 | 3月末日 |
| 優待回数 | 年1回 |
| 優待獲得株数 | 100〜499株/ 保有期間1年以上: 8,000円分、3年以上:10,000円分 500株以上/ 保有期間1年以上:20,000円分、3年以上:25,000円分 |
出典:株式会社 シーボン「株主優待制度のご紹介」
出典:Yahoo!ファイナンス「(株)シーボン」
三越伊勢丹ホールディングス(3099)
三越伊勢丹ホールディングスは、三越・伊勢丹をはじめとする各地の百貨店などを所有・運営する企業です。
三越伊勢丹グループは、国内20店舗・海外28店舗の百貨店事業を中核としながら、金融やシステム・物流など幅広い事業を展開しています(2023年6月28日時点)。
株主優待は、三越伊勢丹グループ店舗で利用できる「株主様ご優待カード」がもらえるというものです。
カード有効期限内であれば、優待対象店舗での買い物や飲食代金で何度でも10%の割引が受けられます(保有株数によって上限金額あり)。
例えば、100株保有(3月末日時点の株主)の場合は利用限度額が30万円となっているため、累計30万円分までの買い物に10%割引が適用され、割引金額の上限は3万円です。
権利確定日は年2回ありますが、優待カードが発行されるのは年1回で、発行時期によって利用限度額が異なります。
デパコスやフレグランスにも優待カードを利用できるため、お気に入りの化粧品ブランドが複数ある方にもおすすめの株主優待です。
三越伊勢丹ホールディングスの株主優待の基本情報
| 株価 | 1,436円 ※2023年6月27日時点 |
| 権利確定日 | 3月末日・9月末日 |
| 優待回数 | 年1回 |
| 優待獲得株数 | 百貨店およびグループ各店舗、オンラインストアで、利用限度額の範囲内で10%割引 100株以上/利用限度額:30万円 300株以上/利用限度額:40万円 500株以上/利用限度額:50万円 1,000株以上/利用限度額:100万円 3,000株以上/利用限度額:150万円 5,000株以上/利用限度額:200万円 10,000株以上/利用限度額:300万円 ※9月末時点の新規株主には上記利用限度額の半額が限度額として設定されたカードが発行される |
※初めて「株主優待カード」が発行された後継続して株式を保有し、3月末日の基準日を2年連続で迎えた時点で保有株式数が300株以上の場合、次回からの「株主優待カード」の利用限度額が2倍になります。
出典:株式会社三越伊勢丹ホールディングス「三越伊勢丹グループについて」
出典:株式会社三越伊勢丹ホールディングス「株主様ご優待制度」
出典:Yahoo!ファイナンス「(株)三越伊勢丹ホールディングス」
株主優待を選ぶ際の注意点

株主優待を目的とした投資をするにあたって、以下の点に注意しましょう。
必要な株数を保有していること
株主優待をもらうための条件として、銘柄ごとに株式の「優待獲得枚数」が決められています。
多くの株主優待は100株以上とされていますが、なかには1株でもらえる銘柄があったり、500株以上保有していないともらえない銘柄もあります。
企業によって条件が異なりますので、投資する前に必ず確認してください。
権利確定日に株を保有していること
株主優待をもらうためには、各企業が定める「権利確定日」に株式を保有している必要があります。
(例)2023年9月末決算銘柄のケース
| 9月27日(水) | 9月28日(木) | 9月29日(金) |
| 権利付き最終日 | 権利落ち日 | 権利確定日 |
「権利確定日」は、配当や株主優待をもらう権利が確定する日です。
株主優待の権利を受けたい場合、「権利確定日」の2営業日前(権利付最終日)までに株式を購入する必要があります。
例えば、月末30日が権利確定日の場合、2営業日前の28日までに株式を購入しなければいけません。
加えて、土日祝日などの休場日の場合は、営業日に含まずに繰り上げてカウントします。
上記の例の場合は9月30日が土曜日となるため、権利確定日が29日(金)、権利付き最終日が27日(水)となります。
株主優待の用語解説
| 用語 | 意味 |
| 権利確定日 | 配当金や株主優待がもらえる権利が確定する日のこと。権利確定日に株式を購入しても、その期の配当や株主優待は受け取れません。 |
| 権利付最終日 | 株主の権利を得ることができる最終売買日のこと。配当金や株主優待を受け取りたい場合は、「権利確定日」の2営業日前までに株式を購入する必要があります。 |
| 権利落ち日 | 「権利付最終日」の翌営業日のこと。この日を過ぎてから株式を売却しても、配当金や株主優待を受け取ることができます(そのため、売却が多くなり株価が下落しやすい傾向があります)。 |
株主優待の廃止、改悪の可能性があること
株主優待は、企業の業績や事業内容の変更などにより、優待の廃止や改悪の可能性があります。
業績が低迷したことによって株主優待を廃止、または縮小した企業も目立つので、優待目当てで株を選ぶ際は慎重さが必要です。
株主優待の廃止や改悪が発表されると投資家の多くが保有株を手放し、株価が急落することもあります。
外食大手の「すかいらーくホールディングス」は、2020年9月に優待内容の大幅縮小を発表し、その翌日に株価は一時10%超下落しました。
他にも、直近では以下のような企業が株主優待の廃止を発表しています。
| 企業名 | 優待内容 | 廃止発表日 |
| トプコン | 「メガネのアイガン」などで利用できる割引券 | 2023年1月 |
| ノエビアホールディングス | ノエビアグループ商品セットなど | 2023年2月 |
| 東京個別指導学院 | カタログギフト | 2023年1月 |
| ペッパーフードサービス | グループ店舗で利用できる株主優待券または商品 | 2022年8月 |
| あさひ | 「サイクルベースあさひ」などで利用できる優待券 | 2023年4月 |
長期保有を前提とした投資の場合も、保有している銘柄の業績や決算発表を確認する癖をつけておきましょう。
株価急落のリスクがある
前述の例のように、株価は急激に下落する可能性があります。
短期的に保有し、売却益(キャピタルゲイン)を目的としている場合、株価変動は大きなリスクです。
一方、中長期的に株式を保有し、株主優待や配当金(インカムゲイン)を目的としている場合は、短期的な株価の変動にとらわれず保有し続けるという選択もできます。
しかし、企業の業績が悪くなれば株価の下落だけでなく、株主優待や配当金が改悪されることもあり得ます。
優待ばかりに目を向けるのではなく、投資先企業の将来性をチェックしたうえで株式の購入を検討することが重要です。

キャピタルゲインとインカムゲインの違いとは?特徴やおすすめを解説
まとめ:株主優待という視点からも投資先を選んでみよう

株主優待をもらうために「聞き慣れた会社」や「日頃使っている商品の会社」を投資先として選ぶことで、その会社の応援にもつながります。
株式投資の目的が、「株主優待をもらうため」と決まっていれば、多少の株価変動にも動じることなく、長期間株式を保有して楽しく投資を続けられるでしょう。
株主優待をもらいながら株価上昇をじっくりと待つというのも一つの方法です。
株主優待という視点からも投資先を検討してみましょう。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎
| 投資の関連記事 | |
| 株式投資の始め方 | 従業員持株会とは |
| 投資で生活可能? | 配当金で生活できる? |
| 自社株買いとは | 空売りとは |
| 10万円以下の株主優待 | 高配当株のメリット |
| 投資はいくらから? | モメンタム投資とは |
| 投資の種類 | 分散投資とは |
| 長期投資の効果 | コアサテライト戦略 |
| 複利の効果 | アセットアロケーション |
| ポイント投資の特徴 | 株主総会とは |








