年金の差し押さえとは?回避方法や基準、未納から実行までの流れ


記事監修者
マネカツ編集部
"将来への漠然としたお⾦への不安はあるけど、何から始めていいのかわからない…"
そんな方に向けて「資産運用」や「税金対策」など、お金に関する情報を発信しています。

記事監修者
マネカツ編集部
"将来への漠然としたお⾦への不安はあるけど、何から始めていいのかわからない…"
そんな方に向けて「資産運用」や「税金対策」など、お金に関する情報を発信しています。
国民年金を滞納されている方には、様々な事情があると思います。
単純に納付を忘れていた、生活が厳しくて支払う余裕がないなど、それぞれ事情があって、年金を払えていない方もいるでしょう。
しかし、どのような事情があったとしても、年金未納を放置すると最悪の場合財産の差し押さえに発展する可能性があります。
この記事では、国民年金保険料を未納するとどうなるのか、最悪のケースとして未納から差し押さえになってしまうまでの流れについて解説します。
年金納付は国民の義務となっており放置しても状況は改善しませんので、支払えない場合の対応方法についても参考にしてください。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎
この記事の目次
国民年金保険料を未納のままにするとどうなるか
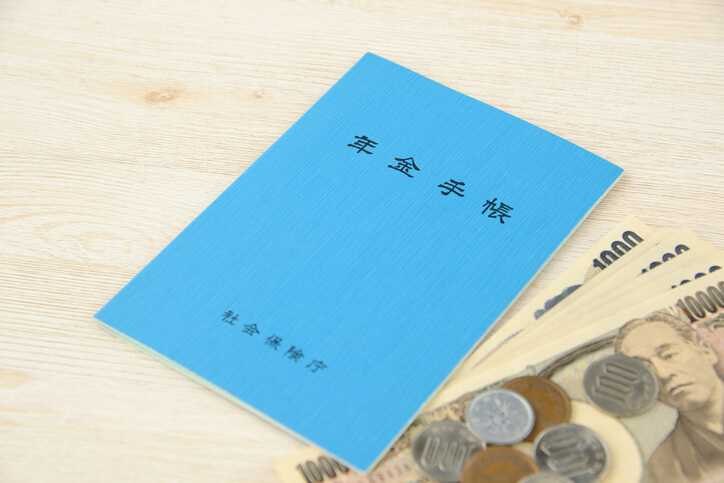
国民年金保険料を未納のままにしていると、「年金を受け取れない」「財産を差し押さえられる」といった不都合が生じる可能性があります。
一定額以上の収入がある方が国民年金保険料を滞納し続けると、最悪の場合財産の差し押さえが実行されます。
年金への加入は法律で義務づけられている
日本に住む20歳以上60歳未満の人は、国民年金への加入が義務付けられています。
日本国籍を持たない20歳以上60歳未満の外国人であっても、日本に住んでいれば加入義務があります。
国民年金保険料を納めた方が受給できる年金の種類は、以下の3つです。
| 種類 | 概要 |
| 老齢基礎年金 | 老後の生活を支える資金 (一般的にイメージされる老後の年金) |
| 障害基礎年金 | 病気やケガが原因で仕事や生活が制限された際に生活を支える資金 |
| 遺族基礎年金 | 亡くなった方に生計を維持されていた家族の生活を支える資金 |
年金保険料を納付していれば、条件を満たすことで、「老後生活」「一定以上の障害を負ったとき」「もしものときの家族の生活費」の保障を得られます。
将来年金が受け取れない可能性がある
国民年金保険料を納付しない場合、将来年金が受け取れない可能性があります。
年金を受給するためには受給要件を満たす必要があり、受給要件には年金保険料の納付状況が関連しています。
| 種類 | 受給要件(一部抜粋) |
| 老齢基礎年金 | ・保険料納付済期間と免除期間の合計が10年以上 |
| 障害基礎年金 | ・被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間の合計が2/3以上 ・初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(初診日が令和8年4月1日前にあるとき、初診日において65歳未満) |
| 遺族基礎年金 | ・保険料納付済期間と免除期間の合計が国民年金加入期間の2/3以上 ・死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(65歳未満で死亡した方のうち、死亡日が令和8年3月末日までの方) |
| 老齢年金の受給権者 (受給資格を満たした方) の遺族基礎年金 | ・保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間の合計が25年以上 |
上記のように国民年金を受け取るためには、国民年金保険料の納付が必要です。
受給要件を満たさない場合は、必要な時に年金が受け取れなくなってしまいます。
老齢基礎年金に関しては、受給要件を満たしていても未納期間があると将来受け取る年金支給額が減少する可能性があります。
年金保険料の納付率

納付率は77.16%
厚生労働省の調査によると、令和2年度(2020年)の年金保険料納付率は71.49%でした。
約30%の方が年金未納であることがわかります。
年金保険料は過去2年分の納付が可能です。
令和2年度の資料には平成30年度(2018年)までの最終納付率が記載されていますが、平成30年度の最終納付率は77.16%で、当時の納付率は68.12%でした。
平成30年度分を含むここ数年は、2年以内に未納分を納付する方が約10%いると確認できます。
過去5年のデータを見ると納付率は徐々に増加しているため一概には言えませんが、令和2年度の最終納付率は80%を超えると予想されます。
令和2年度の納付率を年齢別に見ると、25〜29歳の納付率が59.48%と最も低く、次いで30〜34歳までの納付率が63.96%という割合でした。
若い世代ほど、国民年金を納付できていない傾向にあるといえるでしょう。
未納原因は将来への不安や所得格差拡大の影響?
少子高齢化が進む日本では、年金制度の破綻について話題になることが多く、特に若い世代にとっては「将来年金をもらえないのではないか」という不安を抱く方もいます。
年金をもらえる見込みが低いため保険料を支払う必要性を感じられなかったり、支払った金額以上に年金をもらえる見込みの無さから「損になるのではないか」と考える方もいるでしょう。
収入が少ない人にとっては、自身の今の生活が厳しいため保険料を支払う余裕がないケースもあります。
首相官邸の年金制度改革のページにある、年金に関するQ&Aから一部抜粋して未納原因となり得る要素に関する解答を紹介します(2022年6月時点)。
年金制度の破綻
年金制度は国が責任を持って運営していくため、制度の破綻はないとの回答です。
年金は、支払った保険料が将来自分に返ってくるという制度ではありません。現役世代が納めている保険料から、その時の受給者に年金が支払われる仕組みです。
少子高齢化が進行していく中で、国は給付と負担の調整を行うことで制度の維持を図っていくようです。
参考:国立国会図書館 インターネット資料収集保存事業 「首相官邸 疑問2 年金に保険料を納めても、将来自分が高齢者になる頃には制度が破綻してしまうのではありませんか?」
払い損になるのでは?
結論から言うと、年金は払い損にはなりません。
年金の財源は、私たちが納める保険料の他にも「国庫負担」と「積立金の運用収入」があります。
会社員の方が加入する厚生年金保険であれば、保険料が労使折半であるため会社が保険料の半分を負担してくれています。
そのため、支払った保険料以上の給付を受けることが見込めるでしょう。
加えて、国は年金給付水準の見直しを行うことで、世代間の給付と負担の極端な格差が生じないようにしています。
資料にあるデータによると、1995年生まれや2005年生まれの若者であっても、年金給付額が保険料を上回る見込みであることがわかります。
【1995年生まれ】
| 国民年金 | 厚生年金 (基礎年金を含む) | |
| 保険料 | 1,400万円 | 3,700万円 |
| 年金給付 | 2,300万円 | 8,500万円 |
| 比率 | 1.7倍 | 2.3倍 |
【2005年生まれ】
| 国民年金 | 厚生年金 (基礎年金を含む) | |
| 保険料 | 1,600万円 | 4,100万円 |
| 年金給付 | 2,600万円 | 9,500万円 |
| 比率 | 1.7倍 | 2.3倍 |
参考:国立国会図書館 インターネット資料収集保存事業 「首相官邸 疑問3 「払い損」になるのではないですか?」
年金未納から差し押さえまでの流れ
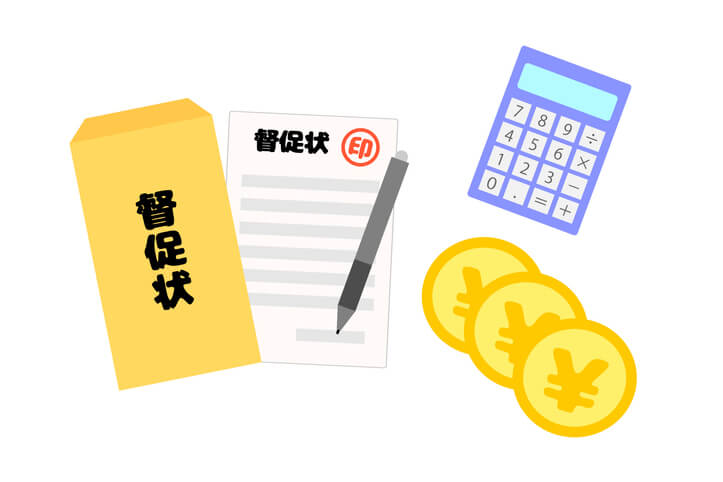
国民年金保険料の滞納を続けた場合、最悪のケースでは財産の差し押さえが実行されます。
滞納を続けていたある日、突然差し押さえが実行されるのではなく、順を追って電話や訪問、書面による催告から始まります。
1. 催告状
国民年金を滞納すると、日本年金機構から「国民年金未納保険料 納付勧奨通知書(催告状)」が届きます。
この書類には、保険料未納の期間や金額が記載されています。
この段階では日本年金機構から委託を受けた民間事業者が、滞納分の保険料を納めるよう電話や個別訪問、郵送などの手段で催促します。
参考:日本年金機構「国民年金未納保険料 納付勧奨通知書(催告状)」
2. 特別催促状
催告状を送付されても支払いに応じない場合は、「特別催告状」が届きます。
特別催告状の封筒の色は3種類に分かれており、青色、黄色、赤色と段階に分けて変化していきます。
青色の封筒では支払いを促す程度の書類ですが、赤色の封筒になると警告に近い内容の書類が届きます。
赤色の封筒である特別催告状を無視し続けると、最悪の場合財産の差し押さえに発展する可能性があります。
催告状は無視せず、しっかりと滞納した保険料を納付することをおすすめします。
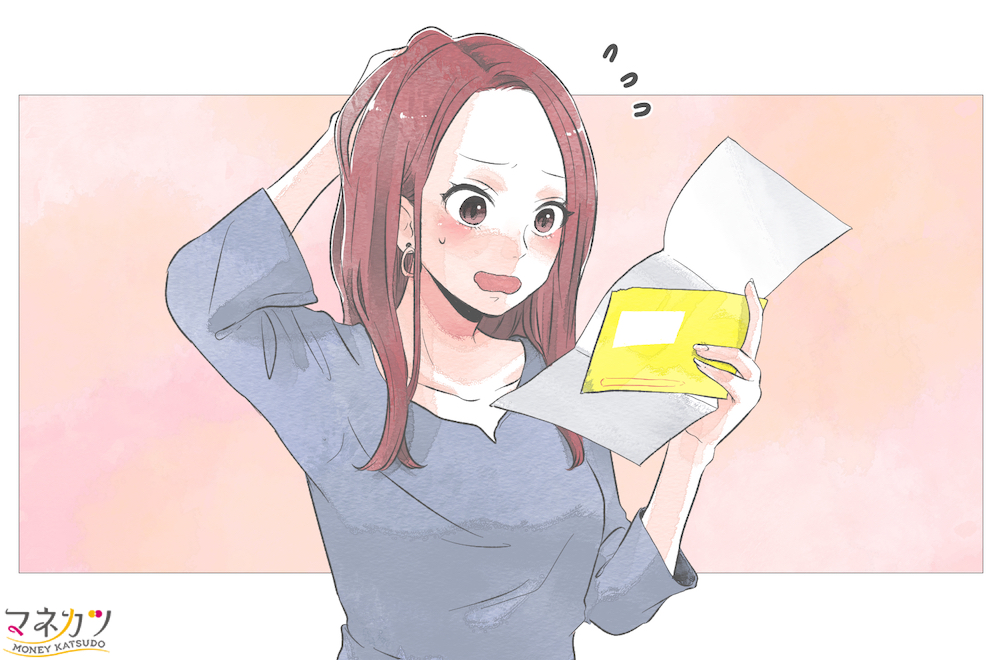
国民年金の特別催告状とは?黄色い封筒が届いた時や払えない場合の対応方法
3. 最終催告状
赤色の封筒の特別催告状が届いても滞納を続ける場合、強制徴収の対象となる「最終催告状」が届きます。
2022年4月時点で強制徴収の対象となるのは、以下の2点を満たす人です。
- 年間所得が300万円以上
- 未納期間が7ヶ月以上
参考:日本年金機構「「国民年金保険料強制徴収集中取組期間」の結果について」
4. 督促状
最終催促状が届いても納付をしなかった場合には、「督促状」が届きます。
期限までに滞納分の保険料を納付しない場合、延滞金が発生します。
延滞金の対象期間は、納期限の翌日から滞納分を納付した前日までです。
督促状に記載のある期限ではなく、納期期限の翌日に遡って適用される点に注意しましょう。
期限までの納付が困難な方は、管轄の年金事務所に「猶予制度」の相談をしてみてください。
5. 差し押さえ予告
督促状の期日を過ぎても納付しない場合には、「差押予告通知」が届きます。
滞納者の財産調査を行い、差し押さえの実行に移ります。
差押予告通知が差し押さえ前の最後の通知です。
6. 差し押さえの実施
差押予告通知が届いても何も対応しない場合、財産の差し押さえが実施されます。
近年、差し押さえの実施件数は増加傾向にあるようです。
| 年度 | 差し押さえ実施件数 |
| 2016年 | 13,962件 |
| 2017年 | 14,344件 |
| 2018年 | 17,977件 |
| 2019年 | 20,590件 |
今後も一定以上の所得がある方には、年金未納による財産の差し押さえが実施されると予想されます。
参考:厚生労働省「日本年金機構の令和元年度業務実績の評価(案)」
年金未納で差し押さえられるもの
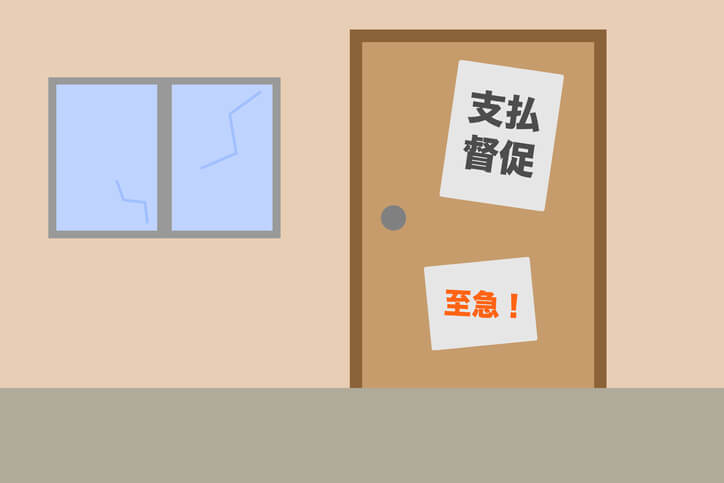
ここでは、差し押さえの対象の代表例について紹介します。
給与や副業所得などの収入
給与やボーナス、退職金、副業所得などの収入は、差し押さえの対象となります。
アルバイトや派遣社員の給与も差し押さえ対象です。
給与は動産(家具や宝飾類など)や不動産と比較すると回収しやすいため、差し押さえされやすい部類になります。
給与の差し押さえには上限額が設定されており、通常は「手取り額の1/4」の金額、手取り給与が44万円を超える場合は手取り額から33万円を差し引いた金額が差し押さえの対象になります。
例えば手取りが20万円の方は5万円が、手取りが50万円の方は17万円が差し押さえられます。
毎月の生活費が手取り額と同額に近い方は、生活に大きな影響が出るでしょう。

【2025年版】安全でおすすめの厳選副業20選!女性向けなど立場別で紹介
預金口座や有価証券
給与と並んで差し押さえの対象となりやすいものが、「預金口座」や「有価証券」です。
預金は普通預金だけではなく、定期預金や当座預金も対象となっています。
差し押さえの限度額を超える部分の給与や年金・生活保護の給付金であっても、預金口座に振り込まれた瞬間からは、銀行に対する預金債権へと変わるため、差し押さえの対象となる可能性があります。

株初心者はいくらから投資を始めるのがおすすめ?少額投資について解説
生活必需品以外
生活必需品以外の動産(不動産以外の形のある財産)は、差し押さえの対象となります。
洗濯機や冷蔵庫などの家電、ベッドや整理タンスなどの家具、衣類などは生活必需品として差し押さえの対象外です。
ただし、上記のものでも複数所有している場合や高級品が含まれているなど、個別の事情によっては差し押さえの対象となります。
住宅などの不動産
家や土地など、動かすことのできない財産である不動産も差し押さえの対象となります。
不動産は資産価値が高いものの差し押さえに手間がかかるため、給与や預金の方が差し押さえされやすいです。
しかし、強制競売によって債権を確実に回収できる見込みがある場合や、他に回収できる資産がない場合は差し押さえの対象となるでしょう。
賃貸に住んでいる場合、借りているお部屋は自身の財産ではないため、差し押さえの対象にはなりません。

「不動産投資はやめとけ」と言われる理由は?やらない方がいい人の特徴
家族の財産も差し押さえの対象
通常の差し押さえであれば、それは本人の債権であるため家族の財産は差し押さえの対象とはなりません。
しかし、国民年金の保険料に関しては、世帯主と配偶者に連帯して保険料を納付する義務が課せられています。
家族が年金滞納を放置していた場合には、家族の財産も差し押さえの対象となる場合があることを留意しておきましょう。
年金未納による差し押さえを回避する方法
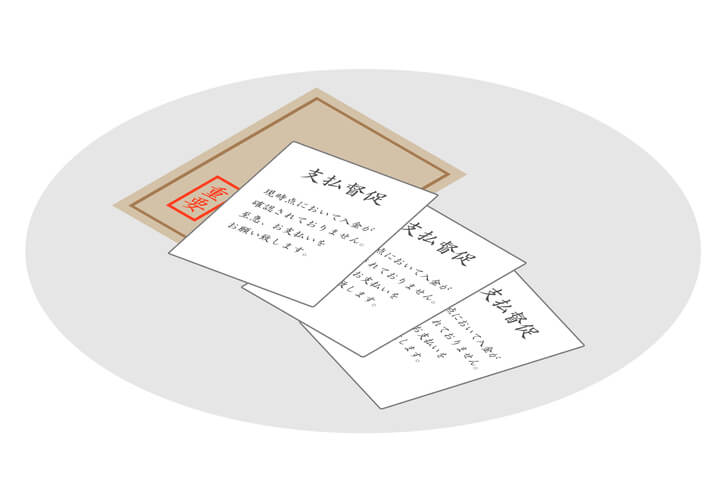
年金の差し押さえが実施されると会社や家族に迷惑をかけてしまったり、財産の差し押さえにより生活がさらに厳しくなることが予想されます。
年金の滞納がある方や支払いが厳しい方は、差し押さえを回避する方法を参考にして対応してください。
少額でも少しずつ返済する
差し押さえられる前の段階、つまり「督促状」が届いた段階までであれば、督促状に記載のある期限を迎える前に年金事務所に相談しましょう。
滞納分の全額一括納付が厳しい場合でも、支払いの意思を告げて少しずつでも返済するようにしてください。
なお、年金事務所への相談は少しでも早いほうが相手の心象もいいため、催告状が届いた段階で相談に行くことをおすすめします。
国民年金の猶予制度/免除制度を活用する
失業した方や所得が低下した方など、経済的な理由から国民年金の保険料の支払いが困難な方もいるでしょう。
そのような方は「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行いましょう。
参考:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
納付猶予
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に納付猶予制度を利用できます。
1月〜6月に申請する場合は、前々年所得が一定額以下であることが求められます。
猶予が認められると受給資格期間にはカウントされますが、老齢基礎年金の受給額には反映されません。
要するに年金支給額が減少してしまうのですが、後から保険料を追納することで老齢基礎年金の受給額に反映されます。
申請免除
所得が少なく、本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下である場合、もしくは失業した場合などに申請できます。
1月〜6月に申請する場合は、前々年所得が一定額以下である必要があります。
免除される額は「全額」「3/4」「半額」「1/4」の4種類です。
免除が認められると、受給資格期間にも老齢基礎年金の受給額にも反映されます。
ただし、受給額への反映は免除された額に応じて異なります。
| 免除額 | 支給額(全額納付と比較して) |
| 全額免除 | 1/2 |
| 3/4免除 | 5/8 |
| 半額免除 | 6/8 |
| 1/4免除 | 7/8 |
免除される金額が大きいほど、老齢基礎年金の支給額は減ります。
コロナの影響で減収した場合も対象
新型コロナウイルスの影響で国民年金保険料の納付が困難になった方を対象にした臨時の特例免除申請があります。
対象者は、令和2年度(2020年)2月以降に、コロナの影響で所得見込額が下がった方です。
所得見込額が以下の計算式で算出された金額以下である場合に申請できます。
| 免除額 | 計算式 |
| 全額免除 | (扶養親族等の数 + 1)× 35万円 + 32万円(※) (※)令和2年度以前は22万円 |
| 3/4免除 | 88万円 (※)+ 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 (※)令和2年度以前は78万円 |
| 半額免除 | 128万円 (※)+ 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 (※)令和2年度以前は118万円 |
| 1/4免除 | 168万円 (※)+ 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 (※)令和2年度以前は158万円 |
参考:日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」
支払いが厳しい場合は相談する
国民年金保険料の支払いが厳しい場合は、年金事務所に相談しましょう。
年金事務所に相談すると、猶予制度や免除制度といった手続きで差し押さえを避けられます。
ただし、当面の生活は守られますが、免除や猶予の期間が長くなると老齢基礎年金の受給額が減少する点には注意が必要です。
まとめ:年金の支払いが難しい場合は差し押さえられる前に相談を

年金の支払いを滞納すると、差し押さえが実施されることがあります。
差し押さえの実施件数は増加傾向にあるため、一定額以上の所得がある方であれば、未納を放置すると財産の差し押さえが行われるでしょう。
年金の支払いを未納のままにしていると催促の通知が届くようになりますが、無視してはいけません。
年金滞納はそのまま放置せず、必ず年金事務所や市役所の担当窓口に相談しに行くようにしましょう。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎
| 年金の関連記事 | |
| 年金問題について | 付加年金とは |
| 年金支給日はいつ? | ねんきんネットとは |
| 年金手帳の提出理由 | 年金手帳紛失時の対応 |
| 特別催告状とは | 年金の差し押さえ |
| 年金の平均受給額 | 基礎年金番号の調べ方 |
| 年金手帳の再発行 | 住所変更の手続き |
| 年金追納のやり方 | |








