【2025】年金支給日はいつ?初回の支給日や手続き方法を徹底解説!
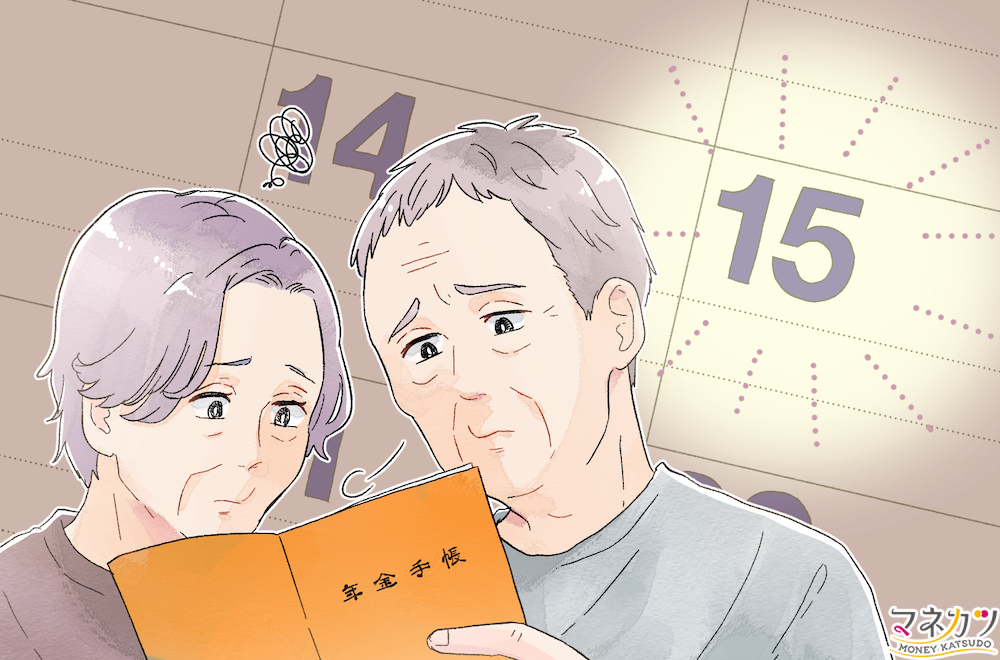
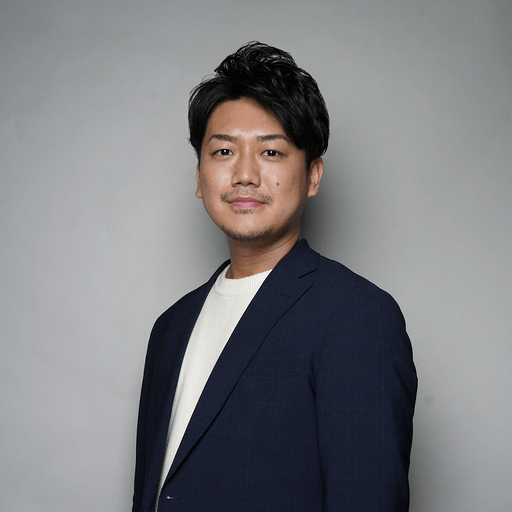
将来の老後プランを考えるうえで、まず知っておきたいのが「年金制度」です。
年金制度についてなんとなく知っていても、「受け取りはまだまだ先のこと」と考えている方も多いのではないでしょうか。
年金は決められた支給日に受け取りますが、毎月支給されるものではありません。
この記事では、年金支給日はいつなのか、初回の支給日や支給日が休日にあたった場合の事例を紹介します。
あわせて知っておきたい年金の請求手続きについても解説しますので、参考にしてください。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎
この記事の目次
年金支給について
日本の公的年金制度は「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金」の2階建て構造です。
かつては「共済年金」と呼ばれる、公務員や私立学校教職員が加入する公的年金制度がありましたが、現在は厚生年金保険に統一されています。
日本国民が受け取ることができる国民年金
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の国民は原則、「国民年金」に加入することになっています。
国民年金の加入者を「被保険者」といい、被保険者は「第1号被保険者」、「第2号被保険者」、「第3号被保険者」の3つに分けられています。
| 国民年金(基礎年金) | 対象者 |
| 第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス、農業者、学生、フリーター、無職など |
| 第2号被保険者 | 会社員・公務員で「厚生年金保険」に加入している人 |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 |
国民年金から受け取れるのは、「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」の3種類です。
| 種類 | 受給要件 |
| 老齢基礎年金 | 65歳以上の人 |
| 障害基礎年金 | 病気やケガが原因で障害を負った人 |
| 遺族基礎年金 | 国民年金の被保険者の遺族となった人 |
上記に該当する方で、受給要件を満たしている場合は年金が支給されます。
保険料を納めた期間や、国民年金の加入者であった期間が一定期間以上ある、などの条件が受給要件です。
会社員や公務員は厚生年金も支給される
会社員や公務員は、「国民年金」と同時に、「厚生年金」にも加入しています。
そのため、国民年金に加えて厚生年金も支給されます。
厚生年金は「老齢厚生年金」「障害厚生年金」「遺族厚生年金」の3種類です。
それぞれの受給要件を満たしている会社員や公務員は、65歳以上になった際に「老齢基礎年金」に上乗せして「老齢厚生年金」も支給されます。
他の年金も同様です。
そのため、自営業者やフリーランスと比較すると、会社員や公務員の年金受給額は多くなります。
年金支給日について

年金保険料納付済期間と保険料免除期間等の合計が10年以上ある人は、原則65歳から老齢基礎年金を受給できます。
この受給資格を満たしたうえで、厚生年金保険に1年以上加入していた人は、同時に老齢厚生年金も受給することが可能です。
受給する年金の金額は、それまでの加入状況によって差が生じます。
しかし年金が支給されるタイミングは決まっていて、受給者は皆、同じ月・同じ日に年金を受け取ります。
年金支給日は原則偶数月の15日
年金が支給される日は、原則「偶数月の15日」と決まっています。
偶数月は2月・4月・6月・8月・10月・12月ですから、支給される回数は年に6回です。一度の支給で2ヶ月分がまとめて振り込まれます。
このときに振り込まれるのは、国民年金や厚生年金だけではありません。
年金には、けがや病気で障害が残ったときに受給できる「障害年金」や、一家の大黒柱が亡くなった際に遺族が受給できる「遺族年金」があります。
これらの年金も、全て同じ日にまとめて支給されます。
2025年(令和7年)の年金支給日カレンダー
2025年の年金支給日は、以下のとおりです。
| 年金支給日 | 支給対象月 |
| 2025年2月14日(金) | 2024年12月・2025年1月の2ヶ月分 |
| 2025年4月15日(火) | 2025年2月・3月の2ヶ月分 |
| 2025年6月13日(金) | 2025年4月・5月の2ヶ月分 |
| 2025年8月15日(金) | 2025年6月・7月の2ヶ月分 |
| 2025年10月15日(水) | 2025年8月・9月の2ヶ月分 |
| 2025年12月15日(月) | 2025年10月・11月の2ヶ月分 |
支給される年金は前月と前々月の2ヶ月分の合算分です。
年金の初回支給日はいつ?

年金支給日は「偶数月の15日」ですが、初回の年金支給日については異なる点があるため注意が必要です。
また、初めて年金が受け取れるのは、年金請求手続きをしてから概ね50日程度後といわれています。
しかし、手続きに時間がかかると初回の振り込みまで3ヶ月以上かかることもあります。
誕生月の翌月から支給対象になる
年金の支給対象となるのは、ほとんどの場合で誕生月の翌月からです。年金の受給資格は65歳の誕生日の前日から発生し、その翌月から支給対象月となります。
たとえば5月生まれの人が65歳になると、翌月の6月から年金の受給対象となり、6・7月分の年金を偶数月の8月15日に受け取ります。
例外として、1日生まれの場合は誕生月から支給対象になります。受給資格が発生するのが誕生日の前日24時、つまり前月であるためです。
たとえば6月1日に生まれた人は6月から年金の受給対象月となり、6・7月分の年金を最短で8月15日に受け取る、ということになります。
初回のみ奇数月に支給されることもある
年金支給日は基本的に偶数月の15日ですが、初回だけは奇数月に支給されることがあります。
初回の年金は手続きが完了した直後の15日に支給されますが、手続きのタイミングによっては偶数月の支給に間に合わないことがあるからです。
実際に年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要になります。
日本年金機構が提出された書類を審査する時間や事務処理をするタイミングによっては、奇数月に振り込まれることもあるようです。
たとえば1月2日生まれの人の場合は、スムーズにいけば2・3月分の年金を4月15日に受け取れます。
しかし、年金事務所側で4月の振り込み手続きに間に合わなければ、2・3月分の年金を5月15日に振り込むこともあるようです。
出典:日本年金機構「初めて年金の支払いを受けましたが、これはいつからいつまでの分ですか。」
年金支給日が土日祝の場合

直前の平日に振り込まれる
年金の支給は通常、偶数月の15日に行われます。
しかし、年金支給日が土日祝日に該当する場合は、振り込まれるのは15日の直前の平日となります。
たとえば15日が土曜日なら直前の平日である14日の金曜日に、15日が日曜日の場合は直前の平日である13日の金曜日に支給されます。
同様に、15日が祝日の場合も、その直前の平日に支給されます。
15日付けの年金入金が確認できなかったと思っても、よく見ると13日や14日付けで入金されているケースもあるので、入金履歴を確認する際は覚えておきましょう。
振込は金融機関の営業開始時間まで
年金が振り込まれるのは年金支給日と決まっていますが、実際に年金が口座に入金される時間は金融機関によって異なります。
銀行ごとの振り込み処理の状況によっても前後するため、明確に「何時に振り込まれる」という決まりはありません。
しかし、ほとんどの金融機関においては、営業開始時間には引き下ろせる状態になっているようです。
多少遅れたとしても、通常は午前中には入金されているのが一般的のようです。
年金を受け取るための手続き
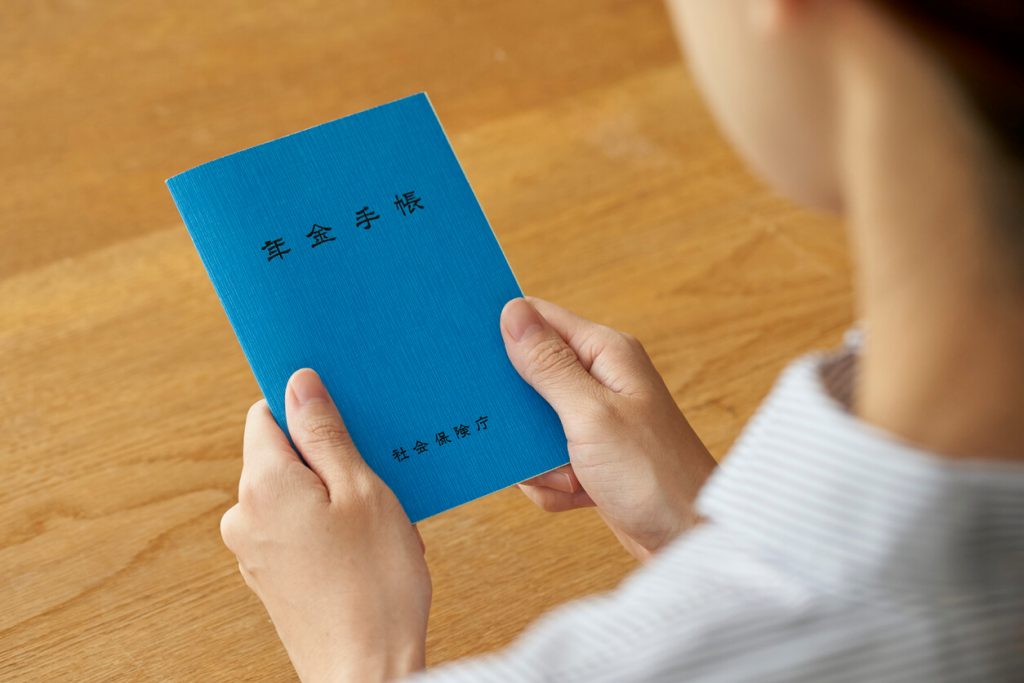
年金を受け取るためには「年金請求書」を記入し、必要書類を添付して送付する手続きが必要です。
年金を受け取る権利が発生した後も年金を請求しないまま5年が経過すると、時効となって消滅してしまいます。
請求漏れがないように、以下の流れで手続きをしましょう。
「年金請求書」を記入する
受給開始年齢に達して受給権が発生すると、受給開始年齢になる3ヶ月前に日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。
送付されてくる年金請求書には、基礎年金番号・氏名・生年月日・性別・住所・年金加入記録が事前に印字されています。
請求手続きの案内も同封されているため、確認しながら手続きを進めましょう。
まずは年金請求書に記載されている年金加入記録の内容に誤りがないかを確認します。万が一漏れや誤りがあれば、年金事務所に問合せをしてください。
問題がなければ、住所・フリガナ・電話番号・受取口座・年金の加入状況・受給状況・家族状況などの必要事項を記入します。
住所欄は原則として住民票住所になっていますが、例外的に他の住所を通知書等送付先とすることも可能です。その際には別途、書類が必要になります。
必要書類と一緒に「年金請求書」を提出する
年金請求者の状況により必要書類は異なりますが、年金請求に必要な添付書類には以下のようなものがあります。
- 戸籍謄本
- 年金受け取り用口座の通帳
- 住民票(世帯全員)
- 年金手帳
- 年金加入期間確認通知書
- 雇用保険被保険者証 など
戸籍謄本や住民票などの添付書類は、受給権が発生した日以降に発行されたもの、且つ年金請求書を提出する日の6ヶ月前以降に交付されたものを用意します。
請求者の厚生年金加入期間や配偶者と子の状況によっては、世帯全員の住民票の写し・請求者や配偶者の収入がわかる書類が必要になります。
また、個々の状況に応じて、年金手帳・雇用保険被保険者証・年金加入期間確認通知書・年金証書などを添付します。詳しくは日本年金機構からの案内やホームページを確認してください。
書類を提出するタイミングは、受給開始年齢の誕生日の前日以降です。受給権が発生する前に提出しても受け付けてもらえないので注意しましょう。
年金請求書の送付先は、お近くの年金事務所か街角の年金相談センターです。年金事務所の窓口に直接提出することもできます。
出典:日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き」
年金証書・年金決定通知書を受け取る
年金請求書を提出すると、1~2ヶ月後に「年金証書・年金決定通知書」が届きます。
年金証書の上部には年金の種類・基礎年金番号・年金コードや受給権取得年月が記載されています。
年金決定通知書部分には、年金額や保険料納付済期間等の内訳など、詳細な情報が記載されているので、届いたら内容をしっかり確認するようにしてください。
年金証書は年金受給者の身分証明書といえるくらいに大切なものです。
受け取り開始後に届け出をする際にも必要となります。なくさないように保管しておきましょう。
年金振込通知書が届いたら年金が支給され始める
年金証書・年金決定通知書が届いてから1~2ヶ月後には、「年金振込通知書」が届き、年金の支給が始まります。
年金振込通知書には年金振込額以外に、年金から天引きされる各種保険料の明細や税額も記載されています。ひととおり目を通すようにしてください。
その後も原則として年1回、6月に年金振込通知書が送付されるので、支払日ごとの詳細を毎年確認するようにしましょう。
年金受給者が死亡してしまった場合に必要な手続き
年金受給者が亡くなると、公的年金を受給する権利を失います。
遺族は「受給権者死亡届(報告書)」を提出し、年金の支給を停止しなければなりません。
この手続きをせずに遺族が年金の受給を継続すると、不正受給とみなされる可能性があるため、必ず手続きを行いましょう。
日本年金機構にマイナンバーを登録している場合は、原則として「年金受給権者死亡届(報告書)」の省略ができます。
未支給年金を受給するための手続き
年金は、偶数月に2ヶ月分がまとめて振り込まれるため、年金受給者が亡くなった時点で受け取れていない年金があります。
例えば、2023年の4月20日に亡くなった場合、2023年4月までの年金を受給する権利があります。
本来であれば、2023年4月分の年金は6月15日に受給できますが、亡くなっているため受給できません。
この受け取れていない年金を「未支給年金」といい、一定の条件を満たす遺族が手続きをすると受給できます。
偶数月に亡くなった場合は1ヶ月分、奇数月に亡くなった場合は2ヶ月分の年金額を請求できます。
手続きが可能な遺族は、年金受給者と生計を同じくしていた3親等内の親族です。
一緒に住んでいたり、離れて住んでいても仕送りなど経済的援助がある場合、生計を同じくしていたと認められます。
必要な手続きは「未支給年金・未支払給付金請求書」、「亡くなった方の年金手帳、基礎年金番号通知書または年金証書」の提出です。
手続きの詳細については、年金事務所にお問い合わせください。
参考:厚生労働省「市町村向け 業務支援ツールのダウンロードページ」 ●死亡を原因とした給付【未支給年金】お手続きガイド—
年金ダイヤルとは?つながらないときの対処法や注意点について解説
まとめ:年金支給日に受け取るための準備をしておこう!

年金の支給日は偶数月の15日です。
ただし、偶数月の15日が土・日・祝日の場合、振り込みは直前の平日になります。
また、初回の年金支給には1〜3ヶ月ほどかかることもあるので、時間に余裕を持って申請するよう注意が必要です。
年金支給開始前の生活資金には、一定の余裕をもたせておいたほうがやきもきせずに済むでしょう。
年金を受け取るには請求手続きが必要です。年金を受給できる権利が発生したら、速やかに手続きをして受給漏れがないよう気をつけてください。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎
| 年金の関連記事 | |
| 年金問題について | 付加年金とは |
| 年金支給日はいつ? | ねんきんネットとは |
| 年金手帳の提出理由 | 年金手帳紛失時の対応 |
| 特別催告状とは | 年金の差し押さえ |
| 年金の平均受給額 | 基礎年金番号の調べ方 |
| 年金手帳の再発行 | 住所変更の手続き |
| 年金追納のやり方 | |








