ドルコスト平均法のメリット・デメリット!やり方やシミュレーション


記事監修者
マネカツ編集部
"将来への漠然としたお⾦への不安はあるけど、何から始めていいのかわからない…"
そんな方に向けて「資産運用」や「税金対策」など、お金に関する情報を発信しています。

記事監修者
マネカツ編集部
"将来への漠然としたお⾦への不安はあるけど、何から始めていいのかわからない…"
そんな方に向けて「資産運用」や「税金対策」など、お金に関する情報を発信しています。
株や投資信託に投資する際、投資手法を間違えると大きなリスクを抱えてしまう可能性があります。
「どの投資先を選ぶか」だけでなく、「どういった投資手法でリスクを抑えるか」という点も重要です。
投資にはリスクがつきものですが、ドルコスト平均法の考え方を身につけることで、損失リスクをある程度抑えることができます。
この記事では、リスクを抑えて運用できる代表的な投資手法「ドルコスト平均法」の特徴やメリット・デメリットについて解説します。
ドルコスト平均法は積立NISAにも取り入れられている手法なので、仕組みを理解して投資を楽しみましょう。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎
この記事の目次
ドルコスト平均法とは

「ドルコスト平均法」とは、金融商品を一定金額で定期的に買い付ける方法です。
同じ金額で買い付けるため、価格が安い時には購入する数量が多くなり、価格が高い時には購入する数量が少なくなります。
例えば、ドルコスト平均法で毎月3万円ずつ株を購入した場合を考えましょう。
株価が1万円の時に購入する株数は3株ですが、翌月に株価が5,000円に下落すると購入株数は6株に増えます。
逆に株価が15,000円に値上がりした場合は、購入株数は2株に減ります。
投資するタイミングを分散させることで金融商品の価格変動リスクも抑えられるため、長期的な資産形成におすすめの投資手法です。
ドルコスト平均法のメリット

平均購入単価を抑えられる
すでにご紹介した通り、ドルコスト平均法は価格が安い時に多く買い、高い時には少なく買うという投資手法です。
そのため平均購入単価を抑えられ、購入口数が増えやすいという点がメリットとなります。
例えば、1株1万円の株に100万円を一括投資する場合と、10万円ずつドルコスト平均法で投資する場合で考えてみましょう。
| 株価 | 最初に100万円投資 (一括投資) | 毎月10万円投資 (ドルコスト平均法) |
| 1ヶ月目/10,000円 | 100株 | 10株 |
| 2ヶ月目/15,000円 | – | 6.6株 |
| 3ヶ月目/12,500円 | – | 8株 |
| 4ヶ月目/10,000円 | – | 10株 |
| 5ヶ月目/8,000円 | – | 12.5株 |
| 6ヶ月目/4,000円 | – | 25株 |
| 7ヶ月目/5,000円 | – | 20株 |
| 8ヶ月目/8,000円 | – | 12.5株 |
| 9ヶ月目/10,000円 | – | 10株 |
| 10ヶ月目/10,000円 | – | 10株 |
| 合計株数 | 100株 | 124.6株 |
10ヶ月で上記のような値動きをした場合、100万円を一括で投資した場合は3ヶ月目まで大きな利益になったものの、その後の下落では損失を大きくし、最終的には元の価格に戻ってきてプラスマイナス0でした。
一方で毎月10万円ずつ投資をしていた場合、株価が上昇したら少なく、下落したら多くの株数を購入していることがわかります。
10ヵ月後は投資開始時と同じ株価1万円ではあるものの、ドルコスト平均法の方が10ヶ月で購入できた株数が多くなっており、評価額もプラスになります。(平均購入単価が安くなっているため)
短い期間では一括投資に及ばないものの、投資期間が長くなるほど有利になりやすいのが、ドルコスト平均法の特徴です。
投資の手間がかからない
ドルコスト平均法は、金融商品を「定期的に」「定額で」買い付ける投資手法です。
多くの証券会社では定期買付の設定が可能であるため、一度設定してしまえばその後手間をかけずに投資を継続できる点がメリットです。
通常、株を売買する際には株価をチェックしたり、業績・決算情報を確認したりと手間がかかるケースは少なくありません。
しかし、ドルコスト平均法は株価の変動に関係なく機械的に銘柄を買い続ける手法であるため、定期買付の設定さえしてしまえば株価やニュースのチェックは不要です。
忙しくて投資に時間を使えないという方でも始めやすい点は、ドルコスト平均法の大きな魅力と言えるでしょう。
機械的に投資を続けられる
投資の失敗で多いのが「感情に左右されて売買してしまう」というケースです。
「もう少し株価が安くなるかも」と考えて購入するタイミングを失ったり、「これから株価が上がるはず」と考えて損失が拡大していったりするパターンです。
先程の一括投資とドルコスト平均法の比較を例に出すと、一括投資は6ヶ月目で100万円が40万円(-60万円)になってしまっているため、これ以上の損失を避けるために売ってしまう可能性も考えられるでしょう。
しかし、ドルコスト平均法は機械的に積立投資を継続するため、株の値動きに感情を左右されずに投資を続けられます。
多少相場が動いても平均購入単価を抑えて買い付けられることから、値動きに一喜一憂する必要もありません。
感情が邪魔をして損をするというケースを防げる点は、大きなメリットと言えるでしょう。
投資を始めるタイミングに悩まなくていい
投資を始める際に「今はまだ高値ではないか」「もっと安くなるのではないか」と悩んでしまい、なかなか始められないというケースは多くあります。
しかし、ドルコスト平均法では仮に始めたタイミングが高値であっても、その後下落した時に多くの数量を購入できます。
タイミングに迷わずに始められる点が、ドルコスト平均法のメリットです。
もちろん、高値のタイミングで始めた場合は、短期的に損をする可能性は十分にあります。
しかし、5年・10年の長い目で見れば短期的な値動きは誤差であるため、現在の価格を気にせず投資を始めて問題ありません。
投資用のまとまった資金が不要
ドルコスト平均法を活用した投資では、毎月一定額を積み立てて投資をしていきます。
そのため、一度にまとまった資金を用意しなくても投資を始めることが可能です。
例えば投資信託であれば、金融機関や商品によっては100円から積み立てることができます。
数十万円〜数百万円の資金を用意する必要がないため、少額から気軽に始められます。
「いきなり大金を投資に使うのは怖い」という方でも比較的始めやすい点が、ドルコスト平均法のメリットです。
ドルコスト平均法のデメリット

短期的に大きな利益は期待できない
ドルコスト平均法は、時間を分散させることでリスクを低減させる投資手法として人気ですが、一方で短期的には大きなリターンになりにくい点がデメリットとして挙げられます。
安定したリターンは得られるものの、すぐに大きな利益を狙いに行きたい人には向かない手法です。
例えば、株価が右肩上がりに伸びている局面では、分散投資をするよりも安値で一括購入して高値で売却した方が大きなリターンを得ることができます。
もちろん、その分抱えるリスクも大きくはなりますが、一括投資の方が大きな利益を得るチャンスは大きくなります。
リスクを抑えることにより高い確率で安定した利益を狙える一方で、短期的に大きな利益を狙いたい方には合わない投資手法といえます。
狙ったタイミングで投資できない
投資をしていると相場が急落することがあり、「いま株を買いたい」と考えるタイミングが多くあります。
しかし、ドルコスト平均法は買い付けのタイミングを気にせずに定期的に購入する手法であるため、自分の好きなタイミングで投資することはできません。
定期買付のルールを破って自分のタイミングで株を購入してしまうと、「機械的に運用ができる」というメリットが損なわれてしまいます。
相場が急落して「いま買いたい」と感じた場合は、ドルコスト平均法で積み立てている資金とは別で株を買いましょう。
長期投資が必要
ドルコスト平均法は、平均購入単価を抑えながら長期間にわたって資産を積み立てることで効果を発揮する投資手法です。
そのため、5年・10年という長い期間で投資を継続しなければならない点がデメリットと言えるでしょう。
短期的には、値動きが大きい銘柄に一括投資をした人にリターンで劣る可能性もあります。
「ほかの投資手法よりもリターンが劣る局面を我慢できない」「短期的にリターンを狙いたい」という方は、ドルコスト平均法を活用した投資は向いていません。

長期投資のメリット・デメリット!おすすめの投資方法を解説
一括投資と比べて手数料がかかる可能性がある
ドルコスト平均法は定期的に株などを買い付ける手法であるため、購入の度に手数料がかかります。
一括投資をする場合と比べて手数料が高くなってしまう可能性がある点に注意が必要です。
例えば、楽天証券の超割コースで株式投資をする場合、100万円の売買手数料は535円、10万円の売買手数料は99円となっています。
100万円を一括投資すれば手数料は535円ですが、10万円を10回に分けて投資をすれば990円の手数料がかかります。
買い付けの回数が多くなる分手数料が高額になってしまうため、なるべく手数料が安い証券会社を利用しましょう。
ドルコスト平均法のシミュレーション

ドルコスト平均法で投資した場合と、一括投資をした場合を比べてみます。
例として、投資資金12万円で投資信託を購入するケースを考えてみましょう。
12万円を一括投資する場合と、毎月1万円ずつ12ヶ月に分けてドルコスト平均法で投資をする場合でそれぞれシミュレーションしてみます。
一括投資の場合
12万円を一括投資する場合、購入価格や購入口数は以下のようになります。
| 期間 | 購入価格 | 購入口数 | 投資金額 |
| 1ヶ月目 | 100円 | 1,200口 | 120,000円 |
最初の投資タイミングですべての資金を購入するため、そのときの投資信託の価格がそのまま購入単価となります。
この場合は、投資信託が100円のときに12万円分の資金を投入しているため、1,200口分の投資信託を購入できる計算です。
ドルコスト平均法の場合
一方、ドルコスト平均法では毎月定額(今回は1万円)を積み立てていく方法なので、投資信託の価格変動に応じて、購入できる口数が以下のように変化します。
| 期間 | 購入価格 | 購入口数 | 投資金額 |
| 1ヶ月目 | 100円 | 100口 | 10,000円 |
| 2ヶ月目 | 200円 | 50口 | 10,000円 |
| 3ヶ月目 | 50円 | 200口 | 10,000円 |
| 4ヶ月目 | 100円 | 100円 | 10,000円 |
| 5ヶ月目 | 150円 | 66口 | 10,000円 |
| 6ヶ月目 | 80円 | 125口 | 10,000円 |
| 7ヶ月目 | 100円 | 100口 | 10,000円 |
| 8ヶ月目 | 60円 | 166口 | 10,000円 |
| 9ヶ月目 | 120円 | 83口 | 10,000円 |
| 10ヶ月目 | 70円 | 142口 | 10,000円 |
| 11ヶ月目 | 140円 | 71口 | 10,000円 |
| 12ヶ月目 | 100円 | 100口 | 10,000円 |
| 合計 (平均) | 約92円 (平均購入単価) | 1,303口 | 120,000円 |
毎月の投資金額は一定でも、価格の変動に合わせて購入できる口数が異なります。
価格が下がっている月は購入口数が増え、価格が上がった月は購入口数が減っていることがわかるでしょう。
投資金額の合計12万円をトータルの購入口数1,303口で割ると、平均購入単価は約92円となりました。
ドルコスト平均法で購入タイミングを分散させることで、一括投資よりも安く・多く投資信託を購入できた良い例といえます。
ドルコスト平均法の注意点
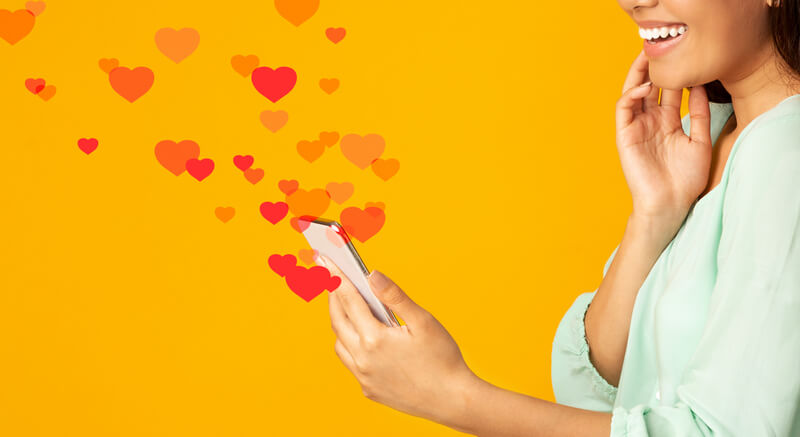
短期的な値動きに一喜一憂しない
ドルコスト平均法は、短期的な値動きでリターンを取りに行く手法ではなく、5年・10年という長期間を見越して投資する手法です。
そのため、短期的な相場の値動きに一喜一憂せず、淡々と積立投資を継続することが重要となります。
投資をしていると暴落相場を経験することが多々ありますが、長い目で見れば短期的な下落は誤差の範囲であることがほとんどです。
もし暴落が来ても、評価額が下がったことを落ち込むのではなく、「安く銘柄を買えてラッキー」という感覚で投資を継続しましょう。
株価指数向きの投資方法
ドルコスト平均法は、短期的な上昇や下落を繰り返しながらも、長期的には右肩上がりに上昇する銘柄と相性が良い投資手法です。
そのため、個別株よりも株価指数の方がドルコスト平均法との相性が良いと考えられます。
個別株の場合、大きな成長に期待が持てる一方で、10年・20年という単位で見ると将来的に失速している可能性があります。
日本の「日経平均株価」やアメリカの「S&P500」などは、国の経済成長に伴って右肩上がりに成長するという期待が高いため、ドルコスト平均法でリターンを得られる可能性も高いです。
ドルコスト平均法を活用して投資する際には、今後も成長が期待できる国の株価指数に投資することをおすすめします。

S&P500をわかりやすく解説!人気の投資信託やETFも紹介
元本割れのリスクは伴う
平均購入単価を抑えられたり、高値掴みを避けられたりするなど、メリットが多いドルコスト平均法ですが、完璧な投資手法ではありません。
投資である以上、元本割れをしてしまうリスクがある点には注意が必要です。
もちろん、10年・20年という単位で長期投資をすればリスクは低減できますが、売却を予定しているタイミングで大暴落が来る可能性も考えられます。
例えば積立NISAは最長20年間を非課税で投資できる制度ですが、20年目にリーマンショックのような暴落が来てしまうこともありえるでしょう。
ドルコスト平均法に限らず投資を始める際には、元本割れのリスクがある点を十分に留意しておきましょう。
まとめ:ドルコスト平均法でリスクを軽減した投資を楽しみましょう

ドルコスト平均法を利用して投資をすると、投資するタイミングが分散されることでリスク低減効果が得られます。
手間をかけず機械的に投資を継続できるため、日々値動きを確認できない忙しい人でも始めやすいでしょう。
一括投資に比べて短期的に大きなリターンは望めないものの、長い時間で見ればリスク少なく着実に資産を増やしていきやすいです。
将来に向けた資産運用のために投資を始めたい方は、ドルコスト平均法を活用して堅実に資産を増やしていきましょう。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎
| 投資の関連記事 | |
| 株式投資の始め方 | 従業員持株会とは |
| 投資で生活可能? | 配当金で生活できる? |
| 自社株買いとは | 空売りとは |
| 10万円以下の株主優待 | 高配当株のメリット |
| 投資はいくらから? | モメンタム投資とは |
| 投資の種類 | 分散投資とは |
| 長期投資の効果 | コアサテライト戦略 |
| 複利の効果 | アセットアロケーション |
| ポイント投資の特徴 | 株主総会とは |








