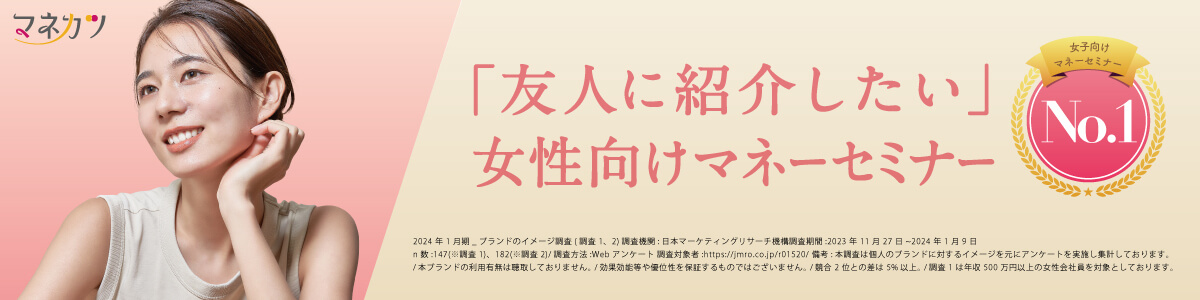NISA積立は「毎日」と「毎月」どっちがおすすめ?検証結果を解説

NISAには、積立投資を行うための「つみたて投資枠」が設けられています。
一般的には「毎月」の積立を行うケースが多いものの、設定によって「毎日」の積立を行うことも可能です。
「毎日」と「毎月」の積立ではどちらの方が効果的になるのかを検討し、効率的な資産運用を目指しましょう。
この記事では、新しいNISA制度の概要や毎日と毎月の積立シミュレーション、NISAでの重要なポイントを詳しく解説します。
新しいNISA制度のメリット・デメリットもご紹介するので、参考にしてください。
\現在開催中の無料セミナーはこちら/
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】
オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎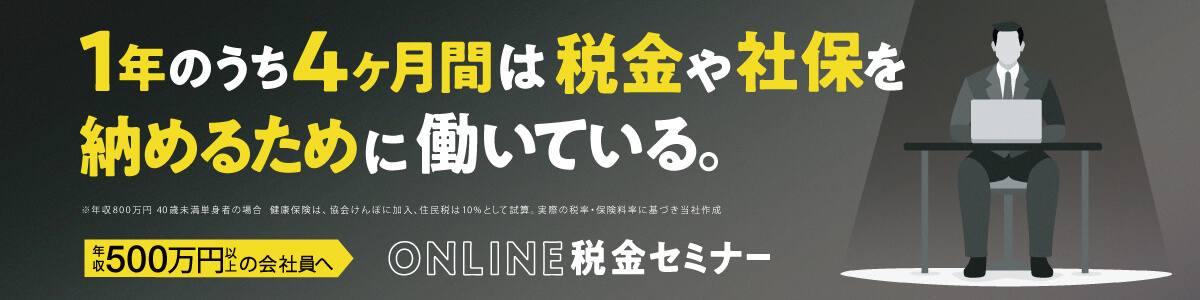
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?
人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎
この記事の目次
NISAの仕組み

NISAとは年間一定額までの投資で得た利益に、税金がかからなくなる制度のことで、「少額投資非課税制度」とも呼ばれます。
本来、株式や投資信託などから得られた利益には20.315%の税金がかかります。
しかし、NISAを使うと制度の範囲内での取引については利益や配当金が非課税になる仕組みです。
ここでは、NISAの概要について解説します。
2024年から新NISA制度が始まった
2014年1月からスタートしていたNISA制度が、2024年1月から「新しいNISA」として生まれ変わりました。
以前の「一般NISA」、「つみたてNISA」は、新しいNISAで「成長投資枠」、「つみたて投資枠」という名称に変更されています。
年間投資枠は一般NISAが120万円、つみたてNISAが40万円だったのに対し、新しいNISAでは成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円に引き上げられました。
また、つみたて投資枠と成長投資枠の2つの非課税投資枠を併用できるようになったり、非課税で運用できる期間が無期限化されたりといった点も新NISAで大きく変更された点です。
これまでより自由度の高い資産運用が可能になったことが新NISAの強みとなっています。
なお、2023年末までに旧NISA制度の口座を開設していた場合、同じ金融機関で新NISA口座が自動で開設されるため、新NISAにともなう手続きは必要ありません。
参考:金融庁「NISAを知る」

新NISAとは?変更点やいつからか、積立NISAと比べて解説
新NISAの「つみたて投資枠」では積み立て投資が可能
前述の通り、新しいNISAでは「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2つの非課税投資枠があります。
成長投資枠・つみたて投資枠の特徴は以下の表の通りです。
| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
| 年間投資枠 | 240万円 | 120万円 |
| 非課税保有限度額(総枠) | 1,200万円 | 成長投資枠と合わせて1,800万円まで(つみたて投資枠のみで1,800万円も可) |
| 投資対象商品 | 上場株式・投資信託・ETFなど | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 |
成長投資枠では上場株式や投資信託、ETFなどの商品に幅広く投資できますが、つみたて投資枠の投資対象商品は金融庁の基準を満たした一定の投資信託に限られます。
つみたて投資枠は積立投資を対象とした制度であるため、原則として投資信託の積立を行うこととなります。
金融庁が定めた条件をクリアしている投資信託で、比較的リスクの低い積立投資を実践できる点が「つみたて投資枠」の特徴です。
積立頻度は「毎日積立」「毎週積立」「毎月積立」から選べる!

通常、積立投資の頻度は「毎月」が一般的ですが、必ずしも「毎月」にしなければならないわけではありません。
証券会社によっては「毎月」「毎週」「毎日」などさまざまな頻度での積立設定が可能です。
積立投資では、自分が設定した日に対象商品の買い付けが行われます。
たとえば「毎月」で「1日」の購入設定をした場合、1月から12月までの年12回、毎月1日に商品を買い付ける仕組みです。
毎週積立であれば指定した曜日、毎日積立は土日・祝日などを除く毎営業日に積立が行われます。
毎日積立と毎月積立、どっちが有利?

過去のデータからは、長期投資であれば「毎日積み立てる人」も「毎月積み立てる人」も同じような結果が見込まれています。
長期的に積立を継続するのであれば、頻度は毎日・毎月のどちらを選んでも良いでしょう。
毎日積立は買い付けのチャンスを逃すことがないため、毎月積立に比べると少し有利に働く可能性があります。
とはいえ、積立の頻度を気にしてわずかなリターンの差を狙うよりも、長期間にわたって投資を継続し続けることが重要です。
毎日積立と毎月積立よりも重要なポイント

シミュレーションの結果、積立NISAでは積立頻度が「毎日」でも「毎月」でも最終的な利益はほとんど変わりませんでした。
積立NISAの最終的な利益には「銘柄選び」と「保有期間」の2点が大きく影響を与えます。
ここでは、積立NISAでしっかりと利益を狙うために重要なポイントである「銘柄選び」「保有期間」について解説します。
銘柄をしっかり選ぶこと
新しいNISAの「つみたて投資枠」で投資できる銘柄は、金融庁の基準を満たした「長期・積立・分散」投資に適している銘柄に限定されています。
これにより、基本的には極端に大きなリスクを抱えることは避けられますが、その中でも自分の投資スタイルに合った銘柄を選ぶことが大切です。
銀行や証券会社で人気の商品が必ずしも自分に適しているわけではありません。自分の運用目的やリスクの許容度に合わせて投資する銘柄を選びましょう。
【2024】積立NISAのおすすめ銘柄10選!組み合わせや楽天・SBIの銘柄を紹介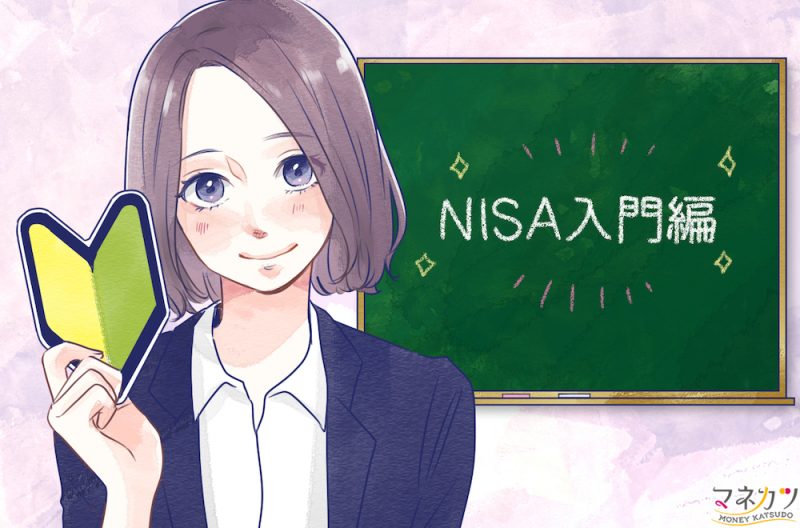
長期運用すること
積立NISAを始めるにあたって、長期運用をすることがとても大切です。
長期投資のメリットは主に以下の4点です。
- 複利効果を見込める
- 短期投資に比べて低コスト
- 時間や精神的な負担が少ない
- リスクをコントロールしやすい
ほとんどの銘柄が価格の上昇と下落を繰り返します。
長期的に見ると右肩上がりの銘柄であっても、短期で見ると下落していることも珍しくありません。
そのため、10年、20年と長期的に考えて成長が見込める銘柄を購入し、長く保有する意識を持つとよいでしょう。

長期投資のメリット・デメリット!おすすめの投資方法を解説
NISA(つみたて投資枠)のメリット・デメリット

新NISAにおける「つみたて投資枠」は、旧NISA制度のつみたてNISAを引き継いだ非課税投資枠です。
この枠のメリット・デメリットを把握し、つみたて投資枠を最大限に活用しましょう。
投資の手間がかからない
「つみたて投資枠」では、最初に積立設定をするだけで、そのまま自動で投資信託が購入されます。
毎月・毎日などの頻度自動積立が継続されるため、市場の値動きを気にする必要がなく、投資の判断や手間が多くかからない点が大きなメリットです。
また、定期的に同じ金額分の買い付けを行うことで「ドルコスト平均法」の恩恵を受けられる点もメリットとして挙げられます。
ドルコスト平均法とは、定期的に一定額を買い続けることで、価格が高いときには少なく、安いときには多く買える仕組みのことです。
全体的な平均購入単価が抑えられるため、長期的な資産形成に有効な手段だといわれています。
手続きがシンプルで、平均購入単価を抑えながら、安定的な運用を期待できる点が「つみたて投資枠」のメリットとして挙げられます。

ドルコスト平均法のメリット・デメリット!やり方やシミュレーション
一括投資ができない
「つみたて投資枠」は主に積立投資を対象とした制度であり、対象商品も長期の積立分散投資に適した投資信託に限られます。
毎月・毎日といった頻度での定期的な買い付けを基本としているため、自分の好きなタイミングで一括投資ができない点がデメリットになるでしょう。
例えば、株価が下落したタイミングで投資信託を一括購入すれば、その後の株価上昇時には大きなリターンが期待できます。
しかし、つみたて投資枠ではタイミングを狙った一括投資が基本的にできないため、大きなリターンを狙った戦略が難しいといえます。
ただし、特定の月に投資金額を増額する「ボーナス積立」という方法を活用すると、一括で投資することも可能です。

【2024】NISAは一括購入できる?一気に買う方法やSBI証券・楽天証券でのやり方
投資できるのは一定の投資信託のみ
繰り返しとなりますが、NISA口座の「つみたて投資枠」で投資できるのは金融庁の基準を満たした一定の投資信託のみとなっています。
限られた選択肢の中から投資商品を選ぶ必要があるため、つみたて投資枠の対象外となっ商品に投資したい方にとってはデメリットになるでしょう。
なお、「成長投資枠」では投資信託に加えて上場株式やETFといった金融商品への投資が可能です。
より幅広い選択肢の中から商品を選びたいという方は、成長投資枠の活用を検討しましょう。
NISA(成長投資枠)のメリット・デメリット

「成長投資枠」は、旧NISA制度における「一般NISA」を引き継いだ非課税投資枠です。
つみたて投資枠とは違った制度であるため、メリットやデメリットを把握して有効活用しましょう。
年間240万まで一括・積立で投資できる
成長投資枠には年間240万円までの非課税枠があり、一括・積立のどちらでも投資可能です。
つみたて投資枠に比べて自由な運用が可能である点がメリットとして挙げられます。
例えば「つみたて投資枠で積み立てている投資信託を、成長投資枠で上乗せして投資する」といった使い方ができます。
また、株価の下落時を狙った一括投資も可能です。
自分の好きなタイミングで自由に取引を行える点が成長投資枠の大きなメリットです。
つみたて投資枠よりも幅広い商品に投資できる
つみたて投資枠では、購入できる商品が金融庁の基準を満たした一定の投資信託に限られますが、成長投資枠では投資信託だけではなく上場株式、ETFなどに投資ができます。
個別銘柄のIPOや外国株式なども購入でき、幅広い商品へ投資ができるのがメリットです。
ただし、上場株式・投資信託であれば無制限に投資できるわけではありません。
信託期間20年未満の投資信託や毎月分配型の投資信託、整理銘柄・管理銘柄などには投資できない点に注意が必要です。
また、金融機関ごとに取り扱っている金融商品が異なります。
NISA口座を開設する際は購入したい商品を取り扱っている金融機関を選ぶことで、自分の投資目的やニーズに合った運用ができるでしょう。
参考:日本証券業協会「NISAの3つのいいさ! | 「みんなにいいさ!NISAがいいさ!!」」
自分で判断すべき場面が多い
成長投資枠は選べる商品のラインナップが多く、売買のタイミングも自由に選べる分、つみたて投資枠と比較すると自分で判断しなければならない場面が多いです。
投資初心者の方にとっては、これが少しハードルに感じる方もいるかもしれません。
新しいNISA制度になってからは非課税期間が無期限化されたため、売却のタイミングを見極める重要性が高まっています。
自分の中で目標リターンを定めて「目標を達成したら売却する」といったルールを決めておくことが大切です。
なお、複雑な判断を減らしたい場合は「つみたて投資枠で積み立てている投資信託と同じ商品を、成長投資枠で上乗せして投資する」という方法もあります。
自分の投資経験や運用目的に合わせ、成長投資枠を有効活用しましょう。
まとめ:「毎日」も「毎月」も長期運用ではあまり変わらない

この記事では、新しいNISAの「つみたて投資枠」における積立の頻度を「毎日」「毎月」とした場合のシミュレーションを解説しました。
積立を開始して数ヶ月で売却する場合にはその数ヶ月間の相場変動によって、毎日積立と毎月積立で結果に大きな差がでることも十分あり得ます。
しかし、数年、数十年と長期で運用することによって利益は平準化されるので、積立頻度による差は小さくなります。
長期での運用が前提となっている「つみたて投資枠」なら、積立頻度にこだわるよりも、毎日と毎月、自分はどちらの方が管理しやすいかで決めることがおすすめです。
毎日・毎月のどちらであっても長期運用においてはリターンの差がわずかであり、そこまで重要な問題ではありません。
銘柄をしっかりと選び、長期的な運用を継続することが重要です。
また、新しいNISA制度の「つみたて投資枠」「成長投資枠」にはそれぞれ異なるメリット・デメリットが存在します。
特徴を正しく把握し、2つの非課税枠を最大限に活用して効果的な資産運用を実現しましょう。
\現在開催中の無料セミナーはこちら/
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】
オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎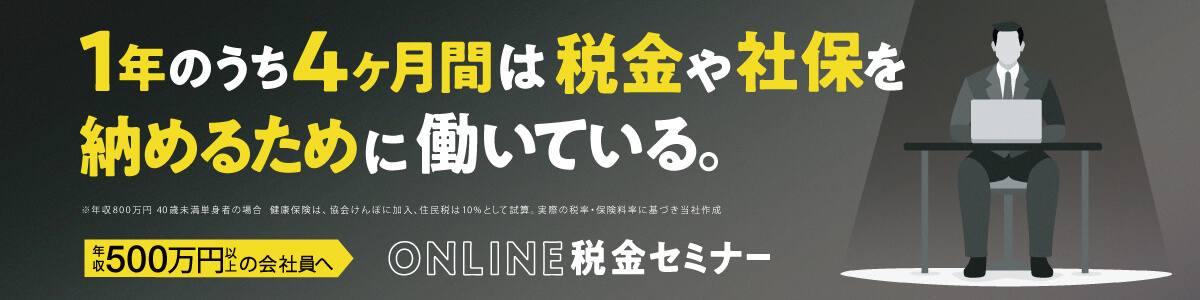
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?
人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎

記事監修者
マネカツ編集部
"将来への漠然としたお⾦への不安はあるけど、何から始めていいのかわからない…"
そんな方に向けて「資産運用」や「節税」など、お金に関する情報を発信しています。

記事監修者
マネカツ編集部
"将来への漠然としたお⾦への不安はあるけど、何から始めていいのかわからない…"
そんな方に向けて「資産運用」や「節税」など、お金に関する情報を発信しています。