投資と投機の違いは?ギャンブルやFX、貯蓄との違いも簡単に解説


記事監修者
マネカツ編集部
"将来への漠然としたお⾦への不安はあるけど、何から始めていいのかわからない…"
そんな方に向けて「資産運用」や「税金対策」など、お金に関する情報を発信しています。

記事監修者
マネカツ編集部
"将来への漠然としたお⾦への不安はあるけど、何から始めていいのかわからない…"
そんな方に向けて「資産運用」や「税金対策」など、お金に関する情報を発信しています。
資産運用への関心が日に日に増している昨今、テレビやネットニュースで「投資」や「投機」という言葉を目にすることが増えてきました。
どちらも同じような言葉に思えますが、両者には明確な違いが存在します。
この記事では、投資と投機の違いやそれぞれのメリット・デメリット、ギャンブルとの違いなどについて解説します。
これから投資を始めようと思っている方も、既に投資を行っている方もそれぞれの意味をしっかりと理解しておきましょう。
| 投資の関連記事 | |
| 株式投資の始め方 | 従業員持株会とは |
| 投資で生活可能? | 配当金で生活できる? |
| 自社株買いとは | 空売りとは |
| 10万円以下の株主優待 | 高配当株のメリット |
| 投資はいくらから? | モメンタム投資とは |
| 投資の種類 | 分散投資とは |
| 長期投資の効果 | コアサテライト戦略 |
| 複利の効果 | アセットアロケーション |
| ポイント投資の特徴 | 株主総会とは |
この記事の目次
「投資」と「投機」の違い

「投資」や「投機」という言葉には明確な定義があるわけではなく、さまざまな捉え方があります。
ただし、一般的に将来が有望な投資先に長期的に資金を投じることを「投資」、相場の価格変動を通じて短期的に利益を得ようとすることを「投機」と呼ぶことが多いです。
投資と投機の違いを挙げるとすれば、以下のようになります。
| 投資 | 投機 | |
| 投資基準 | 将来の成長性・価値 | 値幅の大きさ |
| 取引期間 | 5~10年以上の中長期 | 数秒から数ヶ月の短期間 |
| リターン | 小〜中程度 | 大きい |
| リスク | コントロール可能 | 大きい |
ここからは、投資と投機のより詳しい違いについて解説します。
将来が期待できる投資先に資金を投じる「投資」
「投資」とは、将来が有望な投資先に長期的に資金を投じる行為です。
株式や投資信託、不動産などに資金を投じる行為が投資にあたります。
投資における利益の元となる要素は、その商品の「価値」にあります。
たとえばAという上場企業が、事業で得た利益の一部を研究開発や事業投資に回したとしましょう。
数年後、研究開発によって生まれた新しい商品や、事業投資から新たに展開されたビジネスによりA社の売上が拡大すれば、株価が大きく上昇する可能性が高いといえます。
つまり、A社は自社に投資することで新たな付加価値を生み出し、その価値を源泉として事業の拡大や株価の上昇を果たしたということです。
株主も企業の価値が高まることで株価が上昇することをよく理解しています。
そのため、将来が有望な分野に投資する企業は、中長期計画を発表した段階で株価が上がり、さらに投資の結果として業績が拡大した後も株価が上昇するという好循環が生まれます。
このように将来上がるであろう価値に対して資金を投じる人を、「投資家」といいます。
企業にかかわらず新たな付加価値を生み出すには数年単位の時間がかかるため、投資をするには、じっくりと腰を据えて少しずつ資産を増やしていく心構えが必要です。
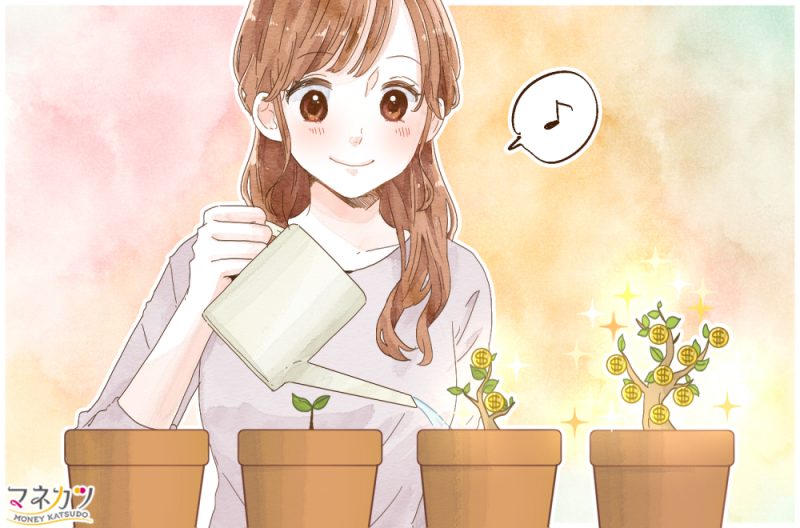
投資とは?行う目的や種類、リスクについてわかりやすく解説
相場の変動を利用して利益を狙う「投機」
投機とは、相場の価格変動を利用して短期間で利益を得ようとする行為です。
FXや仮想通貨など、基本的に短期取引に向いている金融商品は投機の性質が強く現れます。
投機における利益の元となる要素は、その商品の「価格」となります。
たとえば、過去の値動きや現在のトレンドを参考に、短期的な価格変動を予測する方法に「テクニカル分析」というものがあります。
チャートを見ながら相場を分析し、過去の傾向から「ここは買い注文を入れるタイミングだ」と判断するようなイメージです。
投資のように付加価値を生み出したから株価が上がるという理屈ではなく、あくまでこれまでの値動きの傾向から、今後の価格がどう動くのかを予測します。
ギャンブルに近いイメージです。
投機では、いかに勝てる機会(チャンス)を見極められるかが重要となります。
お金を貯める「貯蓄」
「貯蓄」とは、お金を貯めて蓄える行為のことです。
「貯金」「預金」にプラスして株式や投資信託などの投資商品、生命保険や養老保険などの保険・年金を含む保険商品等を活用してお金を蓄えることをいいます。
銀行に預金すると利息を受け取れますが、今の超低金利下の日本で高額な利益は期待できません。
その代わり、預金としての貯蓄は流動性が高く、必要な時に現金を引き出しやすい性質があります。
すぐに必要となる可能性のあるお金は投資や投機に回さず、貯蓄として保有しておくのがおすすめです。

「貯金」と「貯蓄」の違いは?「預金」との違いや資産を増やすポイント
「投資」と「資産運用」の違い

「投資」と「資産運用」も意味を混同しやすい言葉の一つです。
資産運用とは、現預金や不動産、保険など持っている全ての資産を活用してお金を増やす行為です。
投資も資産運用の一つではあるものの、資産運用のように資産を駆使してお金を増やすというより、あくまで株式や投資信託、債券など一部の金融商品に資金を投じて利益を得ることが目的となります。
また、投資よりも資産運用のほうがより長期的に資産を形成する意味合いを強く持つことが多いです。
リスクは最小限に、今ある資産を有効活用しようとするのが資産運用だといえるでしょう。
「投機」と「ギャンブル」の違い

続いて、意味が間違われやすい「投機」と「ギャンブル」の違いを具体的に解説します。
ギャンブルは娯楽に近い
ギャンブルとは、金銭や品物などを賭けて勝負を争う遊戯や、そのような行為を商用化したもので、競馬や競輪、ボートレースなどが該当します。
また、ギャンブルには決まった金額を参加者全員で取り合うという性質があるため、宝くじやパチンコもギャンブルにあたります。
ギャンブルには必ず事業者や国といった「主催者」がおり、主催者は集めたお金から運営料を差し引いた残りを当選者に配分します。
つまり、参加者が勝負に勝っても負けても主催者は損することがなく、勝った人に負けた人からお金が移動しているだけというのがギャンブルの構図です。
また、ギャンブルの勝敗は運の要素が強く影響し、再現性がありません。
一方の投機は、主催者や運営元が存在せず、相場の分析方法や見方などを勉強することで運の要素を最小限に抑え、勝率を高めることができます。
どちらも短期的に大きなリターンを狙うことは変わりませんが、リスクへの考え方が異なります。
FXは投機
投機のなかでも特に代表的な金融商品が「FX」です。
FXとは、米ドル円やユーロ円といった通貨ペア(2国間の通貨)を売買して利益を得る方法です。
基本的に通貨は、株のように企業の成長によって価値が高まるという性質がないため、短期間の価格変動を見て取引されることが多くなります。
過去の値動きや現在の世界情勢等からある程度の方向性は予測できるものの、基本的に上がるか下がるかは誰にもわかりません。
また国内のFX会社では最大25倍までのレバレッジをかけることができ、1回の取引で多額の利益を狙える反面リスクも高いことから、FXは投機だといえるでしょう。

FXとは?やり方や儲ける仕組み・始め方を初心者にもわかりやすく解説
仮想通貨は投資・投機の両面を持っている
仮想通貨は、FXで取り扱われている実在する国の通貨とは違い、何らかの目的を持って開発された金融商品です。
たとえば、仮想通貨で最も取引量が多い「ビットコイン」は、現行通貨の代替となる新たな「お金」になることを目指して開発されました。
ビットコインの次に取引量が多い「イーサリアム」は、運営元がいなくても稼働するアプリケーションプラットフォームを目的に設計されています。
このような開発思想は企業が新しい付加価値を生み出す仕組みと似ているため、仮想通貨に資金を投じる行為は「投資」といえるかもしれません。
しかし、仮想通貨の現状を見ると、短期的な価格変動率の高さに魅了された投機的な動きが目立っています。
2022年5月には、Terra(LUNA)という仮想通貨が1年間で価格を約100倍にまで上昇させた後、一夜で暴落して価値を失った出来事が起こりました。
仮想通貨の将来的な成長を見越して長期的に資金を投じるのは「投資」ですが、億り人を夢見て短期間で多額の資金を投じるのは「投機」であり、仮想通貨は両方の側面を併せ持っているといえるでしょう。

ビットコインのメリット・デメリット!仕組みや特徴、今後はどうなる?
投資のメリット・デメリット

投資と投機の違いを解説してきましたが、必ずしもどちらか一方が良い・悪いというわけではありません。
投資と投機には、どちらにもメリット・デメリットがあるため、その違いをよく理解して自分に合うものを選ぶことが大切です。
まずは、投資のメリットとデメリットを詳しく解説します。
少ない資金から始められる
少ない資金でスタートできるのが、投資のメリットです。
株式投資を例に挙げると、いままでは最低1単元(100株)を購入するだけで数十万~数百万円の元手が必要でしたが、最近は1株からでも買える「単元未満株」を取り扱う証券会社が多くなってきました。
1株であれば、銘柄によっては数百円程度で株式の購入が可能です。
また、「投資信託」でも1口100円から購入できるものや、月々数千円から積立投資できる銘柄が存在します。
資金が少ないほど損をしたときのダメージも小さくなるため、特に投資初心者の方は少額投資から始めることがおすすめです。

株初心者はいくらから投資を始めるのがおすすめ?少額投資について解説
長期保有で複利が狙える
「複利」とは、運用期間中に得た利益を再投資に回すことで元本が増えていき、時間が経過するごとに利益率が向上していくことをいいます。
100万円を年利3%で運用するケースを見ていきましょう。
1年目の利息は、「100万円 × 3%」で30,000円です。
2年目は1年目の利息を元本に加えて運用するため、利息は「103万円 × 3%」で30,900円となります。
上記の条件で運用を続けていくと、元本の100万円は以下のように増えていきます。
| 運用年数 | 利息 | 評価金額 |
| 1年目 | 30,000円 | 103万円 |
| 2年目 | 30,900円 | 106万900円 |
| 3年目 | 31,827円 | 109万2,727円 |
| 5年目 | 33,765円 | 115万9,274円 |
| 10年目 | 39,143円 | 134万3,916円 |
| 20年目 | 52,605円 | 180万6,111円 |
複利で運用することで、2年目以降に受け取れる利息が前年よりも増えていくことが分かります。
長期保有することで「複利の効果」を活かすことができ、上記の例では元本100万円が20年で約180万円まで増えました。
これが複利の力です。

複利の効果を簡単に解説!単利との違いや投資信託で効果を得る方法
結果が出るまでには時間がかかる
投資のデメリットは、結果が出るまでに時間がかかる点です。
たとえば現在行っている企業の設備投資が将来的に大きな価値を生み出す可能性があるとしても、設備の導入費を回収して利益化させるまでには少なくとも数年の時間がかかります。
企業が事業投資をして新しい市場を生み出す場合には、それ以上に時間がかかるでしょう。
いまでこそ世界の時価総額ランキングで上位に位置するAmazon(アマゾン)も、オンラインモールという新規ビジネスが市場に評価されて株価が大きく成長したのは、創業から20年以上が経過したここ最近の話です。
株式や投資信託、不動産などの長期的な成長に資金を投じる場合は、10年や20年といった長いスパンで考える必要があります。

長期投資のメリット・デメリット!おすすめの投資方法を解説
投機のメリット・デメリット

次に、投機のメリットとデメリットを詳しく解説します。
短期間で損益が確定する
投機による最大のメリットは、短期間で成果を得られることです。
短期投資には、数秒から数分単位で売買を行うスキャルピングや、1日に何度も取引を繰り返すデイトレード、1週間から1ヶ月ほど銘柄を保有するスイングトレードなどがあります。
長くても1ヶ月程度で銘柄を手放すことが多いため、投資に比べて短期間で利益を狙えるでしょう。
ただし、明確な根拠なくトレードを繰り返すだけでは勝率が高まらず、取引のたびにお金を失いかねません。
短期投資で利益を得たい場合は、少なくともテクニカル分析やファンダメンタルズ分析、トレンドを把握する方法を学んでおくことをおすすめします。

デイトレードのやり方!1日5,000円を稼ぐ銘柄の選び方やコツを紹介
価格変動に一喜一憂しやすい
短期間に何度も取引を繰り返すことになる投機では、価格変動に一喜一憂し、精神的な負担が増してしまう可能性があります。
精神的に追い込まれると、損切りすべきポイントで無理にポジションを維持してしまったり、適正な判断ができずに損失を膨らませてしまうことも多いです。
感情が取引に影響を与えてしまっている場合は、余裕を持って運用ができる「投資」に切り替えるか、常に機械的に取引を行ってくれる自動売買システムを活用するのが有効でしょう。

損切りとは?目安やタイミング、ルールやラインの決め方を紹介
投資・投機はこんな人におすすめ

投資や投機が向いている人の特徴は以下の通りです。
- 投資:じっくりと資産を増やしたい方におすすめ
- 投機:余剰資金で短期的に利益を狙いたい方におすすめ
投資はじっくりと資産を増やしたい方におすすめ
老後の生活資金や結婚・子育てに必要な資金を貯めたい方には、投資がおすすめです。
10年から20年後にまとまったお金が必要になることがわかっている資金は、投資によって長期間かけてじっくりと増やすのがいいでしょう。
投機のように日々の価格変動に巻き込まれることなく、リスクを最小限に抑えながら複利の効果を得られるのがメリットです。
投機は余裕資金で短期的に利益を狙いたい方におすすめ
ある程度まとまった余剰資金がある場合は、短期的な利益を狙う投機に着手してもいいでしょう。
FXや仮想通貨には「ロスカット」という仕組みがあり、一定水準を超える含み損を抱えてしまった際に強制的に決済される仕組みがあります。
もし生活資金で投機をしてしまい、強制ロスカットをくらってしまうと日々の生活に支障が出てしまいます。
投機は余剰資金で、少なくとも半年から1年ほど生活できるための貯蓄がある状態で行いましょう。
まとめ:投資と投機の違いを理解して使い分けよう

株式投資やFX、投資信託などを始める場合は、「投資」と「投機」の違いをよく理解しておきましょう。
投資は長期的な成長による価値向上を見極める方法で、少ない資金でリスクを抑えながら運用することが可能です。
投機は短期的な価格の動向を予測して利益を狙う方法で、うまくいけば短い期間で大きな利益を獲得できますが、その分リスクも高い傾向にあります。
投資と投機にはそれぞれ向き・不向きがあるため、両者のメリットとデメリットをしっかりと把握したうえで、自分の投資スタイルに合うものを選択しましょう。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎
| 投資の関連記事 | |
| 株式投資の始め方 | 従業員持株会とは |
| 投資で生活可能? | 配当金で生活できる? |
| 自社株買いとは | 空売りとは |
| 10万円以下の株主優待 | 高配当株のメリット |
| 投資はいくらから? | モメンタム投資とは |
| 投資の種類 | 分散投資とは |
| 長期投資の効果 | コアサテライト戦略 |
| 複利の効果 | アセットアロケーション |
| ポイント投資の特徴 | 株主総会とは |








