【2025】円高と円安はどっちがいい?今の日本の状況や金融緩和の影響を解説!
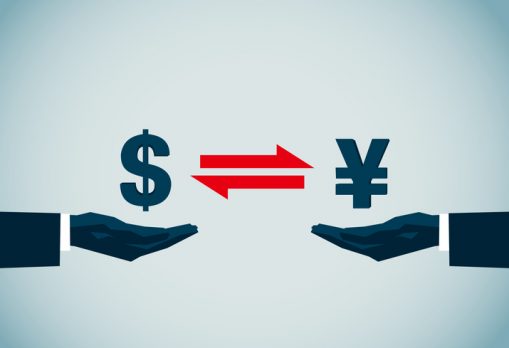

記事監修者
山口 祐平
宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー、証券外務員の資格を持つ専門家。
証券や投資用不動産の販売において、卓越した商品分析力を発揮し、幅広い商品知識を駆使して顧客に最適な投資プランを提案している。
商品特性の深い理解に基づき、複雑な金融商品や不動産投資に関するニーズに対応し、信頼性の高いコンサルティングを提供。
これまで培ってきた知識と経験をもとに、顧客の資産形成に寄与している。

記事監修者
山口 祐平
宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー、証券外務員の資格を持つ専門家。
証券や投資用不動産の販売において、卓越した商品分析力を発揮し、幅広い商品知識を駆使して顧客に最適な投資プランを提案している。
商品特性の深い理解に基づき、複雑な金融商品や不動産投資に関するニーズに対応し、信頼性の高いコンサルティングを提供。
これまで培ってきた知識と経験をもとに、顧客の資産形成に寄与している。
「円高」「円安」は、他国通貨に対する円の価値を計る言葉です。
2022年はニュースや新聞で「円安」について報じられることが多くなっており、人々の関心が高まっています。
円高になったとき、円安になったとき、それぞれが私たちの生活にどのような影響を与えるのかよくわからない方もいるのではないでしょうか。
この記事では、円高・円安についてのメリット・デメリットとわかりやすい覚え方を解説します。
円高・円安を理解すると経済ニュースへの理解が深まり、資産運用にも活用できますので参考にしてください。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎
この記事の目次
円高とは

「円高」とは、外貨と比較して円の価値が高い状態を指します。
円とドルの為替相場を例に「1ドル = 100円」を基準に考えると「1ドル = 50円」になると円高です。
100円をドルに交換するときに、「1ドル = 100円」の相場では1ドルにしか交換できませんが、「1ドル = 50円」の相場では2ドルに交換できます。
100円で交換できるドルが増えたため、円の価値が上がったと判断できます。
通貨の価値が変動する主な要因は、その通貨を購入したい人がどれくらいいるか、その通貨をどのくらい手放す人がいるか、といった需要と供給のバランスです。
例えば、日本の企業に投資したいと考える外国人が多い場合は、自国の通貨を売って円を購入する外国人が増えるため円高になります。
円安とは
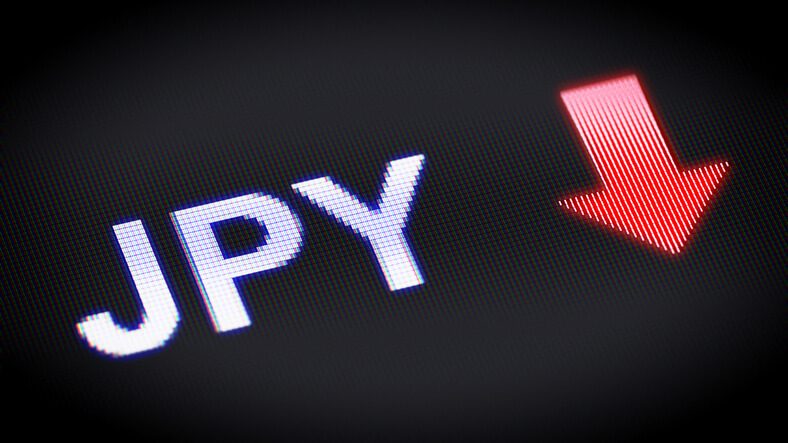
「円安」とは、外貨と比較して円の価値が低い状態を指します。
先ほどの例と同様に「1ドル = 100円」を基準に考えると「1ドル = 150円」になると円安です。
300円をドルに交換するとき、「1ドル = 100円」の相場では3ドルと交換できますが、「1ドル = 150円」の相場では2ドルにしか交換できません。
300円で交換できるドルが減ったため、円の価値が下がったと判断できます。
まとめると、1ドルあたりの円の数字が小さくなった際は円高に、1ドルあたりの円の数字が大きくなった際は円高に変動します。
今は円高・円安どっち?(2024年2月時点)

2024年2月現在、ドル円の相場は昨年に引き続き円安が続いています。
2023年末は1ドル141円台まで円高ドル安が進みましたが、2024年初からは反転して円安ドル高基調となり、2月7日時点では148円台まで円安ドル高が進みました。
昨年は米国経済が好調でインフレが加速し、アメリカで物価上昇抑制のための利上げが実施されたことで、円安ドル高の流れが続きました。
2023年9月以降、FRB(連邦準備制度理事会)は実質的な利上げを停止していますが、今後はいつ利下げに転じるかが為替市場で注目されています。
FRBのパウエル議長は、2024年1月のFOMCで3月の利下げを否定しており、どのタイミングで利下げに舵を切るかがポイントとなるでしょう。
一方、日本では金融緩和が続き、現時点では今年の大きな経済回復は予想されていませんが、賃金の状況によってはマイナス金利政策が解除される見通しです。
アメリカで利下げが始まり、日本でのマイナス金利政策が解除されれば、日米の金利差は縮小し、円高ドル安の傾向が強まる可能性があります。
ただし、為替市場ではすでに金融政策の変化を織り込み始めているため、ここから急激に円高が進むとは考えにくいでしょう。
参考:Bloomberg「FOMC、金利据え置き-3月利下げの可能性低いとパウエル議長」

利上げとは何か?インフレとの関係やローンへの影響、FRBの政策をわかりやすく解説
円高と円安はどっちがいい?

円高と円安、どちらにもメリット・デメリットがあるため、一概にどちらがいいとは言えません。
その人の立場によって考え方が変動すると言えるでしょう。
ここでの内容を参考に円高になった際、円安になった際に自身の生活にどのような影響が出るかを確認してください。
円高のメリット・デメリット

円高になると、外貨を少ない円で購入できるため、円を外貨に交換する機会が多い人にとっては有利に働きます。
その反面、外貨を円に交換する機会が多い人にとっては、円の価値が高いために収入が少なくなるので不利に働きます。
例えば米国株に投資をしている場合、株価が500ドルの場合1ドル100円(円安)の場合は日本円で50,000円になりますが、1ドル50円(円高)の時は25,000円にしかなりません。
外貨での収益が変わらない場合、円に交換した際の収益が円安のときと比較すると少なくなるのはデメリットです。
ここでは、円高のメリット・デメリットを解説します。
輸入品が安く買える
円高のときは、海外の輸入品を安く購入できます。
100ドルの商品を購入する場合を例に比較します。
「1ドル = 100円」のタイミングと「1ドル = 50円」のタイミングで比較しましたが、円高になると円を基準にした際の価格が安くなっていることがわかります。
例えば身近なものとして「iPhone」で例をあげます。
799ドルのiPhoneを1ドル100円の時と1ドル50ドルの時に購入した時では、倍金額が違います。
| 為替相場 | 日本でのiPhone価格 |
| 1ドル = 100円 | 79,900円 |
| 1ドル = 50円 | 39,950円 |
個人だけではなく、企業が輸入品を購入する際も同様です。
石油・天然ガスなどのエネルギー資源や小麦・野菜・肉などの食料などを円基準で安く購入できます。
商品を安く仕入れることができた企業が市場価格を下げると、私たちは安く購入できるようになるため、暮らしが楽になるかもしれません。
海外旅行がお得にできる
海外旅行をする際は現地の通貨を使用するため、円高のときは海外旅行をお得にできます。
お得になる理由は、少ない円で多くの外貨に交換できるからです。
例えばアメリカ旅行を計画する際に、750ドルを準備する場合で比較します。
| 為替相場 | 750ドルに交換するために必要な円 |
| 1ドル = 100円 | 75,000円 |
| 1ドル = 50円 | 37,500円 |
このように円高のタイミングでの海外旅行は円ベースで考えると必要な資金が少なく済むためお得です。
また、旅行資金として準備していたお金を全て外貨に交換する場合は、海外旅行の計画を立てていた当初よりも多くの外貨を入手できるため、円高になっていると海外旅行をより楽しむことができるでしょう。
外国人観光客が少なくなる可能性がある
円高は日本人が海外旅行する際には有利に働くものの、外国人が日本に旅行する際は不利に働きます。
先ほどの逆で、外国人が日本での観光に使う円を確保するために必要な資金が多くなるからです。
経済産業省によると、2019年の訪日外国人の旅行消費は4兆8千億円にも及び、日本経済に大きな影響を与えています。
外国人観光客が直接利用する施設以外にも、外国人が宿泊するホテルが提供する料理に使用する食材の仕入れ先の業者なども、外国人観光客の恩恵を受けているといえます。
また、外国人観光客が減少しなかったとしても、外国人の日本での消費が減少する可能性が考えられるでしょう。
外国人観光客を主なターゲットにしている方にとって、円高はデメリットになるといえます。
外国株を安く購入できる
資産運用をしている方の中には、外国の資産を保有している方もいるでしょう。
外国の資産を購入する際は、円をその国の通貨に交換してから購入することになるため、円高になると安く購入できるといえます。
特に高配当株投資を米国の個別株やETFで行う方にとって、円高は安く購入できる良いタイミングです。
将来的に円高から円安になった際には、円に換算したときの配当収入が多くなります。

【2025】米国高配当ETFのおすすめ銘柄6選!メリット・デメリットや特徴を解説
円安のメリット・デメリット

次に、円安のメリット・デメリットをまとめます。
日本の製品・輸出品が売れやすくなる
円安のときは、海外での日本のモノやサービスの価格が下がるため、輸出企業に有利に働きます。
獲得した外貨を円に交換する際も、円安が進むと多くの収益が見込める点もメリットです。
日本の輸出の上位5品目は以下の通りです。
- 自動車
- 半導体等電子部品
- 鉄鋼
- 自動車の部分品
- 半導体等製造装置
円安のときは、これらの品目を扱う企業の業績に好影響が出るでしょう。
海外旅行の支出が増える
円高のときとは反対で、円安のときの海外旅行は支出が増えます。
旅行先で使うお金を外貨ベースで準備する際は、必要な資金が多くなります。
海外旅行の支出がどのくらい増えるか、具体的な数字を使って見ていきましょう。
先ほどと同様に、為替相場別に750ドルを現金を準備する際に必要な資金を比較します。
| 為替相場 | 750ドルに交換するために必要な円 |
| 1ドル = 150円 | 112,500円 |
| 1ドル = 140円 | 105,000円 |
| 1ドル = 130円 | 97,500円 |
| 1ドル = 120円 | 90,000円 |
| 1ドル = 110円 | 82,500円 |
| 1ドル = 100円 | 75,000円 |
旅行先で観光や食事をする際は、円安のときは多くの資金が必要になることがわかります。
インバウンド需要が見込める
インバウンド需要とは、日本に訪れる外国人観光客の消費を指します。
円安の際は日本人が海外旅行をする時の費用が増えますが、その反面、外国人が日本に訪れる際の費用は抑えられます。
外貨を円に交換する際に、少ない外貨で多くの円に交換できるからです。
外国人観光客が増えることで、宿泊・観光・飲食・航空・鉄道・小売などの業界は直接収益に関係します。
さらに、インバウンド需要の増加が見込まれると、他の業界にも影響が現れます。
例えば、外国人観光客の増加に備えて、宿泊施設の改修や増築が増えると、建設業界の収益にも良い影響が出るでしょう。
外貨で受け取る収入が増える
外貨での収入がある方は、円安のときは収入が増えるといえます。
例としては、YouTubeやブログでGoogleアドセンスからの広告収入を得ている方や外国の金融資産からのインカムゲインがある方などです。
外貨での収入額そのものが変動していない場合でも、円安の影響で円ベースでの収入が増えます。
為替相場の変動によるさまざまな影響に対応するために、資産の一部を外貨で保有したいと考える方は、外貨を得られる副業に挑戦してみたり、外国の金融資産の保有を検討してみてもいいかもしれません。
円高・円安のわかりやすい覚え方

円高・円安は日常的にニュースで見聞きし、為替相場の見通しに欠かせない言葉です。
覚えづらく混乱しがちですが、理解できればニュースや経済をより深く理解することができます。
ここでは円高、円安の覚え方について解説します。
値段が高いと「円安」安いと「円高」
為替はニュースや新聞などで「1ドル110円」のように、1ドルあたりいくらと表現されていることが多いです。
為替を確認する際に注目すべきポイントは、円の部分です。
1ドルあたりの円が高いときは「円安」、円が安いときは「円高」となります。
円高・円安に明確な基準はない
円高・円安を判断する明確な基準はありません。
1ドルいくらだったら円高・円安と決まっているわけではなく、円高・円安は過去の為替水準と比較して判断されます。
経済的な観点では、直近数ヶ月の平均を基準として、円高・円安の判断をすることが多いようです。
そのため基準となる為替相場によって、現在が円高であるか円安であるかの判断が変わってきます。
例えば、2024年2月時点の「1ドル=148円」という為替は、2023年初の「1ドル=130円台」を基準にすると「円安」です。
しかし、戦後の「1ドル=360円」だった時代を基準にすると大幅な「円高」と言えるでしょう。
例えば、2013年12月〜2023年12月のドル円相場を「2021年12月のドル円相場」を基準に円高・円安の判断をすると、以下のようになります。
| 日付 | ドル円相場 | 円高 or 円安 |
| 2013年12月 | 105.08円 | 円高 |
| 2014年12月 | 119.52円 | 円安 |
| 2015年12月 | 120.53円 | 円安 |
| 2016年12月 | 116.89円 | やや円安 |
| 2017年12月 | 112.67円 | やや円高 |
| 2018年12月 | 110.18円 | 円高 |
| 2019年12月 | 108.82円 | 円高 |
| 2020年12月 | 103.24円 | 円高 |
| 2021年12月 | 115.07円 | 基準 |
| 2022年12月 | 131.11円 | 円安 |
| 2023年12月 | 141.06円 | 円安 |
出典:Yahoo!ファイナンス「アメリカ ドル / 日本 円の時系列・推移」
覚え方例1. ドルの価値と比較する
ドルを基準として、「ドルが安いか高いか」と比較して考える方法です。円ではなくドルの価値と比較します。
例えば、現在1ドル = 105円だとします。為替が、1ドル = 100円に変動した場合、それまでよりも5円少なく1ドルに交換できます。
つまり、ドルの価値は下がり、円の価値が高まったということです。これが「ドル安円高」です。
反対に1ドル = 110円に変動した場合、それまでよりも5円多く支払わないと1ドルに交換できない状況となります。
ドルの価値が高まり、日本円の価値が下がったことになります。
これが「ドル高円安」です。ドルと円の価値は、常に相反します。
覚え方例2. 円の価値を基準に考える
次は円を基準とする考え方です。
例えば、10ドルのランチを食べるとき、1ドル = 100円であれば1,000円の支払いで済みます。しかし、1ドル = 110円となると1,100円支払わなくてはいけません。
日本円で考えると、1,000円の方が安く感じ、1,100円の方が高く感じますが、円安・円高を考える際は逆の考え方となります。
1ドル = 100円のときは円の価値が高いため円高、1ドル = 110円のときは円の価値が安いため円安となります。
円高と円安の今後の見通し

円高・円安について考えるにあたって、まずは現在の状況と今後の見通しを整理していきましょう。
為替の動きは、各国の経済や貿易の状況、戦争や紛争などさまざまな要因によって左右されますが、特に注目すべきは「金融政策」です。
ここでは、アメリカと日本の金融政策の違いから、為替の動きについてみていきます。
アメリカの金利政策がもたらす影響
2023年は、アメリカがインフレを抑制するために積極的に利上げを行いました。
これにより、金利の低い日本円から金利の高い米ドルへ資金が流れやすくなり、円安ドル高の傾向が続きました。
2023年の終わり頃からは実質的な利上げが停止され、一時的に円高方向に動いたものの、2024年の年初から再び円安に進んでいます。
今後は、アメリカがいつ利下げに転じるかが為替市場の注目ポイントです。
アメリカが利上げを行うと、日本とアメリカの金利差が縮小し、結果として日本円に資金が戻りやすくなります。
反対に、アメリカが利上げに対して慎重な姿勢を続ける場合、ドル高円安のトレンドが続く可能性が高いでしょう。

利上げとは何か?インフレとの関係やローンへの影響、FRBの政策をわかりやすく解説
日本の金利政策がもたらす影響
日本では、アベノミクスが始まってから約10年間にわたって大規模な金融緩和を続けてきました。
しかし、そろそろ出口戦略に向けて方向転換が始まっているといえるかもしれません。今後、超低金利の日本が本格的に利上げに踏み切ると、円高が進む可能性も考えられます。
2023年の年末頃は、日本の金融政策が正常化するとの予想から為替が円高が進みました。
しかし2024年に入ると、年初に発生した震災の影響もあり、金利引き上げの見通しが後退したことで、再び円安が進んでいます。
今後、日銀の金融政策を予想する上では、3月中旬から始まる春闘の賃上げ動向や日本経済の回復状況に注目が集まりそうです。
これ以上円安に進む可能性は低い?
2024年の為替相場について考える上では、日米の金融政策がポイントとなります。
まず、アメリカの金融政策に関しては、1月31日のFOMCにおいてパウエル議長が3月に利下げを行う可能性は低いと発言したことで、市場では4月の利下げが期待されています。
ただし、今後のアメリカの経済指標の発表や大統領選の結果によっては、利下げの時期がずれる可能性もあるため、注目しておきましょう。
日本の金融政策については、4月にマイナス金利が解除されるというのが市場参加者の主な見方です。
ただし、賃金の伸びが予想を下回ったり、能登半島地震の経済への影響が想定よりも大きかったりする場合、金融政策の変更が遅れる可能性があります。
市場参加者の予想通りに日米の金融政策が実施された場合、これ以上円安が進む可能性は低く、徐々に円高方向に向かっていくものと考えられます。
日本の円安が終わる条件

為替市場では、2022年頃から急激に円安ドル高が進みました。
米国株に投資をしている方や、外貨建て保険に加入している方は、今後も円安が継続するのか気になるかもしれません。
結論からいうと、今後は大きく円安は進まず、緩やかに円高ドル安の流れが進むと予想されます。
円安が終わるための条件や、円高が進むと考えられる理由について確認していきましょう。
貿易赤字の解消に注目
近年、円安が進んだ一つの要因として、日本の貿易赤字拡大が挙げられます。
貿易赤字が進んだ最大の原因は、原油などのエネルギー価格の上昇で輸入額が大きく膨らんだことです。
貿易赤字が続くと、輸入代金として円をドルに交換する量が増えます。為替市場に円が多く出回ることで円安を引き起こしやすくなるという仕組みです。
原油をはじめとするエネルギー価格は、中国の景気減速の影響など複数の要因から低下傾向が続いており、貿易赤字は改善傾向にあります。
引き続きエネルギー価格が低下し続ければ、円安も解消されやすくなるでしょう。
日銀が金融政策の修正に踏み切るのか
日銀がマイナス金利政策をいつ解除するかも、為替の動きに大きく影響を与えます。
日本では、消費者物価上昇率が安定して2%を超えることを目指して、約8年間にわたってマイナス金利政策が実施されてきました。
マイナス金利政策は、金利を引き下げることで経済を刺激し、物価上昇を促進するために行われてきましたが、経済の回復や物価の上昇を背景に徐々にマイナス金利政策の解除が見込まれるようになりました。
長期金利については徐々に事実上の利上げが行われており、今後は短期金利をマイナスからゼロに引き上げるタイミングに注目が集まっています。
特に注目したいのは、3月頃に行われる春闘によってどれだけ賃金の伸びが確認できるかです。
物価上昇とともに健全に賃金が上昇していることが確認できれば、マイナス金利解除の判断材料となりやすいでしょう。
反対に、賃金上昇の伸びが想定よりも良くない場合は、マイナス金利解除の時期が遅れ、円安が続く可能性もあります。
株やFXへの影響

円高・円安が「株」と「FX」の運用に与える影響を解説していきます。
円安時の株式は比較的ポジティブな影響
円安が不利に働く銘柄・業種もあるため、特に個別株の取引を行っている方は銘柄ごとに円安が与える影響を分析する必要がありますが、円安時の日本株は比較的ポジティブな影響を受けやすいです。
円安時は、輸出企業やインバウンド需要が見込まれる業種の株価が上がりやすい傾向にあります。
たとえば自動車メーカーや旅行関連の銘柄などが該当します。
円安時は外国人にとって手元の資金で多くの円を交換できるタイミングであるため、海外からの資金が株式市場に流入しやすい点も特徴です。
海外の投資家が「日本市場が割安傾向」だと判断すると、日本株への投資が増えて株価の上昇が期待できます。
FXはファンダメンタルズの影響で方向感が決まりやすい
FXの方向感は各国の金利差で決まることが多いです。
金利が高い国の通貨を保有する方が利息が多くもらえるため、金利が高い国の通貨に資金が集まりやすい傾向があります。
ドル円相場で考えると、日本は長く低金利政策を継続していますがアメリカは利上げを続けているため、現在はドルに資金が流れて円安ドル高が続いている状況です。
FXでは各国の金利差以外にも、他の金融政策や政府・中央銀行が発表する経済指標、金融政策や財政政策に大きな影響を与える要人の発言、地政学リスクといった「ファンダメンタルズ」の析が重要です。
今後の方向感をつかむためには、まず各国の金利を確認して日本だけではなく世界のニュースに注目し、FXの方向感を分析してください。

FXとは?やり方や儲ける仕組み・始め方を初心者にもわかりやすく解説
まとめ:円高・円安は相対的に決まる

「円高・円安はどっちがいい?」という疑問に対しては、一概にどちらがいいとはいえません。
円高にも円安にもメリット・デメリットがあるからです。
円高とは、外貨の価値と比較して円の価値が高い状態であり、円安とはその反対で円の価値が低い状態です。
「1ドル = 100円」を基準に考えると「1ドル = 50円」のときは円高、「1ドル = 150円」のときは円安になります。
外貨預金やFXなどを始める際は、円高・円安の仕組みについてしっかり理解してから行いましょう。
┏──────────────┓
現在開催中の無料セミナーはこちら!
┗──────────────┛
▶︎▶︎【年収上げるよりも手取りが増える?】◀︎◀︎
▶︎▶︎オンライン税金セミナーの日程を確認する◀︎◀︎
▶︎▶︎【女性限定】 私にあったお金のふやし方って?◀︎◀︎
▶︎▶︎人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程はこちら◀︎◀︎
| 投資の関連記事 | |
| 株式投資の始め方 | 従業員持株会とは |
| 投資で生活可能? | 配当金で生活できる? |
| 自社株買いとは | 空売りとは |
| 10万円以下の株主優待 | 高配当株のメリット |
| 投資はいくらから? | モメンタム投資とは |
| 投資の種類 | 分散投資とは |
| 長期投資の効果 | コアサテライト戦略 |
| 複利の効果 | アセットアロケーション |
| ポイント投資の特徴 | 株主総会とは |








